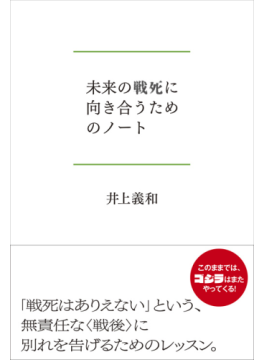女性活躍の環境整備や行財政改革などの成果を強調
東京大改革2・0。これまで進めてきた改革をさらに進めていく意味で、今回の出馬の決意を新たにした」。
フラッシュを浴びながら、小池氏はボードを掲げるおなじみのスタイルで、晴れやかに訴えた。女性活躍の環境整備や行財政改革などの成果を強調。今後も新型コロナ対策に取り組むとし、「都民の命を守ると同時に、経済をよみがえらせ『稼ぐ』東京を実現する」と力を込めた。
一方、前回知事選の公約で大半が未達成の「七つのゼロ」への自己採点を問われると、「都民に採点いただくもの」とかわし、実現していない「スギ花粉ゼロ」への質問には「揶揄(やゆ)する質問かと思う」
-----------------------------------
2020年7月8日 NHK特集記事
積極的な理由から消極的な理由まで選択肢は9つ。最も多かったのは
▼「他の人より良さそうだから」の25%。
次いで
▼「新型コロナウイルス対策を支持するから」の23%、
▼「実行力があるから」が22%と続く。
▼「実績が十分だから」は11%、
▼「新型コロナウイルス対策や東京オリンピック・パラリンピックに関する政策以外を支持するから」は2%にとどまった。
新型コロナへの対策が好評と受け止められたようだ。
小池知事の新型コロナ対応 評価は?
実際、新型コロナをめぐる小池の対応の評価はほかの政治家と比べても高い。
今回は都民のみが対象の調査ではあるが、あえて、東京・神奈川・埼玉・千葉の各都県の知事、今回の対応で全国的に注目された大阪・北海道の知事、そして安倍総理大臣の、あわせて7人の新型コロナへの対応をそれぞれ評価してもらった。
すると、「評価する」(とても+ある程度)の割合のトップは大阪府の吉村知事だった。小池はこれに続く2番目で、神奈川・埼玉・千葉の各知事や安倍を大きく上回った。
都知事選挙が迫る中で、日本、そして東京を襲った新型コロナ。その対応に対する都民の見方が知事の評価に大きく影響した可能性も見えてきた。小池への評価が新型コロナへの一連の対応で変わったかどうかを尋ねたところ、「変わらない」(49%)が最も多くなった一方で、3分の1余りに当たる35%の人が「評価が上がった」と答えたのだ。
新型コロナ対応で増した小池の存在感、さらには評価の高まりが都知事選挙での大量得票を後押しした可能性がある。
新型コロナ対応 評価の理由は発信力!?
では、具体的にどの部分が評価されたのだろうか。都が実施した新型コロナの対応について、6つの項目をそれぞれ評価してもらった。
▼「緊急事態宣言中の外出自粛などの都民への呼びかけ」を「評価する」(とても+ある程度)と答えた人は最も多い71%、
次いで、
▼「軽症者・無症状者を受け入れる施設の確保」が続く。
▼「東京アラートによる警戒の呼びかけ」は、37%にとどまった。
都内で初めて感染者が確認されたのは、ことし1月24日。その後、小池は、さまざまな「横文字」とフリップを使って、都民に警戒を呼びかけた。時には「オーバーシュート(爆発的な感染拡大)」や「ロックダウン(都市の封鎖)」といった強い表現も用いながら。
大型連休中の外出を控えてもらうため、4月下旬には「ステイホーム週間」という言葉を、感染状況の悪化の兆候が見られた6月の頭には「東京アラート」という独特なフレーズも使い、レインボーブリッジと都庁を赤く染めた。
さらに、記者会見だけでなく都の公式動画やSNSでも都民向けのメッセージを配信。知事が前面に出て外出自粛などへの協力を求めるスタイルが全国で広がる中、民放のキャスターや「クールビズ」の旗振り役の環境大臣として培った発信力は、ほかの知事と比べても抜きん出ていた。
小池の資質や能力について、20の項目を挙げ、持ち合わせているか、持ち合わせていないかを尋ねた。それぞれの上位5項目がこちらだ。
「持ち合わせている」の中で最も高かったのが「発信力」の82%。
次いで高かったのは「リーダーシップ」(72%)や「決断力」(68%)。その象徴的な場面が一連の新型コロナウイルスをめぐる対応の中でも見られた。休業要請をめぐる国との水面下の攻防だ。
対象とする業態を広げたい都。一方で経済への深刻な影響を避けたい国。両者で考え方に溝が生じたのだ。小池は、新型コロナ対策を担当する西村経済再生担当大臣と会談。最終的に6つの業態や施設に休業を要請するとともに、要請などに全面的に協力する中小の事業者への協力金の支給もいち早く決めた。その後この動きに追随する自治体が相次ぐことになる。小池は記者会見で「地域の特性に合わせた対策を決める権限はそれぞれの都道府県知事に与えられたもの。もともと代表取締役社長かと思っていたら天の声がいろいろと聞こえてきて中間管理職になったような感じ」と国への不満を口にした。国と対峙する知事の姿を都民に印象づけた形だ。
一方で、「持ち合わせていない」と答えた人が多かったのが「弱者への共感」(62%)や「将来像を描く力」(54%)だ。
社会的、経済的に厳しい立場にある「弱者」への配慮を忘れないでほしいという思い。また、新型コロナの第2波が懸念される中で、知事は東京の将来をどうするつもりなのだろうという不安。多くの人がこうした気持ちを抱いていることの表れかもしれない。
どうなった?「7つのゼロ」
では、都民は、新型コロナ対策以外の都政運営をどう見ているのだろうか。私たちは、小池が4年前の選挙公報で公約の1つとして掲げた「7つのゼロ」に注目した。
東京都によると、このうち「ペットの殺処分」は平成30年度にゼロを達成したとしている。一方、「待機児童」は平成28年に8466人だったのを、およそ2300人に。また「無電柱化」は対象となる都道の2328キロのうち41%で実現。いずれも減らしはしたものの、ゼロにはなっていない。このほか都庁職員の「残業」は増加、「満員電車」は横ばいだ。「介護離職」と「多摩格差」は数値の比較ができないなど検証が難しい。
先月12日の立候補表明の記者会見。「7つのゼロ」の自己採点を問われた小池は、待機児童の数は「格段に減少した」と実績を強調した一方で、「何点かというのはむしろ都民の皆様方にご採点いただくものだと思っております」と述べ、質問に明確に答えなかった。
では、都民はどの程度実現できたと考えているのだろうか。
▼「とても実現できた」と答えた人は、いずれの項目もごくわずかだ。
▼小池が成果を強調した「待機児童ゼロ」ですら、「ある程度実現できた」と答えた人は21%にとどまった。これは小池への投票層に限っても34%だ。
「公約を知らない・わからない」が3割を超えた項目もあり、「7つのゼロ」の達成度合には都民の厳しい目が向けられていることが浮き彫りになった。
小池知事の新型コロナ対策は一定の評価を得ている一方で、都政運営全体が手放しで評価されているわけではなさそうだ。
4割が「収入減」暮らしへの不安は
調査では、新型コロナによる生活への影響も尋ねた。まず、世帯収入がどうなったのか見てみる。
▼「変わらない」(57%)が過半数を占めた一方で、
▼「減った」(大きく+ある程度)と答えた人は4割を超えた。
職業で見ると、「自由業(フリーランス)」(63%)、「自営業」(61%)、「パート・アルバイト」(57%)は特に影響が大きいことが分かる。半数以上が「減った」と答え、「大きく減った」の割合も高い。
新型コロナ感染拡大後の暮らしにどの程度不安を感じているか、8つの項目を挙げてそれぞれ尋ねたところ、「新型コロナ感染時の適切な治療」と「自分や家族への新型コロナの感染」では8割以上が「不安を感じている」(とても+ある程度)と答えた。
また、「収入の減少」は「不安を感じている」が57%。
特に、職業別に見ると、「契約・派遣社員」(71%)、「自由業(フリーランス)」(71%)、「自営業」(70%)といった層では「不安を感じている」人たちの割合が会社員や公務員といったほかの職業の人たちより高くなっている。
今後、収入が減るのではないかと不安を抱えている層は、新型コロナの感染拡大で世帯収入が「減った」という回答層と重なる。こうした層は新型コロナが感染拡大する中で、とりわけ手厚い支援の必要性が指摘された人たちだ。さらなる苦境に陥らないよう配慮の行き届いた政策遂行が求められている。
優先すべき政策は
しばらくは避けられそうにない「ウィズコロナ」の生活。しかし、都政の課題は新型コロナの感染拡大だけではない。
では、都民は知事に今後どのような政策に取り組んでほしいと思っているのだろうか。分野ごとに、それぞれ6つの政策を具体的に挙げて、優先的に取り組んでほしいこととしてあてはまるものをすべて選んでもらった。
まず「経済・雇⽤」を見てみる。「新型コロナの影響を受けた中⼩企業への⽀援」(55%)が最も多かった。
回答を詳しく見ると、何に優先的に取り組んでほしいのか、職業によって異なることが分かった。
▼「会社員」「公務員/団体職員」「学生」は「企業の『働き方改革』の支援」を一番に求めていた。「働き方改革」への意識が高まるなか、現場で働く人や将来仕事に就く人にとって重要な課題なのだ。
▼「契約・派遣社員」「無職」は「失業者への雇用支援」に期待する声が特に多かった。
次に「医療・福祉」。この分野では「新型コロナに対応した医療体制の充実」(61%)が最も多くなった。やはり都⺠が新型コロナ対策を喫緊の課題と捉えていることが読み取れる。この政策を選んだのは、重症化のリスクが⾼いとされる「60代」(66%)や「70代」(68%)で特に高かった。
「まちづくり」では、緊急事態宣言が解除されて電車が混み合うようになったことも影響したのか、「通勤電車の混雑緩和対策」(62%)と答えた人が最も多かった。「学生」「公務員/団体職員」「契約・派遣社員」「会社員」といった毎日の通勤通学で電車を利用しているとみられる層の求めが強い。
「教育・子育て」では、小池知事の「7つのゼロ」の1つ、「待機児童の解消」(46%)も、依然として30代以下の若い人たちを中心に優先順位の高い政策のようだ。
「防災」では、「豪雨対策」(50%)が最も多くなった。毎年のように甚大な被害をもたらす豪雨災害。去年も台風19号で各地に大きな被害が出て、都内でも住宅が水に浸かった。いまも九州を中心に被害が広がっていて、都民もひと事ではない。
優先的に取り組んでほしい政策を都政に詳しい専門家はどう見るのか。都庁に36年間勤め、石原慎太郎知事時代には副知事を務めた明治大学の青山佾(やすし)名誉教授に読み解いてもらった。
多くの人が新型コロナ関連の政策や豪雨対策といった都民の命を守る取り組みを求めていると指摘し、「新型コロナは目の前の危機であり、それへの対策に取り組んでほしいというのは当然だ。また、去年の台風19号では、海抜ゼロメートル地帯が広がる江東5区(墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区)で広域避難が課題になるなど、防災への関心も高い。都民は安心や安全のための対策を望んでいることがうかがえる」と分析する。
一方で、かつて都政の中枢にいた経験からこうも言及した。
「電車の混雑緩和のために鈴木都政で始まった都営大江戸線の建設は石原都政で完成した。当時はいろいろ言われたが完成したら好評だった。このように、後世のために長期的な視点で取り組む必要もある。今回、コロナ後の新しい生活の在り方も含めて長期ビジョンを作り直すいいタイミングだ。ここ数か月は目の前の対応に追われてきたが、コロナ後の長期的な東京の在り方を示すことが求められている」
投票日の今月5日午後8時すぎ。新宿区の事務所で当選確実の知らせを受けた小池は、報道各社のインタビューで、新型コロナのさらなる感染拡大に備えて医療体制を充実させるため、東京都版のCDC=疾病対策予防センターを創設して迅速で効率的な対応を目指すとともに、厳しい経営状況にある医療機関を支援していく考えを示した。そして「命と経済を守る東京都、そして世界の中での都市間競争に打ち勝つ東京を進めていきたい」と抱負を述べた。
都民の意見に耳を傾ける政治を
新型コロナの感染拡大防止策と経済活動の両立。いま、都政はかつてない難題に直面している。次々に打ち出したこれまでの対策で都の財政状況は厳しさを増し、1兆円近くあった、都の貯金にあたる「財政調整基金」は大半を取り崩した結果、現時点の見込みで807億円にまで減った。
いまの都政は都民の意見が反映されていると思うか尋ねたところ、「反映されていない」(あまり+全く)は64%。「全く反映されていない」は1割を超えた。
終息がまったく見通せない新型コロナウイルス。都民の暮らしへの影響はこれからさらに深刻化することも予想される。今後、都の税収は減るとみられ、厳しい財政運営を迫られることになるだろう。都民の声に真摯に耳を傾けながら、どう都民の暮らしを守っていくのか。2期目の小池に課せられた責任はとてつもなく重い。
(文中敬称略)
【調査概要】
調査期間:2020年6月21日~24日
調査方法:インターネット
調査対象:楽天インサイトに登録しているモニターで東京都内在住の18歳から79歳までの都民1万人
※年齢・性別が偏らないように総務省の最新の人口推計の比率に近くなるように回収
質問項目:146