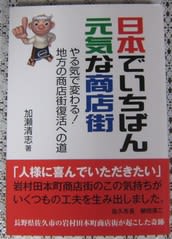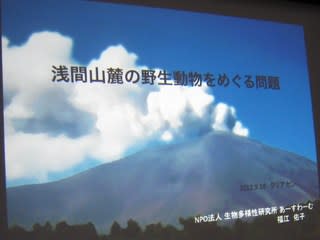先ほど、学校に戻ってまいりました。
今日は、河井継之助記念館の稲川館長さんの記念講演「河井継之助と山本五十六に見るリーダーの在り方」をお聞きしました。
今日も大変勉強になりました。
河井継之助は、幕末維新期の北越戊辰戦争で新政府軍と戦った長岡藩の家老上席であった人物です。
また、長岡といえば、「米百俵」の故事が有名ですね。
河井継之助が率いた北越戊辰戦争で敗れた長岡藩は、知行を減らされました。藩士たちはその日の食にも事欠く状態でした。このため窮状を見かねた長岡藩の支藩三根山藩(みねやまはん:現在の新潟市西蒲区峰岡にあった藩)から百俵の米が贈られることになりました。
藩士たちは、これで生活が少しでも楽になると喜びましたが、藩の上役小林虎三郎は、贈られた米を藩士に分け与えず、売却の上で、学校設立の費用とすることを決定します。藩士たちはこの通達に驚き反発して虎三郎のもとへ押しかけ抗議しますが、それに対して虎三郎は、
「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる(学校を建てて人材を育てる)」
と諭し、自らの政策を押し切ったのでした。
小泉首相が、内閣発足直後の国会の所信表明演説で、「米百俵の精神」として、引用して有名にもなり、2001年の流行語にもなりました。
この信州でも、学校設立時期の話として、「村人達が自分の食べるものを減らしてでも、お金を集め、町村立(組合立)の学校をつくった」話を思い出しますね。
軽井沢高校も、「昭和十八年、地元の要望を受け、町立軽井沢高等女学校が創立されました。設立当初は、高等女学校とは名ばかりで、独自の校舎もなく小学校の教室を借りて授業が行われるという状態でした。戦後の学制改革で新制高校として再出発したものの、戦後の貧しさの中ですべてが貧しい状態でした。そんな中で先生も生徒も自分たちの手で校庭を作り、校門を建て学園を創りだしていきました」とあります(小川貢同窓会長の文から『軽井澤高等学校四十年の歩み』)。当時の軽井沢、町内に中等教育機関はなく、一番近くても小諸市内の学校でした。現在の小諸商業と小諸高校です。男子の場合、普通教育を学ぶには、現在の岩村田高校か上田高校が一番近い学校でした。女子は、小諸高校だったでしょうか。
山本五十六は、「やってみせ、いってきかせて、させてみて、誉めてやらねば、人は動かじ」という言葉も有名な、先の大戦を戦った海軍軍人ですよね。
ある雑誌を読んでいた時に、「校長は、平穏無事なときは、ビジョンを示すだけでいいが、一旦事が起こった時には、先頭に立って事態の収拾にあたらなければならない」とありましたが、河井継之助にしろ山本五十六にしろ、まさに、「一旦事が起こった時」のリーダーでありました。一方、緊急事態の備えを絶えず意識していた人物でもありました。
学校では、2年生の国際文化科の生徒が、今日から明日にかけて、町内のベルデ軽井沢で「英語キャンプ」を実施しています。

上の写真は、キャンプのしおりです。
英語科の長嶋先生と漆原先生及びALTのアシュリーには、事前の準備から当日の引率までお世話になります。
本日は、他校からのALTの協力、長野外語カレッジの協力、さらに成城大学の打越教授のご支援を受け、さまざまな取組を行う予定です。
明日は、軽井沢ガイドサービスの永島さんのご協力を得て、ALTを相手に旧軽井沢中心に英語で観光案内する学習を行います。
今年の合宿の特徴的なことを聞きました。
1 「軽井沢森の詩かるた」の英語訳を作成し、生徒がこのかるたの作成にに深く関わった打越成城大学教授の前で発表する。
2 「軽井沢森の詩かるた」大会 2人一組のチームを作り、源平戦で勝敗を決するとのことです。町内の一般の方も参加してくださいます。
3 長野外語カレッジの先生方と留学生の皆さんとの交流を行います。
4 ALTを相手に(外国からの観光客になっていただき)、軽井沢駅から旧軽井沢周辺を、英語で観光ガイドを行う。
このことについては、8月28日の「校長日記」ですこしふれました。
聞いただけで、わくわくするような英語合宿です。
「PDCAサイクル」という言葉があります。
PはPlan(計画) DはDo(実践) CはCheck(点検) AはAction(行動)
あらかじめ計画を立て、その計画に基づき実践し、結果を検証する。その検証に基づき、新たな行動にうつすということでしょうか。
この英語合宿の近年の流れを見ていますと、まさに、この「PDCAサイクル」を見事に実践していて、毎年、前年の反省を生かし、「よりよいものに改善」しています。
物事をゼロから立ち上げる苦労も大変なことです。また、一度立ち上げたプロジェクトをさらによりよいものにしていくことも、これもまた大変なことであります。生徒のために、さまざまなことを考え、本校の先生方だけでおこなうのではなく、他校のALTや地域の皆さんなどのご支援を賜り、実施しているこの英語合宿、手前味噌で恐縮ですが、すばらしいものだと私は思っています。
生徒たちがこの合宿で一段と成長することを期待しています。
1学年では、10月実施の学習合宿説明会及び11月実施の就業体験オリエンテーションを実施しました。
☆追伸 9月18日18時
先ほど、軽井沢タリアセンから戻り、英語合宿の様子を英語科の長嶋先生から伺いました。
生徒からのアンケートはこれからとるそうですが、おおむね、好評だったようです。

まずは、ALT及び長野外語カレッジの留学生相手に英語で自己紹介中

長野外語カレッジの皆さんが帰られる前の記念撮影

打越成城大学教授の講演会

軽井沢森の詩かるた、源平戦の様子
軽井沢町議会の正副議長さんにも来ていただき、かるたに参加しました。
ありがとうございました。
ベルデ軽井沢の手水さんにはさまざまご配慮を賜りました。
こちらもありがとうございました。
カルタを畳の部屋で実施できるなんて、なんともありがたいご配慮です。

15日午前、旧軽井沢にて、英語を使い、ALTに観光ガイド中の生徒たち
☆追伸9月20日
英語合宿の様子をまとめました。以下からご覧いただけます。
http://www.nagano-c.ed.jp/karui-hs/120906-eigogassyuku.pdf
☆追伸11月2日
打越先生のブログを以下からご覧いただけます。
http://karuizawa-cross.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-b4cd.html