斎藤美奈子の『名作うしろ読み』を読んでいる。
小説のはじまりは、よく語られるのだが、「たとえば、トンネルを抜けるとそこは・・・」とか、しかし、その最後は語られない。
その最後の言葉を記して、その小説を簡単に論じるのがこの本のみそ。とはいえ、1つの小説で、見開き2頁なので、そう長くはない。もともと、新聞連載のものをあつめたもの。
この斎藤という人、小説などの解説の解説をしてみたり、最後に注目してみたり、以外と面白い発想をする。
とはいえ、今回の本で考えたのは、文章の最後の部分ということ。
よく、論文の最後の締めをどうするか悩む。結論があるわけじゃない場合もあり、終わり方がわからない・・・。これでいいやという踏ん切りができないときは、だらだらと書いてしまって、結局何が言いたかったのかわからなくなっちゃうという経験を積んできた。
そういう意味での、最後のことばをみてみると、その論文や文章を書いた人の人柄や、躊躇、葛藤などもほんのりと判るのかもしれない。
小説のはじまりは、よく語られるのだが、「たとえば、トンネルを抜けるとそこは・・・」とか、しかし、その最後は語られない。
その最後の言葉を記して、その小説を簡単に論じるのがこの本のみそ。とはいえ、1つの小説で、見開き2頁なので、そう長くはない。もともと、新聞連載のものをあつめたもの。
この斎藤という人、小説などの解説の解説をしてみたり、最後に注目してみたり、以外と面白い発想をする。
とはいえ、今回の本で考えたのは、文章の最後の部分ということ。
よく、論文の最後の締めをどうするか悩む。結論があるわけじゃない場合もあり、終わり方がわからない・・・。これでいいやという踏ん切りができないときは、だらだらと書いてしまって、結局何が言いたかったのかわからなくなっちゃうという経験を積んできた。
そういう意味での、最後のことばをみてみると、その論文や文章を書いた人の人柄や、躊躇、葛藤などもほんのりと判るのかもしれない。












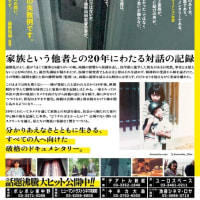




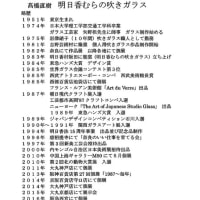

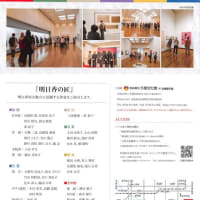
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます