障害児学研究室(障害児学教室)開設50周年を祝う
1966(昭和41)年4月、奈良教育大学に養護学校教員養成課程が設置された。養護学校教員養成課程の設置から本格的に障害児教育の教員養成が開始され、50年を経たこととなる。
教員養成系大学・学部における、養護学校教員養成課程に設置は、1960年度、東京学芸大学・広島大学に最初に設置され、1962年度に静岡大学、1963年度、京都学芸大学・大阪学芸大学、熊本大学、1964年度、金沢大学・山梨大学・愛知教育大学・高知大学、1995年度、弘前大学、山形大学、千葉大学、福井大学、岐阜大学、鳥取大学、岡山大学、香川大学と続いた。こうして、1966年度に、茨城大学、三重大学、神戸大学、島根大学、山口大学、徳島大学、福岡教育大学と並んで、奈良教育大学に設置されることとなったものである。最終的に、全都道府県に養護学校教員養成課程が設置されたのは、1973年度の鹿児島大学での設置を待たなければならない。すでに、50周年を経た大学での年史等が出されたことは寡聞にしてきかないので、すこしばかり、設置された時代に遡って障害児教育の教員養成について振り返って書いておくことは無駄なことではあるまい。
戦後教育の再出発は、1947年の教育基本法・学校教育法の公布によって開始される。6-3-3-4制の学校体系とし、そのうち、小学校と中学校の9年間を義務教育制度とした。盲学校、聾学校の義務制実施は、1年遅れた1948年度より、学年進行によって行われたが、養護学校の義務制の実施は、見送られることとなった。教員養成は、科学と教育を結ぶものとして、大学における教員養成のシステムが取られ、戦前教員養成を担ってきた師範学校は、組織再編されて新制大学に統合されることとなった。奈良師範学校は、奈良学芸大学として、1947年に出発することとなった。
戦後障害児教育の教育と研究、そして教員養成については、東京盲学校師範部、東京聾学校師範部から国立盲教育学校、国立聾教育学校を経て、1951年、東京教育大学教育学部の特設教員養成部の盲教育部及び聾教育部となり、あわせて同じ年に設置された東京教育大学教育学部特殊教育学科とともにはじまる。1953年には、広島大学教育学部に盲学校教員養成課程、東京学芸大学に聾学校教員養成課程が設置され、盲学校、聾学校の教員養成が開始されることとなった。しかし、養護学校については、教員養成どころかその設置が遅々として進まず、ようやく1956年6月、公立養護学校整備特別措置法が公布され、その設置と教員雇用に国庫補助が適用されることとなった。
1959年には中央教育審議会が「特殊教育の振興について」の答申を出し、特に知的障害者(当時のことばでは「精神薄弱者」)や肢体不自由者の教育が諸外国に比べ著しく遅れていることを指摘するとともに、これらの教育を担当する教員の養成をはかる必要のあることを指摘した。それをうけて、主として現職教員を対象とする臨時の養護学校教員養成課程を5大学(北海道学芸大学、東京学芸大学、京都学芸大学、広島大学教育学部、熊本大学教育学部)に設置した。この臨時養成課程は、知的障害教育を対象として、各大学とも1年コース(定員20名)と半年コース(各期定員20名)というものであった。研修旅行などでお世話になった京都府立与謝の海養護学校の開校と学校づくりを担ってこられた故青木嗣夫先生も、京都学芸大学臨時養護学校教員養成課程が設置された1960年の後期半年コースで学んでいた。
1960年代、先に見たように養護学校教員の養成課程の本格的な開設となり、それと並行して、教育課程ということでも、1963年4月にはじめての養護学校学習指導要領(小・中学校部精神薄弱教育編、小学部肢体不自由教育編及び小学部病弱教育編)が通達された(中学部肢体不自由教育編及び中学部病弱教育編は、1964年3月に通達)。
養護学校設置への国庫補助、教員養成や学習指導要領の整備の基礎は整えられたが、養護学校の設置はそのままでは進展し得ない。全国の都道府県での養護学校の設置の進展は、養護学校に関する義務制が未施行であったため、進む状況ではなかった。文部省は、中央教育審議会答申に基づいて、肢体不自由養護学校設置と知的障害特殊学級の計画設置を重点的に推進することとし、肢体不自由養護学校については、1960年度を初年度とする5カ年計画で、1964年までに未設置県の解消を図るものとし、知的障害学級については1969年度を初年度とする5カ年計画を作成した。しかし、その計画はそのとおりには進まず、その後修正され、肢体不自由養護学校の未設置研の改称は、1969年度を待たなければならなかった。奈良県では、1966年に、現在の奈良県立明日香養護学校(当時、奈良県立養護学校)が設置された。知的障害の養護学校については、1970年代にはいり、1971年に奈良県立西の京養護学校(現在の奈良県立東養護学校、西養護学校の母体となった学校)の開校を見ることとなった。
ところで、国立大学では、1958年、東京教育大学教育学部附属養護学校(肢体不自由)、1960年、東京学芸大学附属養護学校(精神薄弱)が設置されていくが、多くの大学附属では特殊学級の設置がなされていった。ちなみに、1963年4月、本学附属小学校、1965年4月、附属中学校に、それぞれ「特殊学級」が設置され、すでに50周年を経ている。附属小学校・中学校の学級設置におくれて、1966年度に養護学校教員養成課程が設置されたこととなる。この半世紀の間に、障害のある子どもたちをめぐる状況も大きく変化した。
当時の養護学校教員養成課程の開設当時の「特殊教育」の科目は、「異常児」を冠されて「異常児心理」「異常児教育」などの科目で開講される場合が大方だったが、本学では、「障害児」の名称を掲げて、心理分野を柳川光章先生、教育分野を津曲裕次先生が担当となって、教室・研究室名を「障害児学」を冠するものとされた。田辺正友先生が着任されるとともに、津曲先生の転出で着任した大久保哲夫先生、また学内措置で医学分野に藤井伸先生が着任され、「障害児学研究室」の発展の基礎を培われた。当時としては、「障害」への着眼とその支援を総合的に行おうとする意欲的な用語使用と思われる。
「特殊教育」の用語から、「障害児教育学」「障害児心理学」障害児医学」「障害児福祉学」などの学問分野を総合して「障害児学」とされたものと受けとめられる。「特殊教育」の用語は、いくた議論の末、2007年に「特別支援教育」に移行し、今日にいたる。奈良教育大学養護学校教員養成課程や大学院での養成のシステムも大学改革と障害児教育の発展の中でいくたびか改組されることとなったことは別の論考と年史・年表によって確認してほしい。
学部、臨時養成課程、特別専攻科、大学院教育学研究科など、これまで、本学の障害児教育・特別支援教育の学びと研究の中で、多くの方々が実に真摯にともに学び、ともに成長し合ってきた。障害児学研究室を構成してきたすべての方々とともに、その実りの多い日々の記憶をこれからも糧として、障害のある子どもたちの未来を切りひらく努力とそのために研鑽に励むことを誓い合いたい。
『障害児学研究室50年の歩み』2016年9月
1966(昭和41)年4月、奈良教育大学に養護学校教員養成課程が設置された。養護学校教員養成課程の設置から本格的に障害児教育の教員養成が開始され、50年を経たこととなる。
教員養成系大学・学部における、養護学校教員養成課程に設置は、1960年度、東京学芸大学・広島大学に最初に設置され、1962年度に静岡大学、1963年度、京都学芸大学・大阪学芸大学、熊本大学、1964年度、金沢大学・山梨大学・愛知教育大学・高知大学、1995年度、弘前大学、山形大学、千葉大学、福井大学、岐阜大学、鳥取大学、岡山大学、香川大学と続いた。こうして、1966年度に、茨城大学、三重大学、神戸大学、島根大学、山口大学、徳島大学、福岡教育大学と並んで、奈良教育大学に設置されることとなったものである。最終的に、全都道府県に養護学校教員養成課程が設置されたのは、1973年度の鹿児島大学での設置を待たなければならない。すでに、50周年を経た大学での年史等が出されたことは寡聞にしてきかないので、すこしばかり、設置された時代に遡って障害児教育の教員養成について振り返って書いておくことは無駄なことではあるまい。
戦後教育の再出発は、1947年の教育基本法・学校教育法の公布によって開始される。6-3-3-4制の学校体系とし、そのうち、小学校と中学校の9年間を義務教育制度とした。盲学校、聾学校の義務制実施は、1年遅れた1948年度より、学年進行によって行われたが、養護学校の義務制の実施は、見送られることとなった。教員養成は、科学と教育を結ぶものとして、大学における教員養成のシステムが取られ、戦前教員養成を担ってきた師範学校は、組織再編されて新制大学に統合されることとなった。奈良師範学校は、奈良学芸大学として、1947年に出発することとなった。
戦後障害児教育の教育と研究、そして教員養成については、東京盲学校師範部、東京聾学校師範部から国立盲教育学校、国立聾教育学校を経て、1951年、東京教育大学教育学部の特設教員養成部の盲教育部及び聾教育部となり、あわせて同じ年に設置された東京教育大学教育学部特殊教育学科とともにはじまる。1953年には、広島大学教育学部に盲学校教員養成課程、東京学芸大学に聾学校教員養成課程が設置され、盲学校、聾学校の教員養成が開始されることとなった。しかし、養護学校については、教員養成どころかその設置が遅々として進まず、ようやく1956年6月、公立養護学校整備特別措置法が公布され、その設置と教員雇用に国庫補助が適用されることとなった。
1959年には中央教育審議会が「特殊教育の振興について」の答申を出し、特に知的障害者(当時のことばでは「精神薄弱者」)や肢体不自由者の教育が諸外国に比べ著しく遅れていることを指摘するとともに、これらの教育を担当する教員の養成をはかる必要のあることを指摘した。それをうけて、主として現職教員を対象とする臨時の養護学校教員養成課程を5大学(北海道学芸大学、東京学芸大学、京都学芸大学、広島大学教育学部、熊本大学教育学部)に設置した。この臨時養成課程は、知的障害教育を対象として、各大学とも1年コース(定員20名)と半年コース(各期定員20名)というものであった。研修旅行などでお世話になった京都府立与謝の海養護学校の開校と学校づくりを担ってこられた故青木嗣夫先生も、京都学芸大学臨時養護学校教員養成課程が設置された1960年の後期半年コースで学んでいた。
1960年代、先に見たように養護学校教員の養成課程の本格的な開設となり、それと並行して、教育課程ということでも、1963年4月にはじめての養護学校学習指導要領(小・中学校部精神薄弱教育編、小学部肢体不自由教育編及び小学部病弱教育編)が通達された(中学部肢体不自由教育編及び中学部病弱教育編は、1964年3月に通達)。
養護学校設置への国庫補助、教員養成や学習指導要領の整備の基礎は整えられたが、養護学校の設置はそのままでは進展し得ない。全国の都道府県での養護学校の設置の進展は、養護学校に関する義務制が未施行であったため、進む状況ではなかった。文部省は、中央教育審議会答申に基づいて、肢体不自由養護学校設置と知的障害特殊学級の計画設置を重点的に推進することとし、肢体不自由養護学校については、1960年度を初年度とする5カ年計画で、1964年までに未設置県の解消を図るものとし、知的障害学級については1969年度を初年度とする5カ年計画を作成した。しかし、その計画はそのとおりには進まず、その後修正され、肢体不自由養護学校の未設置研の改称は、1969年度を待たなければならなかった。奈良県では、1966年に、現在の奈良県立明日香養護学校(当時、奈良県立養護学校)が設置された。知的障害の養護学校については、1970年代にはいり、1971年に奈良県立西の京養護学校(現在の奈良県立東養護学校、西養護学校の母体となった学校)の開校を見ることとなった。
ところで、国立大学では、1958年、東京教育大学教育学部附属養護学校(肢体不自由)、1960年、東京学芸大学附属養護学校(精神薄弱)が設置されていくが、多くの大学附属では特殊学級の設置がなされていった。ちなみに、1963年4月、本学附属小学校、1965年4月、附属中学校に、それぞれ「特殊学級」が設置され、すでに50周年を経ている。附属小学校・中学校の学級設置におくれて、1966年度に養護学校教員養成課程が設置されたこととなる。この半世紀の間に、障害のある子どもたちをめぐる状況も大きく変化した。
当時の養護学校教員養成課程の開設当時の「特殊教育」の科目は、「異常児」を冠されて「異常児心理」「異常児教育」などの科目で開講される場合が大方だったが、本学では、「障害児」の名称を掲げて、心理分野を柳川光章先生、教育分野を津曲裕次先生が担当となって、教室・研究室名を「障害児学」を冠するものとされた。田辺正友先生が着任されるとともに、津曲先生の転出で着任した大久保哲夫先生、また学内措置で医学分野に藤井伸先生が着任され、「障害児学研究室」の発展の基礎を培われた。当時としては、「障害」への着眼とその支援を総合的に行おうとする意欲的な用語使用と思われる。
「特殊教育」の用語から、「障害児教育学」「障害児心理学」障害児医学」「障害児福祉学」などの学問分野を総合して「障害児学」とされたものと受けとめられる。「特殊教育」の用語は、いくた議論の末、2007年に「特別支援教育」に移行し、今日にいたる。奈良教育大学養護学校教員養成課程や大学院での養成のシステムも大学改革と障害児教育の発展の中でいくたびか改組されることとなったことは別の論考と年史・年表によって確認してほしい。
学部、臨時養成課程、特別専攻科、大学院教育学研究科など、これまで、本学の障害児教育・特別支援教育の学びと研究の中で、多くの方々が実に真摯にともに学び、ともに成長し合ってきた。障害児学研究室を構成してきたすべての方々とともに、その実りの多い日々の記憶をこれからも糧として、障害のある子どもたちの未来を切りひらく努力とそのために研鑽に励むことを誓い合いたい。
『障害児学研究室50年の歩み』2016年9月












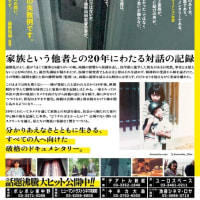




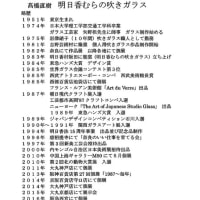

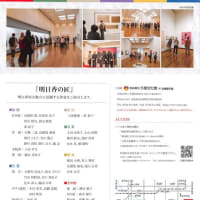
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます