柏てん『京都伏見のあやかし甘味帖 おねだり狐と町家暮らし』(宝島社文庫,2017)
主人公の小薄れんげ(29歳)が、理不尽にも解雇され、その日に家に帰ると同棲相手の彼氏の浮気現場に直面。失業と失恋のダブルパンチに、京都へ逃避行。ラノベだが、まえのあやかしのものと比べると大人っぽいので、読んでいく。しかし、「中書島」のルビが、「なかがきじま」p.22とあって、閉口。京都の和菓子についてかかれたところ、ちょっとうんちく気見たところなど摘記してみた。
「いなり(稲荷)」の由来 今から千三百年以上昔、山城国とよばれていた頃。深草に秦伊呂巨(はたのいろこ)という者があり、彼は稲を積みて豊かに暮らしていた。ある時、弓で餅を射ると、驚いたことに餅は白鳥へと姿を変え、山の峰で稲となった。ゆえに山の名は古くを伊禰奈利(いねなり)、転じて稲生となり、稲荷となった。P.147
・虎太郎が和菓子に魅了されたきっかけ 京菓子司・満月の阿闍梨餅
・虎太郎の甘味日記 宇治編
「椿餅」 源氏物語と言えば、椿餅やんなあ p.74
椿餅というのは一節には和菓子の起源とも言われるお菓子で、なんと千年の歴史がある。当時は砂糖がなかったので甘葛の汁と、道明寺粉を練って椿の葉で挟んでいたらしい。
「茶団子」:「御菓子司能登椽 稲房安兼」(御菓子司は公家の家来として御菓子作りを認められた一部の和菓子屋のこと:創業1717年)
・虎太郎の甘味日記 平安神宮編 p.98
「京菓子司平安殿本店」 京吟味百撰の認定を受ける
「平安殿」「栗田焼」「平安饅頭」
・「おせきもち」
ヨモギのお餅としろいお餅が一つずつ。その上に、粒あんがダイナミックに載せられている p.134
・虎太郎の甘味日記 松風編
「松風」 納豆味の和菓子・石山本願寺で生まれる。カステラに似た形状、カステラより固くせんべいより柔らかい、保存に優れた乾パン。小麦粉、砂糖、麦芽飴、白味噌をませ合わせ、自然発酵させた生地にケシの実を振りかけて巨大な縁万頃に焼き上げる、それを重宝気にに切り分けられたもの。 亀屋陸奥(西本願寺の南東:創業1421年)
亀屋陸奥の「松風」、松屋藤兵衛の「紫野味噌松風」、松屋常磐の「紫野味噌松風」が御三家 p.150-151
・亀屋伊織の「貝づくし」(木型で押した「押物」という種類の菓子)、有平糖「わらび」p.171
・豊栄堂の「酒まんじゅう」、「酒カステラ」
・「虎太郎の甘味日記 出町柳編」
出町ふたば 「名代豆餅」「三宝だんご」「桜だんご」(桜の葉が練り込まれた薄紅のだんご)p.181
・鶴屋吉信 直営店限定「青苔」(寒天を砂糖やなんかで甘くして、外側だけ乾燥させた琥珀糖という御菓子)
・「虎太郎の甘味日記 祇園編」
鍵善良房の「葛切」
柏てん『京都伏見のあやかし甘味帖 花散る、子一縷、鬼探し』(宝島社、2018)
今度は「中書島」は「ちゅうしょじま」となっていた。ますます「あやかし」の世界にはいっていって、和菓子どころではなくなっていく。伏見稲荷の白菊命婦(しらぎくのみょうぶ)からの頼みで「鬼女」を探すというもの。安倍晴明はでてくるは、主人公の「小薄(おすすき)れんげ」の元彼の「理」に乗り移っているし、貴船、蹴上、宇治、一条戻橋、あっちに行ったりこっちに行ったり。
肝心の和菓子は…、
・虎太郎の甘味日記―老松編
老舗「老松」の「夏柑糖」:輝く橙(だいだい)の果実をくりぬき、その果汁と寒天を混ぜて皮の中に戻して冷やし固める。寒天は酸により分解されるので、夏柑糖は難しい柑橘寒天を成功させ京都人に親しまれていた。P.43-44
・現代のどら焼きー朧谷瑞雲同(おぼろやずいうんどう、紫竹地区)の「どら焼き」p.75。種類:小倉、抹茶、黒胡麻、苺、桜など、「吟味謹製生銅鑼焼風味絶佳(ぎんみきんせいなまどらやきふうみぜっか)」。どら焼きとよぶのを躊躇うようなクリームの塊p.77-78
・虎太郎の甘味日記―哲学の道編
叶匠寿庵の京都茶室棟(熊野若王子神社裏手) 「あも」:叶匠寿庵の代表ともいえる菓子。昭和46年生まれ。柔らかく滑らかな餅が、しっとりしたつぶあんに包まれた、一見要官位も見える棹菓子。大福があべこべになったようなお菓子。P.106
・「にっき餅」「名物志んこ」(「まめ餅」「桜餅」に続いて)p.112-113、「祇園饅頭」の工場でかえる。「志んこ」はちいさな巻物のようなもの、お餅というよりは白玉に近い歯触り。味はほんのりと上品な甘さ。米粉で作るので「真の粉」で「志んこ」となった。p.114
・「玖豆善哉(くずぜんざい)」p.121白玉の上に載った透明な餅のような葛(練りたて)。善哉のふんわりした甘さと、なんともいえない葛の柔らかな口当たりが口の中で溶け合う。P.122
・虎太郎の甘味日記―複雑な男心編
「ウチュウワガシ」の「落雁」(落雁の由来は琵琶湖の浮御堂におりてくる雁の情景を描いた打ち物とも、中国の明の時代の菓子『軟落甘』を略したものとも言われている。素材となる穀粉は様々、うるち米、玄米、小麦、大豆、小豆、蕎麦、栗などを製粉して砂糖、水、水飴で練り型に入れて固める。麦を使ったもの麦落雁、豆を使ったもの豆落雁、栗の粉をつかったものは栗落盤。和菓子の落陽とともにその授業は年々減り続け、木型をつれる職人もごくわずか。P.166
・JEREMY&JEMIMAH いろとりどりの一風変わったわたあめを売る店。p.193
・おまけの一口―子狐のひとりごと
「呪い」と「祝い」:名は呪い。そして祝いでもある。名前という言霊によって相手を縛り、名を贈ることで生命の誕生を言祝ぐ(ことほぐ)のである。P.228
「どろぼう」というお菓子:泥棒したいくらい美味しい。小さい麩菓子のようなもの、どちらかというと岩おこしに近い。茶色くて、口に入れるとねっちりしていて、とても甘い。P.248












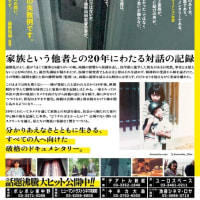




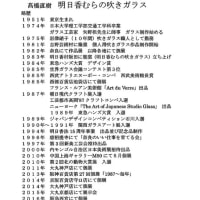

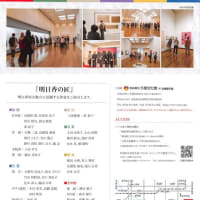
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます