
「しあわせ」と「学校」
本シンポジュームのテーマで想起したのは山田洋次監督の映画『学校』。この『学校』シリーズは、それぞれ、不就学、障害、シングル、そして不登校など、夜間中学校、養護学校(特別支援学校)、専門学校、思春期の旅の場で織りなされる物語。シリーズ最初の夜間中学校をテーマとした『学校』が上映されたのは、1993年、すでに25年余を経ています。「本当の教育とはなにか」を考えさせるこのシリーズを貫くテーマは、1993年に公開された最初の『学校』の中に明確に示されています。夜間中学校が舞台となったこの映画、登場する夜間中学校の生徒達も、不登校、非行、勤労青年、不就学、在日など様々な事情をもった人たち。この学校での学びが描かれつつ、後半に続いていきます。後半には田中邦衛ふんする猪田幸雄(イノさん)さんの生涯をめぐるホームルームとなっていきます。イノさんの思い出を語り合いながら、「イノさんは幸せだったんだろうか?」と、自分のこれまでと重ね合わせた問いがなされ、そして、「幸福」とは何かを問うこととなっていきます。これだけ直裁に「しあわせ」を提起した学校での姿が印象的でした。
「希望」と「教育」
映画「学校」シリーズで学校に集う人たちは、それぞれの背景や思い(「ニーズ」ともいいかえてもいいかもしれない)をもっていました。ある意味、子どもも含めたそれぞれの背景や思いは、「希望」とも言い換えてもいいかもしれません。「希望」は、「希(まれ)」な「望(のぞみ)」でもあります。その望みを受け止める仕組みがないとそれこそ反対のものとなってしまいます。それぞれの人たちの希望やニーズを受けとめる教師や仲間、そして学校の姿が必要です。様々な子どもたちと接してきたという特別支援教育の立場から、困難を背負ってきた子どもたちの教育や学校への希望や願いが、新たな学校や教育への発想を切り拓き、学校教育そのものを変えてきたということを共有したいと思います。
「自由」と「発達」
子どもの権利条約が採択されて30周年、批准されて25周年です。2019年国連子どもの権利委員会最終所見では、少子高齢化社会のなかで、子どもの総合的な施策がないことが指摘されています。また、子どもたちをめぐって、貧困の存在も看過できません。子どもたち、わたしたちも含めたすべての人たちの発達(Development:開発とも訳される)が育まれる社会となっていく必要があります(国連では、Right to Development、そしてEducation for Sustainable Development, 今日ではSDG’Sなどとして課題視されています)。
「発達」の「発」は植物の実がはじける姿からつくられ、「達」は羊が生まれる姿から形象化された文字といわれています。「学校」の主役だったイノさんの名前は「幸雄」。一時期、「発達」の「達」の文字に「幸」という文字をかえて使われた時もあったようです(「幸せになる」という意味)。「幸」の文字は、手を縛られた姿から解放されるという象形文字。
「自由」を獲得し、人間として自由になっていくこと、ともに自由になり、そしてともに社会の形成者として発達していくこと、その姿を学校づくりとして行っていこうということを考えてみたい。学びと教育は、私たち、一人ひとりが、「夢と希望」をもち「幸せ」を追究して、自由になるという発達の権利を実質化するものとしてあります。このような観点から、現在の学校と教育をあらたな仕組みとして再創造することが私たちの課題となると思われます。














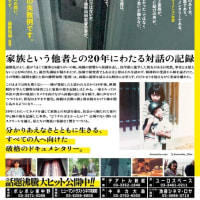




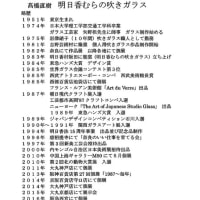

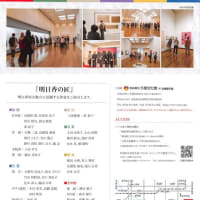
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます