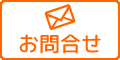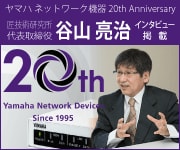MySQLからMariadbが枝分かれ
こんにちは。匠技術研究所の谷山 亮治です。
MySQLはおそらく世界で最も普及しているオープンソースのRDBMSで、インターネットサーバとの組み合わせで広く普及しています。MySQLの開発メンバーが設立した会社はSUNが買収し、MySQLの開発はSUNの一部門として継続しています。
元祖MySQLであるMichael Widenius氏がこのたび、SUNを離れて自分の会社Monty Program Abを作り、MySQLから枝分かれしてMariadbをリリースする旨のブログが公開されました。
ブログには、SUNを離れることの背景と、今後の活動について書かれています。
氏のブログ中のリリースに関する情報を引用し当方の意訳と併せて紹介すると
Maria 1.5 (the crash safe version of MyISAM) is now in beta and we hope to get binaries out soon.
Marina 1.5(なかなかクラッシュしないMyISAM版)がbeta版として開発中で、直ぐにバイナリーのリリースができると期待している。
We have already started working on Maria 2.0 features (full transactional release) and performance issues.
Maria 2.0の機能(フルトランザクション版)と性能について検討を開始した。
ということから、フルトランザクションをサポートする版がMadina 2.0として登場することが判ります。
また、Mariadbの開発者たちはMySQLのMySQL-5.1-Maria版の系統に対して、パッチの提供を行うと書かれています。
整理すると、SUNのMySQL開発チームは引き続き、MySQLのリリースを行います。一方このたび分岐したMariadbはMaria1.5を初期版として、フルトランザクション機能を備えるMaria 2.0の開発を目指しています。
MySQLのバージョン管理ツリーから見れば、Mariadbは枝分かれですが、Mariadbの開発をリードするのがMySQLの生みの親です。今後は、MySQLを使うかMariadbを使うかと選択肢が増えることになります。どちらもオープンソースのデータベースなので、お互いに良いところは取り込み合いながら開発が進むと思います。
MySQLの元祖Michael Widenius氏のブログ(英文)へ
このブログのMySQLの関連記事へ
このブログのMariaDBの関連記事へ
VPNの四方山話/RTXVPN.COMへ
(*)OCN固定IPのお得情報あります。アクセスのほどよろしくお願いします。
(*)この記事の作成・投稿はWindowsXPとFirefox3上で行いました。
☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!