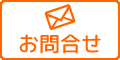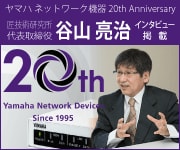こんにちは。匠技術研究所の谷山 亮治です。
事務所で使うWindowsXPパソコンにOpenOffice.orgを入れ、ドキュメントの関連付けもMicrosoft OfficeからOpenOffice.orgに切り替えました。ドキドキしています。
切り替えはもう少し期間を置くかどうか迷ったのですが、Linux上でOpenOffice.orgを使い、ファイルサーバー上のMicrosoft Office(Word,Excel,PowerPoint)で作ったファイルを参照している期間が一月以上有り、特段不便を感じなかったので移行に踏み切りました。
弊社の電子ドキュメントはシンプルなつくりのものがほとんどなので、問題を感じることが少ないようです。
OpenOffice.orgは家庭の事務ソフトとしても十分使えますね。テンプレートがほとんどありませんが、Microsoft Office系のものが流用できるので、作成済みのものを変更していくのであれば、さほど問題は感じないとおもいます。

OpenOffice.orgは統合ソフトですが、ワープロ機能だけとか、プレゼン作成機能だけなど、機能単位でのインストールも可能です。
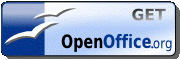
 ☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!
☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!
 Firefox3の現在のダウンロード数はこちら Firefox3の灯火へ
Firefox3の現在のダウンロード数はこちら Firefox3の灯火へ


事務所で使うWindowsXPパソコンにOpenOffice.orgを入れ、ドキュメントの関連付けもMicrosoft OfficeからOpenOffice.orgに切り替えました。ドキドキしています。
切り替えはもう少し期間を置くかどうか迷ったのですが、Linux上でOpenOffice.orgを使い、ファイルサーバー上のMicrosoft Office(Word,Excel,PowerPoint)で作ったファイルを参照している期間が一月以上有り、特段不便を感じなかったので移行に踏み切りました。
弊社の電子ドキュメントはシンプルなつくりのものがほとんどなので、問題を感じることが少ないようです。
OpenOffice.orgは家庭の事務ソフトとしても十分使えますね。テンプレートがほとんどありませんが、Microsoft Office系のものが流用できるので、作成済みのものを変更していくのであれば、さほど問題は感じないとおもいます。

OpenOffice.orgは統合ソフトですが、ワープロ機能だけとか、プレゼン作成機能だけなど、機能単位でのインストールも可能です。
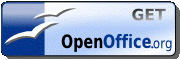
 ☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!
☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ! Firefox3の現在のダウンロード数はこちら Firefox3の灯火へ
Firefox3の現在のダウンロード数はこちら Firefox3の灯火へ