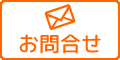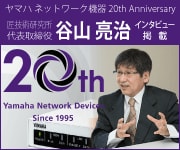こんにちは。匠技術研究所の谷山 亮治です。
帝人が、無線通信シートを開発、発表しました。
日経での報道記事
2008年3月4日付け日経新聞には、図解があります。
机上にデスクマットのように敷いて、その上にパソコンを置きます。パソコンはこれまでの無線LANアダプタを使うようです。パソコンを10センチ程度離すと無線がきれ、通信ができなくなります。
現在普及している無線LANは、通信範囲が広いので、誰がどこで接続しているのか把握が困難です。通信シートは、電波を極めて弱くすることで、通信範囲を限定することになります。これは、丁度駅のアナウンス用スピーカーが、大型のスピーカーを一台置いて、大きな音を出す方法から、小型のスピーカーを沢山配置し、スピーカーの音を限定した範囲に止める方法に変わりつつあることと同じです。
無線シートはおそらくLANケーブルでLANと結ぶ必要があるので、LAN工事は有線と同じように必要だと思われます。事務所内で使うことの利点は、極近距離無線LANにすることで、情報セキュリティを高めることができるとされています。
このような極近距離の無線LAN接続を、広く提供できる仕組みは今までに無かったので、今後製品が登場し、使い勝手がこなれてくると、意外な市場に広がると思います。
帝人が、無線通信シートを開発、発表しました。
日経での報道記事
2008年3月4日付け日経新聞には、図解があります。
机上にデスクマットのように敷いて、その上にパソコンを置きます。パソコンはこれまでの無線LANアダプタを使うようです。パソコンを10センチ程度離すと無線がきれ、通信ができなくなります。
現在普及している無線LANは、通信範囲が広いので、誰がどこで接続しているのか把握が困難です。通信シートは、電波を極めて弱くすることで、通信範囲を限定することになります。これは、丁度駅のアナウンス用スピーカーが、大型のスピーカーを一台置いて、大きな音を出す方法から、小型のスピーカーを沢山配置し、スピーカーの音を限定した範囲に止める方法に変わりつつあることと同じです。
無線シートはおそらくLANケーブルでLANと結ぶ必要があるので、LAN工事は有線と同じように必要だと思われます。事務所内で使うことの利点は、極近距離無線LANにすることで、情報セキュリティを高めることができるとされています。
このような極近距離の無線LAN接続を、広く提供できる仕組みは今までに無かったので、今後製品が登場し、使い勝手がこなれてくると、意外な市場に広がると思います。