今日も凪が続いています。すこし、曇り日和です。
見島の古きを知る「生き字引」となる方も少なくなってきて、誰に「昔の見島」のこと聞いたらいいのかになってきました。
今のうちに、語り継ぐことは残しておかないといけんと思いますが。
小学校3年の頃、理科の授業の一環で「夜光虫」をみなで見るというのがあり、当然夜の砂浜なんですが。
当時、駐在所の前から高見山の裾までずっと、砂浜を含めた磯端で、つまり普通に横浦に続く海岸でした。
特に、駐在所から今の漁協へ行く方は、砂見田の様なきれいな砂浜でした。港も一線しかありませんでした。
昔の人が出て来たら、「こんな所に港が出来チョル」ぐらいに、びっくりすると思いますね。
発電所の下の辺で石を起こすと、「うなぎの子供」10cmくらいのがけっこういました。今なら...ひともうけ...。
墓の下辺りではあさりがいたし、中学校の時は、キス釣りのゴカイやホムシがたくさん掘りました。
見島本村港.....避難港しての長期整備で、よくなりました

発電所前の今日の風景.....砂浜はありません

八町八反は、先に述べたように貝殻がたくさん出て来ます。
埋め立てしなければ今頃は、ハマグリやアサリのほか大きめの貝などを掘る、潮干狩りの憩いの場だったかも!?
「そうだ。八町八反を元の海に戻そう」プロジェクト....萩城再構築より難しいかな!?
じゃなくて、八町八反一帯は、前出の防人が来た7世紀頃から稲作奨励のために干拓が始まったようです。
昭和の時代に、ジーコンボ周辺に潮風よけに松を植えたり、それ以前にジーコンボの墓石で【防潮堤】を構築したようです。
わたしの推測では、ジーコンボが出来る前の横浦海岸と焼却炉がある大久保海岸辺りをせき止めたと思います。
干拓用の土は、磐梯山や中山を削ってどんどん埋めていったと聞き及びます。
いろんな貝が出てくるほかに、竹や木の化石に近いものが耕作作業で出て来たりと散見されてたそうです。
防人さんたちが、守りの任務以外にも【見島の礎】を築いたのは間違いないみたいです。
というか、防人が島を治め.....使用役の見島住人も居たと言うことになると思います。
上空からの八町八反近辺.....ジーコンボ周辺からせき止めた。

見島ダムから見た八町八反の田園......防人の遺産の田んぼ群

さてほかに、現在の小学校と自衛隊官舎の間辺りに、【住吉神社】が存在していたようです。
この神社は漁師の崇める神様ですから、当然そこは海に近かったと言うことです。
かつて海!?今日の見島小学校のグランド...校舎は建て替え中、向こうは官舎

赤崎旅館の下辺りとかまで潮が来ていたらしいので、中学校体育館下から発電所のぐるりも海だったのかも。
更に宇津でも、近年になって弁天荘周辺やおにようずの繋留地も砂浜だったのでかなり埋め立てています。
となると、以前の見島は【見島牛の形】をしていなかった!!......もしかして、意図的に島の形を変えられた!?
上空、牛似の見島 ( 資料映像 )
そんなわけはないか、でもかなりの範囲で見島は大きくなっていったんですよ。
将来、ずっと埋め立てていけば......萩に着く.....とか定期船要らないとか、萩城構築より難しいかな!?
夢の萩城もいいなあ...天守閣からの眺め

( 資料映像 )
◎ 熟熟余談(つらつらよだん- 本日の日めくり 四字熟語 )
「 呑舟之魚 」(どんしゅうのうお) : 常人をはるかに超えた才能をもつ大物。大人物。善人・悪人ともに用いる。
▽「呑舟」は舟を飲み込むこと。舟を飲み込んでしまうほどの大きな魚の意味。



( 資料映像 )
























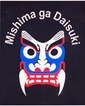

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます