見島には、八十八基のお地蔵様が全島に鎮座まします。
宇津の観音堂には、若き日の空海(弘法大師)が修行中に彫り上げ、漂着した仏像を祀っています。
四国八十八箇所の巡礼も弘法大師が開祖、当然のように見島もご利益にあやかろうと参考にしたのであろう。
そもそもお地蔵様(道祖神)信仰は、災厄を集落に入れないための結界(境界線)の役目を果たしている。
われわれ俗をはずれの郊外で、ずっと文句を言わず見守ってくれるありがたい象徴的存在なのだ。
ここのお地蔵様の場所は、島のご婦人方の多くは、2月11日が宇津地区その次の日曜日に本村地区と分かれて「札打ち」と言って、
寒行も兼ねてかお参りするので在りかは旧知のことだが、どこにどの番号があるかまではなかった。
そこで昭和50年頃に、見島勤務の自衛隊員が地道に調べ上げ地図上に番号を示し、表にして地名までまとめ上げている。
このおかげで、初めての人でもかなりのところまでは、行けるようになった。
私も以前PTA活動で、児童や先生と一緒に回ったが、知らないと疲れるしせいぜい一日で半分程度が関の山だ。
やはりいわくつきの訳あり箇所で守ってくれているだけに、ヤブ在り谷在りの道を開いていく場所も多々ある。
旦那さんが沖に漁に出て、女房は家にいて無事を祈る。さも当然のように普通に家に戻ってくる、
これこそがご加護の現れと素直に感謝する。
ほのぼのとしたしあわせがそこにあり、受け継がれる見島独自の伝統文化の一つも、こうしてかいま見られる。
配置図 観音様階段口
元見島中学校教頭実地撮影記録(抄)
※写真クリック拡大






























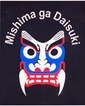

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます