前にも記事にしましたが、最近「MAKING PEACE」という本 を少しずつ読んでいます。
を少しずつ読んでいます。
奉仕や学びの合間に時間を作って、辞書を片手に訳しながら読んでいます
これから随時、要点を分かち合っていければと思っています。
ただし、私なりの理解でありますので・・・
内容をより正確に確認したい方は、ぜひ直接その本をご自分で読んでみることをお勧めします。
著者は、基本的な枠組みとしてこの2つの視点を提示しています。
 教会の対立はいつも神学的なことであって、ただ対人関係にまつわることではない。教会の対立は、文化的、霊的、構造的要因を含む、多くの原因と理由がある。しかし、すべての教会の対立は神学的な根を持っている。
教会の対立はいつも神学的なことであって、ただ対人関係にまつわることではない。教会の対立は、文化的、霊的、構造的要因を含む、多くの原因と理由がある。しかし、すべての教会の対立は神学的な根を持っている。
 すべての教会の対立は、常にリーダーシップと性格と共同体に関するものである。対立は当事者が実際どのような者であるのかを明らかにする。
すべての教会の対立は、常にリーダーシップと性格と共同体に関するものである。対立は当事者が実際どのような者であるのかを明らかにする。
多くの教会の対立の問題に取り組んできた著者は、対立の根を以下の4つの観点から考察しています。
 文化的問題点
文化的問題点
 構造的問題点
構造的問題点
 霊的問題点
霊的問題点
 神学的問題点
神学的問題点
取りあえず、今はここまでです
まだ最初の導入の辺りですが・・・
表面の現象や状況だけでなく、根本をしっかり見据えていくことが大切ですね。
 を少しずつ読んでいます。
を少しずつ読んでいます。奉仕や学びの合間に時間を作って、辞書を片手に訳しながら読んでいます

これから随時、要点を分かち合っていければと思っています。
ただし、私なりの理解でありますので・・・

内容をより正確に確認したい方は、ぜひ直接その本をご自分で読んでみることをお勧めします。
著者は、基本的な枠組みとしてこの2つの視点を提示しています。
 教会の対立はいつも神学的なことであって、ただ対人関係にまつわることではない。教会の対立は、文化的、霊的、構造的要因を含む、多くの原因と理由がある。しかし、すべての教会の対立は神学的な根を持っている。
教会の対立はいつも神学的なことであって、ただ対人関係にまつわることではない。教会の対立は、文化的、霊的、構造的要因を含む、多くの原因と理由がある。しかし、すべての教会の対立は神学的な根を持っている。 すべての教会の対立は、常にリーダーシップと性格と共同体に関するものである。対立は当事者が実際どのような者であるのかを明らかにする。
すべての教会の対立は、常にリーダーシップと性格と共同体に関するものである。対立は当事者が実際どのような者であるのかを明らかにする。多くの教会の対立の問題に取り組んできた著者は、対立の根を以下の4つの観点から考察しています。
 文化的問題点
文化的問題点 構造的問題点
構造的問題点 霊的問題点
霊的問題点 神学的問題点
神学的問題点取りあえず、今はここまでです

まだ最初の導入の辺りですが・・・
表面の現象や状況だけでなく、根本をしっかり見据えていくことが大切ですね。










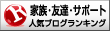

 夕食は手作りピザでした。
夕食は手作りピザでした。







 10人で12枚のピザを完食
10人で12枚のピザを完食
 神学校の
神学校の から教会の行事として始めていることがあります。
から教会の行事として始めていることがあります。
 のんびりお話をする時間です。
のんびりお話をする時間です。
 神様のすばらしさを知って頂くきっかけができればうれしいです。
神様のすばらしさを知って頂くきっかけができればうれしいです。





