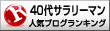日本独特の文化を表す言葉というのは、得てして英語に訳すのが難しいものです。
茶の湯の精神をひとことで表す時、「もてなしの心」とともに最もよく使われる言葉が「わび・さび」でしょう。
飾り気のない、誰も見向きもしない簡素なものに枯れた美を見出す。
そんな美学を全般に指していいます。
茶の湯を大成させたという、戦国時代の茶人・千利休は、二束三文の価値しかなかった薬入れに美を見出し茶入れとして使い始めました。
七つの茶道具を並べ、六人の弟子に一つずつ気に入ったものをとらせ、最後に残った茶碗を「これこそ極上の茶器」と生涯愛用し続けました。
人が見過ごしそうなものに価値を見出す。
もともとの利休の考えはそのようなところにありそうです。
時代とともに、茶の湯の文化が栄え、名人たちはそうした「わび・さび」を人の技を使って生み出していくことに取り組みました。
茶碗にひねりを加え、少し黒ずんだ竹で茶杓を作り、茶庭に不規則に石を並べました。
自然な美しさを、人の手で作り出していったのです。
数百年の時をかけて「わび・さび」の文化は、茶の湯の、そして日本の文化の極みにまで高められてきました。
さて、それを英語で何と訳し、外国の人にどのように紹介するか。
難問です。
西洋にはそのような文化や価値観がないので、ひとことで言い表す英語は存在しません。
beauty in imperfection
不完全の美
aesthetics of simplicity
簡素さの美学
このように説明する人もいます。
本来はこのような美学や価値観は、言葉だけでは決してその本質は伝わらないものなのでしょう。
利休の逸話を聞いたり、日本の歴史を学んだり、実際に茶室や茶道具などを見たり、そういう中から「感じとる」ことで初めて理解できるものです。
しかし、実際にそこまでの体験をできる外国人はごく少数です。
日本のことに興味関心はあるが日本に来る機会の少ない人たちに、「わび・さび」を説明しようと思うと、言葉に頼らざるを得ません。
自国の文化を外国の人に伝え理解してもらう。
他国の言語を学ぶ大きな目的の一つでもあります。
そしてそのためには、自国の文化を十二分に自分が理解していなくてはなりません。
「わび・さび」をどのように英語で表現するか。
よいトレーニングになる題材です。
茶の湯の精神をひとことで表す時、「もてなしの心」とともに最もよく使われる言葉が「わび・さび」でしょう。
飾り気のない、誰も見向きもしない簡素なものに枯れた美を見出す。
そんな美学を全般に指していいます。
茶の湯を大成させたという、戦国時代の茶人・千利休は、二束三文の価値しかなかった薬入れに美を見出し茶入れとして使い始めました。
七つの茶道具を並べ、六人の弟子に一つずつ気に入ったものをとらせ、最後に残った茶碗を「これこそ極上の茶器」と生涯愛用し続けました。
人が見過ごしそうなものに価値を見出す。
もともとの利休の考えはそのようなところにありそうです。
時代とともに、茶の湯の文化が栄え、名人たちはそうした「わび・さび」を人の技を使って生み出していくことに取り組みました。
茶碗にひねりを加え、少し黒ずんだ竹で茶杓を作り、茶庭に不規則に石を並べました。
自然な美しさを、人の手で作り出していったのです。
数百年の時をかけて「わび・さび」の文化は、茶の湯の、そして日本の文化の極みにまで高められてきました。
さて、それを英語で何と訳し、外国の人にどのように紹介するか。
難問です。
西洋にはそのような文化や価値観がないので、ひとことで言い表す英語は存在しません。
beauty in imperfection
不完全の美
aesthetics of simplicity
簡素さの美学
このように説明する人もいます。
本来はこのような美学や価値観は、言葉だけでは決してその本質は伝わらないものなのでしょう。
利休の逸話を聞いたり、日本の歴史を学んだり、実際に茶室や茶道具などを見たり、そういう中から「感じとる」ことで初めて理解できるものです。
しかし、実際にそこまでの体験をできる外国人はごく少数です。
日本のことに興味関心はあるが日本に来る機会の少ない人たちに、「わび・さび」を説明しようと思うと、言葉に頼らざるを得ません。
自国の文化を外国の人に伝え理解してもらう。
他国の言語を学ぶ大きな目的の一つでもあります。
そしてそのためには、自国の文化を十二分に自分が理解していなくてはなりません。
「わび・さび」をどのように英語で表現するか。
よいトレーニングになる題材です。