Ⅲ 歌窯
雲梯
「オキナは後鳥羽院の御代、院が隠岐に流罪となって当地に向かう途次、院の御製を密かに口頭で託され、それを都の参議某に伝えるべく命じられた随身だが、それを中国地方の脊梁山脈の奥深いこのミズナラの森のなかに「落としてしまった」。オキナは、「忘れてしまった」とは言わなかった。」。
このあたりはとても内容が深くなっている。まず「後鳥羽院」の出現にかんして見ていこう。たとえば後鳥羽院の、
人もをし人もうらめしあちきなく世をおもふ故に物おもふ身は
について『百首要解』(岡本保孝 『百首異見・百首要解』大坪利絹編 和泉書院)には以下のように書かれている。
源氏須磨、かかるをりは、人わろくうらめしき人おほく、世間はあちきなきも
の哉とのみ、万につけておほすとあるを、用ひさせ給ひて、一首となさせ給ひしなるへし、」あちきなく、心にかなはでせんすべなきを、あちきなしといへり、俗ににかにかしといふに似たり、と縣居翁(賀茂真淵)いはれき、」をしは愛の字をよめり、」一首の意、せんすへなき世をおほしつつけ給ふにつきては、御身の行末いかかあらん、とよろつ御こころにまかせ給はぬままに、なつかしくおほす人もあり、又うらめしくおほす人もありと也、」此とき大御稜威おとろへ給ひて、よろつ御心にまかせぬをりの御歌也、(適宜改稿、丸括弧注=筆者)
このように『源氏物語』をベースにされている。『源氏物語』については大野晋が以下のように記している。
宣長に至るまでの『源氏物語』の享受と研究とは、およそ三期に分けられる。はじめは自由にこれが讀めた時代。次は多少の注がつけられはじめ、次第にその注釋が多くなる時代、つまり院政時代末期から室町時代末期まで。その次が『源氏物語』を嚴密な學問研究の對象として客観的に取扱い、論じる時代、江戸時代の初めから中頃までである。
第一の時代について、最初に言えることは、『源氏物語』が成立當初から人々に愛讀されていたらしいことである。東國の果てにいて、早く上京して『源氏物語』全帖を讀みたいと熱望した少女もいたし、みずから書く物語の巻の名を『源氏物語』に模してつける女もあった。『源氏物語』は一帖一帖が纏まっているから、人々は手にするままにこれを讀むことが可能であった。しかし、やがて平安時代も末になり、藤原貴族の政治上の實權が弱まるころ頃には、『源氏物語』を讀まない歌よみもあったらしい。藤原俊成が「源氏見ざる歌よみは遺恨事也」と『六百番歌合』の判詞で述べたのは有名である。あるいは、その頃すでに『源氏物語』の文章が、當時の口語と距離を大きくしつつあったのかもしれぬ。(本居宣長全集 第四巻 解題一より 適宜改稿)。
一応以上のことを確認した上で本文に戻る。
「オキナは」「落としてしまった」「忘れてしまった」とは言わなかった」。この「落としてしまった」は文脈上、物・人をある所から離れさせる。(ついていたものを)なくす、が適していると思われる。「忘れ」の、自然に記憶や印象が消える。記憶が失せる、ではない。
まだ解いておかねばならぬことがある。
この詩の題になる『雲梯』とは和語に直せば「雲のかけはし」のことである。後鳥羽院の御製歌、
かささぎの雲のかけ橋さえわたり霜置きまどふ有明の月
の本歌は寂蓮の、
鵲の雲のかけ橋秋暮れて夜半には霜や冴え渡るらん
という歌である。
寂蓮は俊成の猶子であり定家の甥にあたる。寂蓮について歌は多く残っているが彼の生涯については詳しいことが分からない。『後鳥羽院御口伝』に、
寂蓮は、なおざりならず哥詠みし者なり。あまり案じくだしき程に、たけなどぞいたくはかたくはなかりしけれども、いざたけある哥詠まむとて「龍田の奥にかかる白雲」と三躰の哥に詠みたりし、恐ろしかりき。折につけて、きと哥詠み、連哥し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、眞実の堪能と見えき。
とその評価はすこぶる高い。
ところで、この『雲梯』の詩の最終行に時里は参考とでも言うべくして小文字で、
「猿ほどの小さな体躯のこの初期型アンドロイドの名は名井島の資料によれば「雲梯」とある。」と結んでいる。
「猿ほどの小さな体躯」とは「オキナのはだかの心を容れる新しい身体」=「飴色につやつやと磨かれたミズナラの硬い傀儡の身体」、これはとりもなおさず後鳥羽院がその本歌として用いられた「寂蓮」「の心を容れる新しい身体」ではないだろうかと推察する。
時里の和語の美しさが目を惹く一篇である。
歌窯
『雲梯』にひきつづいて『歌窯』においても詩歌史を経に動物変身譚を緯に編んでいる。詩歌史の方は『源氏物語』より『新古今集』、足利の宗祇を経て明治・大正の「ポエジー」に至る。一方アンドロイドを含め動物変身譚は「動物比喩譚」として折口信夫は以下のように記す。
何処の国々にも、かう言ふ説話があり、とりわけ感情から判断まで、人間的なものばかりの世界を伝へるものを、動物比喩譚などと称して、人間の上にあることを仔細あつて、動物に準へて語るとしてゐる。(中略)神話・伝説の類の上に見る人間と似ない神・霊物は、結局其が他界の生類であることを示す手段として、違った姿形(ナリ)が考へつかれたのである。(『折口信夫全集20』「民族史観における他界観念」適宜改稿=筆者)。
この詩においては読者の煩をさけるための参考のみを記すことにとどめよう。
「定家卿」の歌論書のうちわたしの手元にあるのは『近代秀歌』『詠歌大概』『毎月抄』(ともに『日本古典文学体系 歌論集 能楽論集』所収)である。とくに「定家卿」がかさねて記していることを大事として『近代秀歌』から写しておく。
いまは、そのかみのことに侍るべし。ある人の、歌はいかやうによむべきものぞととはれて侍りしかば、愚かなる心にまかせて、わづかにおもひえたることを書きつけ侍りし。いささかのよしもなくただことばにかきつづけておくり侍りし。見ぐるしけれど、ただおもふままのひがごとに侍るべし。
やまとうたのみち、あさきに似てふかく、やすきに似てかたし。わきまへる人、又いくばくならず。(中略)おもひいれてすぐれたるうたは、たかき世にもおよびてや侍らむ。いまの世となりて、このいやしきすがたをいささかかへて、ふるきことばをしたへるうた、あまたいできたりて(中略)たえたるうたのさま、わづかに見えきこゆる時侍るを、物の心さとりしらぬ人は、あたらしきこといできて、うたの道かはりにたりと、申すも侍りるべし。(中略)ただききにくきこととして、やすかるべきことをちがへ、はなれたることをつづけて、にぬうたをまねぶとおもへるともがら、あまねくなりにて侍るにや。(中略)ことばはふるきをしたひ、心はあたらしきを求め、およばぬたかきすがたをねがひて、寛平以往(六歌仙以前)にならはば、おのずからよろしきこともなどか侍らざらん(適宜改稿、括弧注=筆者)。
このことは昨今の現代詩にも言えることなので詩人も肝に銘じておくべきだと思う。
なお、「歌窯」「歌床」「歌種」は「麵麭」の縁語にしてよく出来た造語であると思われる。
雲梯
「オキナは後鳥羽院の御代、院が隠岐に流罪となって当地に向かう途次、院の御製を密かに口頭で託され、それを都の参議某に伝えるべく命じられた随身だが、それを中国地方の脊梁山脈の奥深いこのミズナラの森のなかに「落としてしまった」。オキナは、「忘れてしまった」とは言わなかった。」。
このあたりはとても内容が深くなっている。まず「後鳥羽院」の出現にかんして見ていこう。たとえば後鳥羽院の、
人もをし人もうらめしあちきなく世をおもふ故に物おもふ身は
について『百首要解』(岡本保孝 『百首異見・百首要解』大坪利絹編 和泉書院)には以下のように書かれている。
源氏須磨、かかるをりは、人わろくうらめしき人おほく、世間はあちきなきも
の哉とのみ、万につけておほすとあるを、用ひさせ給ひて、一首となさせ給ひしなるへし、」あちきなく、心にかなはでせんすべなきを、あちきなしといへり、俗ににかにかしといふに似たり、と縣居翁(賀茂真淵)いはれき、」をしは愛の字をよめり、」一首の意、せんすへなき世をおほしつつけ給ふにつきては、御身の行末いかかあらん、とよろつ御こころにまかせ給はぬままに、なつかしくおほす人もあり、又うらめしくおほす人もありと也、」此とき大御稜威おとろへ給ひて、よろつ御心にまかせぬをりの御歌也、(適宜改稿、丸括弧注=筆者)
このように『源氏物語』をベースにされている。『源氏物語』については大野晋が以下のように記している。
宣長に至るまでの『源氏物語』の享受と研究とは、およそ三期に分けられる。はじめは自由にこれが讀めた時代。次は多少の注がつけられはじめ、次第にその注釋が多くなる時代、つまり院政時代末期から室町時代末期まで。その次が『源氏物語』を嚴密な學問研究の對象として客観的に取扱い、論じる時代、江戸時代の初めから中頃までである。
第一の時代について、最初に言えることは、『源氏物語』が成立當初から人々に愛讀されていたらしいことである。東國の果てにいて、早く上京して『源氏物語』全帖を讀みたいと熱望した少女もいたし、みずから書く物語の巻の名を『源氏物語』に模してつける女もあった。『源氏物語』は一帖一帖が纏まっているから、人々は手にするままにこれを讀むことが可能であった。しかし、やがて平安時代も末になり、藤原貴族の政治上の實權が弱まるころ頃には、『源氏物語』を讀まない歌よみもあったらしい。藤原俊成が「源氏見ざる歌よみは遺恨事也」と『六百番歌合』の判詞で述べたのは有名である。あるいは、その頃すでに『源氏物語』の文章が、當時の口語と距離を大きくしつつあったのかもしれぬ。(本居宣長全集 第四巻 解題一より 適宜改稿)。
一応以上のことを確認した上で本文に戻る。
「オキナは」「落としてしまった」「忘れてしまった」とは言わなかった」。この「落としてしまった」は文脈上、物・人をある所から離れさせる。(ついていたものを)なくす、が適していると思われる。「忘れ」の、自然に記憶や印象が消える。記憶が失せる、ではない。
まだ解いておかねばならぬことがある。
この詩の題になる『雲梯』とは和語に直せば「雲のかけはし」のことである。後鳥羽院の御製歌、
かささぎの雲のかけ橋さえわたり霜置きまどふ有明の月
の本歌は寂蓮の、
鵲の雲のかけ橋秋暮れて夜半には霜や冴え渡るらん
という歌である。
寂蓮は俊成の猶子であり定家の甥にあたる。寂蓮について歌は多く残っているが彼の生涯については詳しいことが分からない。『後鳥羽院御口伝』に、
寂蓮は、なおざりならず哥詠みし者なり。あまり案じくだしき程に、たけなどぞいたくはかたくはなかりしけれども、いざたけある哥詠まむとて「龍田の奥にかかる白雲」と三躰の哥に詠みたりし、恐ろしかりき。折につけて、きと哥詠み、連哥し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、眞実の堪能と見えき。
とその評価はすこぶる高い。
ところで、この『雲梯』の詩の最終行に時里は参考とでも言うべくして小文字で、
「猿ほどの小さな体躯のこの初期型アンドロイドの名は名井島の資料によれば「雲梯」とある。」と結んでいる。
「猿ほどの小さな体躯」とは「オキナのはだかの心を容れる新しい身体」=「飴色につやつやと磨かれたミズナラの硬い傀儡の身体」、これはとりもなおさず後鳥羽院がその本歌として用いられた「寂蓮」「の心を容れる新しい身体」ではないだろうかと推察する。
時里の和語の美しさが目を惹く一篇である。
歌窯
『雲梯』にひきつづいて『歌窯』においても詩歌史を経に動物変身譚を緯に編んでいる。詩歌史の方は『源氏物語』より『新古今集』、足利の宗祇を経て明治・大正の「ポエジー」に至る。一方アンドロイドを含め動物変身譚は「動物比喩譚」として折口信夫は以下のように記す。
何処の国々にも、かう言ふ説話があり、とりわけ感情から判断まで、人間的なものばかりの世界を伝へるものを、動物比喩譚などと称して、人間の上にあることを仔細あつて、動物に準へて語るとしてゐる。(中略)神話・伝説の類の上に見る人間と似ない神・霊物は、結局其が他界の生類であることを示す手段として、違った姿形(ナリ)が考へつかれたのである。(『折口信夫全集20』「民族史観における他界観念」適宜改稿=筆者)。
この詩においては読者の煩をさけるための参考のみを記すことにとどめよう。
「定家卿」の歌論書のうちわたしの手元にあるのは『近代秀歌』『詠歌大概』『毎月抄』(ともに『日本古典文学体系 歌論集 能楽論集』所収)である。とくに「定家卿」がかさねて記していることを大事として『近代秀歌』から写しておく。
いまは、そのかみのことに侍るべし。ある人の、歌はいかやうによむべきものぞととはれて侍りしかば、愚かなる心にまかせて、わづかにおもひえたることを書きつけ侍りし。いささかのよしもなくただことばにかきつづけておくり侍りし。見ぐるしけれど、ただおもふままのひがごとに侍るべし。
やまとうたのみち、あさきに似てふかく、やすきに似てかたし。わきまへる人、又いくばくならず。(中略)おもひいれてすぐれたるうたは、たかき世にもおよびてや侍らむ。いまの世となりて、このいやしきすがたをいささかかへて、ふるきことばをしたへるうた、あまたいできたりて(中略)たえたるうたのさま、わづかに見えきこゆる時侍るを、物の心さとりしらぬ人は、あたらしきこといできて、うたの道かはりにたりと、申すも侍りるべし。(中略)ただききにくきこととして、やすかるべきことをちがへ、はなれたることをつづけて、にぬうたをまねぶとおもへるともがら、あまねくなりにて侍るにや。(中略)ことばはふるきをしたひ、心はあたらしきを求め、およばぬたかきすがたをねがひて、寛平以往(六歌仙以前)にならはば、おのずからよろしきこともなどか侍らざらん(適宜改稿、括弧注=筆者)。
このことは昨今の現代詩にも言えることなので詩人も肝に銘じておくべきだと思う。
なお、「歌窯」「歌床」「歌種」は「麵麭」の縁語にしてよく出来た造語であると思われる。











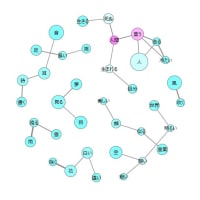


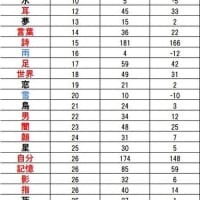
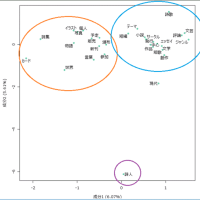
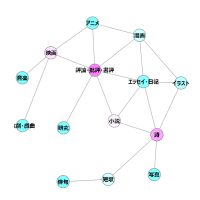
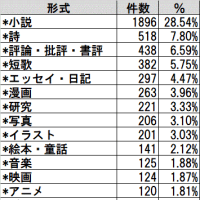
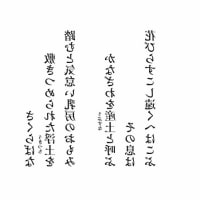
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます