さて、これまで何度か、討ち入りの際には、左兵衛は薙刀をふるい応戦したも、負傷のために戦線離脱。その最中に義父・上野介が討たれた事は書いてきたが、当日の討ち入りから後までの左兵衛を、詳しく追っていこう。
元禄15年12月14日は、義父・上野介のたっての所望で開かれた茶会であった。前日には江戸一帯を覆い雪を降らせていた雲も晴れ、真冬の眩い光に照らされる庭先の雪化粧が、風情を写し出していた。
京風をこよなく好む上野介は、京にて宗偏流を起こした茶人・山田宗偏を茶道の師に仰ぎ、この日も茶会に招いていた。
だが、上野介はむろん、左兵衛も知らなかったのである。山田宗偏が、脇屋新兵衛と変名した赤穂浪士の大高忠雄がを弟子に持ち、本日の茶会を知らせていた事を…。
柔和な顔の山田宗偏のどこに、そのような裏切りの思惑があったのか。
そして何事もなく、元禄15年12月15日の朝を迎える筈であった。
一帯が静まりかえった夜八半(午前3時)。積もった雪は大勢の足音を消し、息を潜める者たちに味方していた。
どんといった大きな音が屋敷に響く。東側の表門は、旗本・牧野一学の屋敷に面し、西側の裏門の先は旗本の小屋敷と回向院。北側の越前福井藩松平家江戸屋敷(家老・本多孫太郎長員)と旗本・土屋主税の屋敷と地続の塀には潜り戸が2カ所設けられている。
381坪に及ぶ屋敷の周囲は、426坪の郎党たちの長屋が取り囲み、主の居室への進路は困難な筈であった。
当時の吉良家家臣の数は諸説あるが、討ち入り後の幕府の検死役の書には、「中間小物共89人」。桑名藩所伝覚書では「上杉弾正(上杉綱憲)から吉良佐平(吉良義周)様へ御付人の儀侍分の者40人程。雑兵180人程参り居り申し候よし」と記しており、これは、義周が上杉家から吉良家へ養子に入った際に従った者である。
また、赤穂市発行の「忠臣蔵」によれば、「屋敷の内にいた者は150人、死者17人、負傷者は28人、長屋に閉じ込められた者101人(用人1人、中間頭1人、徒士5人、足軽7人、中間86人であり、抵抗しなかった裏門番1人)とされる。
同じく赤穂市発行の「忠臣蔵第一巻(概説編)」によると、「本屋内での死者2人、負傷者2人、本屋外での死者6人、負傷者は17人、合わせて死者は17人、負傷者は28人、合計45人であった」と記されているも、数が合わないのは、負傷者の過半数は瀕死の重傷のため、一両日中に死亡した者も含めた人数になる。
逃亡者とみなされるのは、事件後行方不明となった当夜、左兵衛の側に寝ていた中小姓1人、徒士3人である。夜襲をかける浅野側も浅野側なら、主君を置いて逃げた吉良側も吉良側。また、閂をかけられ閉じ込められたとしても、大昔の木と紙の長屋ではないか。大の男の腕力を持ってすれば、その気さえあれば引き戸など、蹴破られそうなものだと思うのは早計だろうか。
石高からみても90から100名程は詰めていたと思われる。
だが、屋敷を取り巻く長屋門の臣下たちは、直ちに飛び起きるも、差料を手に飛び出す間もなく、閂(かんぬき)にて出入り口を打ち付けられと閉じ込められたため、実際の戦闘に参加したのは、当夜の宿直の者が主と考えて良いだろう。
いずれにしても、完全武装の浪士側に対し、吉良家の者たちは、寝起きざまに斬り付けられたのだ。恐らく、騒ぎに飛び起きた者たちは、火事騒ぎかと思って飛び出した事だろう。大勢が徒党を組んで夜襲をかける。こんな不意打ちを、義士などと奉る事が武士道なのであろう筈もない。
しかも、前の項でも書いたが、大石内蔵助は、「上野介が見付からなければ、義周の首を取れ」と言っているのだ。義周を討つ事が主君への忠義など片腹痛い。義周こそ良い迷惑である。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
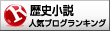
 にほんブログ村
にほんブログ村

元禄15年12月14日は、義父・上野介のたっての所望で開かれた茶会であった。前日には江戸一帯を覆い雪を降らせていた雲も晴れ、真冬の眩い光に照らされる庭先の雪化粧が、風情を写し出していた。
京風をこよなく好む上野介は、京にて宗偏流を起こした茶人・山田宗偏を茶道の師に仰ぎ、この日も茶会に招いていた。
だが、上野介はむろん、左兵衛も知らなかったのである。山田宗偏が、脇屋新兵衛と変名した赤穂浪士の大高忠雄がを弟子に持ち、本日の茶会を知らせていた事を…。
柔和な顔の山田宗偏のどこに、そのような裏切りの思惑があったのか。
そして何事もなく、元禄15年12月15日の朝を迎える筈であった。
一帯が静まりかえった夜八半(午前3時)。積もった雪は大勢の足音を消し、息を潜める者たちに味方していた。
どんといった大きな音が屋敷に響く。東側の表門は、旗本・牧野一学の屋敷に面し、西側の裏門の先は旗本の小屋敷と回向院。北側の越前福井藩松平家江戸屋敷(家老・本多孫太郎長員)と旗本・土屋主税の屋敷と地続の塀には潜り戸が2カ所設けられている。
381坪に及ぶ屋敷の周囲は、426坪の郎党たちの長屋が取り囲み、主の居室への進路は困難な筈であった。
当時の吉良家家臣の数は諸説あるが、討ち入り後の幕府の検死役の書には、「中間小物共89人」。桑名藩所伝覚書では「上杉弾正(上杉綱憲)から吉良佐平(吉良義周)様へ御付人の儀侍分の者40人程。雑兵180人程参り居り申し候よし」と記しており、これは、義周が上杉家から吉良家へ養子に入った際に従った者である。
また、赤穂市発行の「忠臣蔵」によれば、「屋敷の内にいた者は150人、死者17人、負傷者は28人、長屋に閉じ込められた者101人(用人1人、中間頭1人、徒士5人、足軽7人、中間86人であり、抵抗しなかった裏門番1人)とされる。
同じく赤穂市発行の「忠臣蔵第一巻(概説編)」によると、「本屋内での死者2人、負傷者2人、本屋外での死者6人、負傷者は17人、合わせて死者は17人、負傷者は28人、合計45人であった」と記されているも、数が合わないのは、負傷者の過半数は瀕死の重傷のため、一両日中に死亡した者も含めた人数になる。
逃亡者とみなされるのは、事件後行方不明となった当夜、左兵衛の側に寝ていた中小姓1人、徒士3人である。夜襲をかける浅野側も浅野側なら、主君を置いて逃げた吉良側も吉良側。また、閂をかけられ閉じ込められたとしても、大昔の木と紙の長屋ではないか。大の男の腕力を持ってすれば、その気さえあれば引き戸など、蹴破られそうなものだと思うのは早計だろうか。
石高からみても90から100名程は詰めていたと思われる。
だが、屋敷を取り巻く長屋門の臣下たちは、直ちに飛び起きるも、差料を手に飛び出す間もなく、閂(かんぬき)にて出入り口を打ち付けられと閉じ込められたため、実際の戦闘に参加したのは、当夜の宿直の者が主と考えて良いだろう。
いずれにしても、完全武装の浪士側に対し、吉良家の者たちは、寝起きざまに斬り付けられたのだ。恐らく、騒ぎに飛び起きた者たちは、火事騒ぎかと思って飛び出した事だろう。大勢が徒党を組んで夜襲をかける。こんな不意打ちを、義士などと奉る事が武士道なのであろう筈もない。
しかも、前の項でも書いたが、大石内蔵助は、「上野介が見付からなければ、義周の首を取れ」と言っているのだ。義周を討つ事が主君への忠義など片腹痛い。義周こそ良い迷惑である。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます