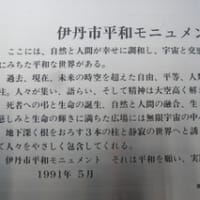高瀬舟
2010-04-30 | パパ
森鴎外の小説に「高瀬舟」という小作品がある。
高瀬舟とは京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が島流しの際に乗せられるものであった。高瀬舟に乗る罪人の多くは、思わぬことで罪を犯してしまった者であり、温情として親類一人を同船させることを暗黙で容認されていた。護送の役をする同心は、罪人と親類の夜どおしの語らいをそばで聞き、二人の悲しい身の上を細かく知ることになる。
「同心を勤める人にも、色々の性質があるから、この時只うるさいと思って、耳をおおいたく思う同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ気色には見せぬながら、無言のうちにひそかに胸を痛める同心もあった。」
小説はこの後者の存在、すなわち役柄を超えた一人の同心の人間性の発露によって展開していく。
ある時、珍しい罪人が高瀬舟に載せられた。名は喜助といい30歳ばかりになる住所不定の男で、舟には親類もなく只一人であった。護送を命ぜられた羽田庄兵衛は、彼が弟殺しの罪人だということだけを知らされていた。
何が珍しかったというと彼が只一人だったという状況においてではなく、一般に罪人が見せる悲哀を顔に浮かべるでもなくただただ晴れやか面持ちで黙って座っていたからである。庄兵衛は、喜助の態度が腑に落ちない。それどころか、ますますこの男の姿に輝きが増していくように感じられる。
しばらくして、こらえ切れなくなった庄兵衛は喜助に声をかける。
「いや、別にわけがあって聞いたのではない。実はな、おれはさっきからお前の島へ往く心持が聞いてみたかったのだ。おれはこれまでこの舟で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ往くのを悲しがって、見送りに来て、いっしょに舟に乗る親類のものと、夜どおし泣くにきまっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ往くのを苦にはしていないようだ。一体お前はどう思っているのだい」
喜助はにっこり笑ってこたえる。
「なるほど島へ往くということは、外の人には悲しい事でございましょう。その心持はわたくしにも思い遣って見ることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまでわたくしのいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で、命を助けて島へ遣ってくださいます。島はよしやつらい所でも、鬼のすむところではございますまい。・・・・」
積み重なる労苦は、喜助に諦めを教え、諦めによって彼は救われたのかもしれない。晩年の鴎外は、自己の運命をすなおに受け止めて達観すること、高い精神をもつ者の諦めの境地をドイツ語でレジニアション(諦念)と語っている。
話を最後まで聞き終えた庄兵衛は、今度は喜助の身の上を自身に置き換えてみる。そして漠然と人の一生ということを考えることになる。
「人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備えるたくわえがないと、少しでもたくわえがあったらと思う。たくわえがあっても、又そのたくわえがもっと多かったらと思う。かくの如きに先から先へと考えてみれば、人はどこまでいって踏み止まることができるものやら分からない。それを今目の前で踏み止って見せてくれるのがこの喜助だと、庄兵衛は気がついた。」
鴎外は漱石と並ぶ明治時代の文豪であり、日本が急速に西洋化していく中で、人間が欲望に突き動かされてやまない生き物であることを案じていたのかもしれない。
ここで、最後の疑問が残る。何故このような人間が弟を殺してしまったのかと。
高瀬舟が扱うテーマとは、実はこの弟殺しの理由なのである。そして、それは古くて新しい「ユウタナジイ(安楽死)」という問題につながっていく。
喜助は病に倒れて苦しむ弟を、ためらいながらも、弟の思いを受け止めて殺してしまうのである。
鴎外は小説の中でこの問題に解を見出しきれていない。解が存在しないからこそ小説を書き、「安楽死」という問いを謎のまま読者に投げ出したかったのかもしれない。
高瀬舟とは京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が島流しの際に乗せられるものであった。高瀬舟に乗る罪人の多くは、思わぬことで罪を犯してしまった者であり、温情として親類一人を同船させることを暗黙で容認されていた。護送の役をする同心は、罪人と親類の夜どおしの語らいをそばで聞き、二人の悲しい身の上を細かく知ることになる。
「同心を勤める人にも、色々の性質があるから、この時只うるさいと思って、耳をおおいたく思う同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ気色には見せぬながら、無言のうちにひそかに胸を痛める同心もあった。」
小説はこの後者の存在、すなわち役柄を超えた一人の同心の人間性の発露によって展開していく。
ある時、珍しい罪人が高瀬舟に載せられた。名は喜助といい30歳ばかりになる住所不定の男で、舟には親類もなく只一人であった。護送を命ぜられた羽田庄兵衛は、彼が弟殺しの罪人だということだけを知らされていた。
何が珍しかったというと彼が只一人だったという状況においてではなく、一般に罪人が見せる悲哀を顔に浮かべるでもなくただただ晴れやか面持ちで黙って座っていたからである。庄兵衛は、喜助の態度が腑に落ちない。それどころか、ますますこの男の姿に輝きが増していくように感じられる。
しばらくして、こらえ切れなくなった庄兵衛は喜助に声をかける。
「いや、別にわけがあって聞いたのではない。実はな、おれはさっきからお前の島へ往く心持が聞いてみたかったのだ。おれはこれまでこの舟で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ往くのを悲しがって、見送りに来て、いっしょに舟に乗る親類のものと、夜どおし泣くにきまっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ往くのを苦にはしていないようだ。一体お前はどう思っているのだい」
喜助はにっこり笑ってこたえる。
「なるほど島へ往くということは、外の人には悲しい事でございましょう。その心持はわたくしにも思い遣って見ることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまでわたくしのいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で、命を助けて島へ遣ってくださいます。島はよしやつらい所でも、鬼のすむところではございますまい。・・・・」
積み重なる労苦は、喜助に諦めを教え、諦めによって彼は救われたのかもしれない。晩年の鴎外は、自己の運命をすなおに受け止めて達観すること、高い精神をもつ者の諦めの境地をドイツ語でレジニアション(諦念)と語っている。
話を最後まで聞き終えた庄兵衛は、今度は喜助の身の上を自身に置き換えてみる。そして漠然と人の一生ということを考えることになる。
「人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備えるたくわえがないと、少しでもたくわえがあったらと思う。たくわえがあっても、又そのたくわえがもっと多かったらと思う。かくの如きに先から先へと考えてみれば、人はどこまでいって踏み止まることができるものやら分からない。それを今目の前で踏み止って見せてくれるのがこの喜助だと、庄兵衛は気がついた。」
鴎外は漱石と並ぶ明治時代の文豪であり、日本が急速に西洋化していく中で、人間が欲望に突き動かされてやまない生き物であることを案じていたのかもしれない。
ここで、最後の疑問が残る。何故このような人間が弟を殺してしまったのかと。
高瀬舟が扱うテーマとは、実はこの弟殺しの理由なのである。そして、それは古くて新しい「ユウタナジイ(安楽死)」という問題につながっていく。
喜助は病に倒れて苦しむ弟を、ためらいながらも、弟の思いを受け止めて殺してしまうのである。
鴎外は小説の中でこの問題に解を見出しきれていない。解が存在しないからこそ小説を書き、「安楽死」という問いを謎のまま読者に投げ出したかったのかもしれない。