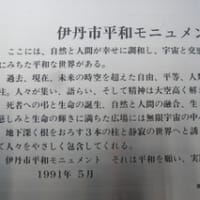オーストリアの詩人リルケは「マルテの手記」の冒頭で次のように書いている。
「人々は生きるためにこの都会へ集まって来るらしい。しかし、僕はむしろ、ここではみんなが死んでゆくとしか思えないのだ。」

詩人の鋭い感性がとらえた都市の印象だ。それは孤独だったのではないか?
人は人を求めて都市に集う。そこに都市の魅力がある。しかし、一方で人は集団となることで匿名となり孤立化していくのも事実だ。
今、日本では都市の砂漠化が進んでいる。毎年増え続ける自殺者の数、幼児虐待や行方不明老人の問題など弱者が孤独の中で、都市に消えていく。
本当の砂漠が食料の欠乏という状態で目に見えるのに対して、都市の砂漠化は人々の無意識の生活の中に水面下で広がっていく。砂漠が限りなく無に近い孤独であるとするなら、都市は密集した人と人の間に生じる無関心による見えない孤独であると言い換えてもいい。
戦後の経済成長によって、家族という共同体は、個人の自由と引き換えに機能を縮小しながら大都市に点在していった。自由は快適な反面、共同体がもつ相互扶助という強い絆を断ち切ってしまった。その断ち切れた絆を補うかのように人は都市をさまよい、その途中で社会の片隅に消えていく。それは、誰もが無関心でも快適でさえあれば生きていけると信じきってしまったせいかもしれない。
ニーチェは言う。
「お前たちに言ってやろう。我々が神を殺したのだと。お前たちと俺が!」
日本の現在の状況は、まさに神なき時代なのかもしれない。
世界はグローバル化の波で、ますます膨れあがり、社会の孤立化がますます進んでいくのだとすれば、我々を繋ぎとめる神を今こそこの手に掴み取らなければならないのではないか。国家によるセーフティネットの強化も大事であるが、前提として我々が殺してしまった「神」とは何であったのかを問いなおす必要があるのではないでしょうか。
「何のために生きるのかと言う確固たる意識がなければ、そのまわりにたとえパンの山を積まれても、人間は…この地上にとどまるよりは、むしろ自殺の道を選ぶに違いない。」
フョードル・ドストエフスキー 「カラマーゾフの兄弟」
「人々は生きるためにこの都会へ集まって来るらしい。しかし、僕はむしろ、ここではみんなが死んでゆくとしか思えないのだ。」

詩人の鋭い感性がとらえた都市の印象だ。それは孤独だったのではないか?
人は人を求めて都市に集う。そこに都市の魅力がある。しかし、一方で人は集団となることで匿名となり孤立化していくのも事実だ。
今、日本では都市の砂漠化が進んでいる。毎年増え続ける自殺者の数、幼児虐待や行方不明老人の問題など弱者が孤独の中で、都市に消えていく。
本当の砂漠が食料の欠乏という状態で目に見えるのに対して、都市の砂漠化は人々の無意識の生活の中に水面下で広がっていく。砂漠が限りなく無に近い孤独であるとするなら、都市は密集した人と人の間に生じる無関心による見えない孤独であると言い換えてもいい。
戦後の経済成長によって、家族という共同体は、個人の自由と引き換えに機能を縮小しながら大都市に点在していった。自由は快適な反面、共同体がもつ相互扶助という強い絆を断ち切ってしまった。その断ち切れた絆を補うかのように人は都市をさまよい、その途中で社会の片隅に消えていく。それは、誰もが無関心でも快適でさえあれば生きていけると信じきってしまったせいかもしれない。
ニーチェは言う。
「お前たちに言ってやろう。我々が神を殺したのだと。お前たちと俺が!」
日本の現在の状況は、まさに神なき時代なのかもしれない。
世界はグローバル化の波で、ますます膨れあがり、社会の孤立化がますます進んでいくのだとすれば、我々を繋ぎとめる神を今こそこの手に掴み取らなければならないのではないか。国家によるセーフティネットの強化も大事であるが、前提として我々が殺してしまった「神」とは何であったのかを問いなおす必要があるのではないでしょうか。
「何のために生きるのかと言う確固たる意識がなければ、そのまわりにたとえパンの山を積まれても、人間は…この地上にとどまるよりは、むしろ自殺の道を選ぶに違いない。」
フョードル・ドストエフスキー 「カラマーゾフの兄弟」