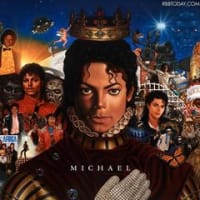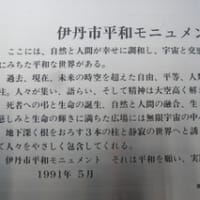シェイクスピアの「ハムレット」に次のようなセリフがある。
To be, or not to be: that is the question
ネットで調べると
「世に在る、世に在らぬ、それが疑問じゃ」(坪内逍遥訳)
「生きるか、死ぬか、そこが問題なのだ」(市河三喜・松浦嘉一訳)
「やる、やらぬ、それが問題だ」(小津次郎訳)
「このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ」(小田島雄志訳)
名訳というものは、訳者が生きた時代の「時代精神」なるものが反映されているのかもしれない。そして、創造的な誤読による多様性と、時代を超えた永遠性をこの短いセンテンスに凝縮させたシェイクスピアはやはりすごい。だから、いつの時代も国境を越えて全世界的に読み込まれ、豊かな議論の場を提供していくのだろう。
古典と呼ばれるものは、誤読しながら読み解かれ、読者を芳醇な知の体系へと導いていくがゆえに尊いと思う。
知識というものが、生きていくための便利なツールとして薄っぺらい情報にまとめられ、社会に氾濫している。「○○の力」、「~の生き方」などの自己啓発本が売れるのは、そのような社会状況を反映しているものと思われる。悩めだとか、力を抜いて生きよなどと、適当なことばかりを並べ立てて、大衆を振り回して、利益を貪ろうとしている。○○の著者絶賛、50万部突破などの宣伝はそんな出版業界の思惑を如実に現していると思う。
わかりにくいものを、わからないまま受け止め続けることが、学びを不断のものとさせる。わかりにくいということが、古典がもつ永遠性の本質であり、多様な知の場を広げていく原動力なのだから。

To be, or not to be: that is the question
ネットで調べると
「世に在る、世に在らぬ、それが疑問じゃ」(坪内逍遥訳)
「生きるか、死ぬか、そこが問題なのだ」(市河三喜・松浦嘉一訳)
「やる、やらぬ、それが問題だ」(小津次郎訳)
「このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ」(小田島雄志訳)
名訳というものは、訳者が生きた時代の「時代精神」なるものが反映されているのかもしれない。そして、創造的な誤読による多様性と、時代を超えた永遠性をこの短いセンテンスに凝縮させたシェイクスピアはやはりすごい。だから、いつの時代も国境を越えて全世界的に読み込まれ、豊かな議論の場を提供していくのだろう。
古典と呼ばれるものは、誤読しながら読み解かれ、読者を芳醇な知の体系へと導いていくがゆえに尊いと思う。
知識というものが、生きていくための便利なツールとして薄っぺらい情報にまとめられ、社会に氾濫している。「○○の力」、「~の生き方」などの自己啓発本が売れるのは、そのような社会状況を反映しているものと思われる。悩めだとか、力を抜いて生きよなどと、適当なことばかりを並べ立てて、大衆を振り回して、利益を貪ろうとしている。○○の著者絶賛、50万部突破などの宣伝はそんな出版業界の思惑を如実に現していると思う。
わかりにくいものを、わからないまま受け止め続けることが、学びを不断のものとさせる。わかりにくいということが、古典がもつ永遠性の本質であり、多様な知の場を広げていく原動力なのだから。