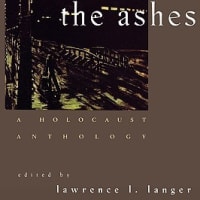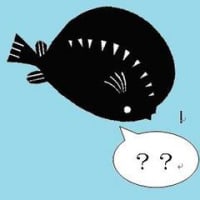幸福な老後とは何だろう。お金や健康以上に大切なのは、心の通うパートナーが傍にいることだろう。
その相手が、たとえ「家族」でなくても、純粋な愛で結ばれた二人が、老いを慈しみあう姿をアメリカ映画「ウーマン・ラブ・ウーマン」が描いている。
アビーとイーデスは、もう30年以上も一緒に暮してきて60歳をとうに過ぎた。質素で清潔な一軒家、笑いの絶えない食卓、そこには老醜のカケラもなかった。ある夜、庭にあるムク鳥の巣箱に餌をやろうとして、アビーは誤って脚立から落ち、脳卒中で救急病院に運ばれた。手術後の彼女の手を握りたいとイーデスは看護婦に懇願した。答えは、「いま患者さんに会えるのはご家族だけです」
待合所で、まんじりともせず夜明けを迎え、イーデスは手術の結果を聞いた。
「その方は、今朝三時に死亡しました」
「ええっ? 私はずっとここで待っていたのですよ」
「でも、あなたはご家族じゃないでしょう?」
病院が、こうして家族以外を排除する国際的慣習はどこから生まれたのだろう。たぶん、患者の財産をめぐるトラブルに病院側が巻き込まれまいとする経験的な知恵であろう。
アビーの唯一の親戚という若い甥夫婦がやってきた。葬式もすんだ。今まで会ったこともないのに、「叔母の品々を処分する」と彼らは言い出した。二人の暮しがしみこんだ家具やポットの「思い出」さえ奪い、「名義が叔母だから、家も売却したい」と言い出した。
「でも、私はアビーと二人でローンを払ってきたのですよ。今さら私はどこに行けばいいのでしょう」
亡き叔母とどんなに堅い絆で結ばれていようと、若夫婦にとってイーデスは「赤の他人」である。愛も追憶もオレたちには関係ない。金目のものはビタ一文「他人」に渡すものか。
ラストシーンは、一切のモノも記憶も室内から消えた一軒家が、売却を待ってポツンと建っている。イーデスは一体どこに行ってしまったのだろうか。
惰性で暮す配偶者よりも熱い絆の暮しが、かつて、確かにここにあった。(信)
著:石井信平(2003年1月)
日経新聞「描かれたエルダー」掲載
アメリカ、2000年製作
HBO Film Presents
脚本・監督 Jane Anderson
その相手が、たとえ「家族」でなくても、純粋な愛で結ばれた二人が、老いを慈しみあう姿をアメリカ映画「ウーマン・ラブ・ウーマン」が描いている。
アビーとイーデスは、もう30年以上も一緒に暮してきて60歳をとうに過ぎた。質素で清潔な一軒家、笑いの絶えない食卓、そこには老醜のカケラもなかった。ある夜、庭にあるムク鳥の巣箱に餌をやろうとして、アビーは誤って脚立から落ち、脳卒中で救急病院に運ばれた。手術後の彼女の手を握りたいとイーデスは看護婦に懇願した。答えは、「いま患者さんに会えるのはご家族だけです」
待合所で、まんじりともせず夜明けを迎え、イーデスは手術の結果を聞いた。
「その方は、今朝三時に死亡しました」
「ええっ? 私はずっとここで待っていたのですよ」
「でも、あなたはご家族じゃないでしょう?」
病院が、こうして家族以外を排除する国際的慣習はどこから生まれたのだろう。たぶん、患者の財産をめぐるトラブルに病院側が巻き込まれまいとする経験的な知恵であろう。
アビーの唯一の親戚という若い甥夫婦がやってきた。葬式もすんだ。今まで会ったこともないのに、「叔母の品々を処分する」と彼らは言い出した。二人の暮しがしみこんだ家具やポットの「思い出」さえ奪い、「名義が叔母だから、家も売却したい」と言い出した。
「でも、私はアビーと二人でローンを払ってきたのですよ。今さら私はどこに行けばいいのでしょう」
亡き叔母とどんなに堅い絆で結ばれていようと、若夫婦にとってイーデスは「赤の他人」である。愛も追憶もオレたちには関係ない。金目のものはビタ一文「他人」に渡すものか。
ラストシーンは、一切のモノも記憶も室内から消えた一軒家が、売却を待ってポツンと建っている。イーデスは一体どこに行ってしまったのだろうか。
惰性で暮す配偶者よりも熱い絆の暮しが、かつて、確かにここにあった。(信)
著:石井信平(2003年1月)
日経新聞「描かれたエルダー」掲載
アメリカ、2000年製作
HBO Film Presents
脚本・監督 Jane Anderson