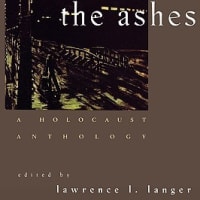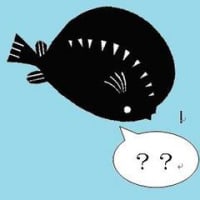―天才・田中希代子の波乱の生涯―
石井信平
1996年2月22日午後、いつものように田中希代子のレッスンを受けに来た生徒が、呼び鈴を押した。返事がない。同じ敷地の母屋に住む甥が駆けつけ、合鍵で玄関を開けた。そこに、希代子は車椅子から前のめりに投げ出される姿勢で倒れていた。脳溢血だった。
2月26日午前、練馬区の病院で希代子の心臓と呼吸が停止した。遺体は自宅のレッスン室に帰った。窓辺に頭を寄せ、グランドピアノの脇に、横たえられた。午後になって、宮内庁の車が着き、職員が口上した。「皇后陛下からの、悲しみで一杯です、とのお言葉を、お伝えに参りました」。そこで渡されたのは野の草花で、緑のリボンが目に鮮やかだった。美智子皇后が、自ら庭で草花を摘んで作った花束だった。それは、「希代子さんの演奏は、私の、心の支えでした」と親しい人に語った皇后が、余人の理解を超えた苦労で同時代をともに生きた芸術家の死に贈る、別れのしるしだった。
かつて、1955年当時、パリやニースで希代子と交流した作曲家・三善晃は、葬儀の弔辞で、希代子の写真に語りかけた。
「桐朋学園のピアノ科に、評判の暴れん坊がいます。ある時、彼の母親が、希代子さんのCDを彼に聴かせました。やがて彼は別室に駆け込むと、そこで嗚咽していました。『この世に、こんなピアノを、弾く人がいたのか……』そう言ったのです。希代子さん、あなたの音楽は、今、確実に若い人に伝えられているのです」
■鮮烈なデビュー
私は、田中希代子の演奏を、ナマで聴いたことはない。30歳代の半ばで演奏をやめた彼女の音楽を愛惜する人人が、残された録音テープをもとにCDをつくった。その1枚を聴いて、私は衝撃を受けた。サン・サーンス作曲、ピアノ協奏曲第五番。1965年録音、彼女が33歳の時である。それを聴いた時の感動は、今でも覚えている。狂うような激しさ、そして、それと隣り合わせの、みなし児のような孤独感。「メリハリがある」などという、のどかな表現ではおさまり切らない音楽が、疾風のように駆け抜けて行った。
ピアニスト田中希代子が生まれたのは、1932年(昭和7年)。父はバイオリニスト田中詠人、母は声楽家・田中伸枝。妊娠中毒により母子ともに危険な状態での誕生は、波乱に満ちた希代子の生涯を暗示していた。
中国戦線がドロ沼化する頃、時代に抵抗するように、4歳の娘・希代子のピアノ・レッスンが開始された。1945年、国敗れて、音楽が残された。焦土に国民がへたり込んでいた時、田中家からは希代子の弾くピアノが、うなりをあげて聞こえて来た。安川可寿子に師事したことは、さらに彼女の才能に弾みをつけた。1949年、日本音楽コンクール特別賞を受ける。17歳の時である。「東京裁判」と軍事指導者たちの公職追放が相次ぐ時、希代子の鮮烈なデビューは、水泳の古橋・橋爪の世界記録とともに、時代の転換を象徴していた。音楽評論家・遠山一行はその時の希代子の演奏について「この先この少女が準備している音楽の世界をはかりかね、茫然とした」と記している。
1950年、戦後初めてのフランス政府給費留学生に選ばれた6人のなかに、18歳の田中希代子の名前があった。インド洋を横切る40日間の船旅の後、9月25日、パリ到着。思いは、選ばれしことの恍惚と不安。300人の受験者中、トップの成績でパリ国立高等音楽院(コンセルバトワール)に入学した。パリではラザール・レヴィに師事した。レヴィからの安川宛て書簡にはこうある。「……また繰り返すようだが、実に感動的だ。彼女のタッチは、深みがあると同時に、幽玄である。一言に言えば、参ってしまった」。
希代子の演奏が与えた衝撃は、ひとりレヴィに対してだけではなかった。翌年6月、コンセルバトワール卒業試験を受けた希代子は、一等を受賞した。
一等を得た者はパリの大新聞に写真入で掲載され、もはや音楽院の教育をこれ以上必要としない。つまり在学一年に満たないで、希代子は卒業した。レヴィの記憶では、これは、1933年、やはりレヴィ門下のロシア人、オボレスカ嬢以来のことであった。
■皇太子妃とのツーショット
卒業後も、希代子はパリにとどまった。1952年、ジュネーブ国際コンクールで1位なしの2位受賞。53年、パリのサル・ガヴォーでデビュー・リサイタル。同年、ロン・ティボー国際コンクールで4位。そして、1955年3月、ショパン国際コンクールに日本人として初めて10位に入賞した。
1位、ハラシェヴィチ、2位、アシュケナージ。時は冷戦の真っただ中で上位入賞は東欧からの出場者が占拠した。審査員のひとりだったイタリア人ミケランジェリは、希代子への採点の不当を訴えて、最終表決にサインすることを拒否した。
この夏の夜、23歳の若い、美貌のピアニストは日本に凱旋帰国する。日比谷公会堂でのコンサート。まだ少女の面影を残すポニーテールの髪は、カメラのフラッシュに輝いた。メディアが、いつの時代も表層を撫でるだけであるのに対し、音楽評論の重鎮・野村光一は、希代子の本質に触れて、当時、次のように寄稿している。
「彼女の内に、深く沈潜している、その何ものかを表す唯一の機会は、ピアノを弾いているとき、その音を通して、爆発する以外にないのである。だから、彼女の演奏には、低気圧のようなものが、いつも底の方にひそんでいて、それが一種の不気味ささえも催させる。これが、彼女の魅力といえばいえる……」
新進ピアニストの魅力が「不気味さ」とは―。ここに希代子の出現が、並のデビューではない、一種ただならぬ空気を漂わせていたことが窺える。
拠点をパリに置き、欧米はもちろん、遠くブラジルまで演奏旅行を続ける生活が始まった。57年には、日本人の新進作曲家と結婚。パリは25歳の希代子にとって、祝福された「花の都」だった。しかし、祖国が安保闘争で揺れる頃、希代子の身辺にも異変が起こった。1961年、離婚を機会に、希代子は11年住み慣れたパリを去り、ウィーンに移住する。大好きなパリ、第二の母国語フランス語を捨て、新しい跳躍に彼女は賭けた。29歳、真っ赤なオペルを運転してウィーンの街を颯爽と走る希代子には、なお無限の未来が、目の前に広がっていた。
このころ、60年代初め、一時帰国した希代子は聖心女子大学に招かれ演奏した。これを聴いた美智子・皇太子妃(当時)は演奏後の歓談の時、率直な感動のことばを希代子に伝えたという。この時撮られたツーショットの写真は、死ぬまで希代子のピアノの上に飾られた。
■病魔の拷問がはじまった
ウィーンと東京を行き来する生活をつづけるうち、希代子は時々、高熱と疲れを訴えることが多くなった。2年先まで予定された演奏会のスケジュールをこなしながら、体の体調は次第に由々しい事態になってきた。疲れは、痛みに変わり、40度の高熱が1ヶ月つづいた。1968年3月、京都会館での京響との共演、ショパンのピアノコンチェルト第一番を弾いたのが、その時だった。以後予定されていたヨーロッパでのコンサートはキャンセルされた。田中希代子の姿は音楽界から消えた。「消えた」というのは、雲や霧が消えたことを連想させる表現だが、当人にとっては、消えることなき病魔の拷問を受けつづける、七転八倒の始まりだった。
しかし、本人は事態をそれほど深刻に受け止めていなかったフシがある。病気だからいずれは治る、と信じていた。あまりに多忙な日々をふりかえれば、少し休息する良い機会だと思っていた。
「これで、初心に帰れるわ。音階から、みっちり磨き直すんだ」希代子がそう言っていたのを弟・千香士(N響コンサートマスター)は忘れない。今となっては悲しいが、毎朝の練習は休みなく続けられた。
急性の肝機能障害、これが聖路加病院での最初の診断だった。しかし投薬、静養をつづけても容態は一向に好転しなかった。やがては、医療の限りを尽くしながら、遠くに「効くらしい」うわさの祈祷師ありときけば、まず行って、その霊験にすがりついた。
田中家に残された写真入れの箱に、私は異様な一枚を見た。全身を包帯で巻かれ、そのあまりのぶ厚さのゆえに、まるで雪ダルマのなかにスッポリと体を入れたような一人の女が、かろうじて苦しげな顔だけを出しているスナップ写真だった。ある民間団体による温熱療法を受けている田中希代子の姿である。「一ヶ月間、この状態を我慢しました」。千香士の妻の述懐である。
ある新興宗教の教祖からは、「副腎皮質ホルモンをやめない限り治らない。病は気からだ」と言われ、薬をやめた。それがさらに病状を悪化させ、「食堂憩室」という食堂に小さな袋が出来る病気を併発して手術を受ける羽目になった。それらの「騒ぎ」をよそに、確実に進行していたのは精神の絶望であった。そして、最終的に「膠原病」の診断が下された。
原因も治療法も分からぬ難病だった。高熱に伴うその苦痛は、千香士の言葉によれば「からだをケサがけに刀で切り刻まれる痛さ」だった。当時の医師の説明によると、この病気により、内臓を包む膜が溶けてなくなる結果、それぞれの臓物が直接ふれあうことによる痛みだという。それを、なんとか和らげるための手術が何度も行われた。
希代子が、もはや自力では入浴できなくなった時から、その介護は千香士の役目となった。男の力でなければ支え切れない介護の時、いつしか二人は、これを週に一度の「お風呂会議」と呼んだ。足腰が確実に衰え、次第に手の指が変形を始めた。希望がひとつひとつ摘み取られて行く。会議とは、それを二人で確かめ合うことでしかなかった。
ああ、やっぱり。もう、ピアノを弾くことは駄目かもしれない。うろたえること、自分を見失うこと、絶望すること。この残酷な三連音符を、ただ、それだけを、死ぬまで演奏をつづけよと、音楽の神は、彼女に命令したのである。
生まれた時からピアニストになることを約束されていた。そして、世界中のコンサートホールがピアニスト・キヨコを待望し、熱狂して迎えた。彼女は、自分が何者か、自分のアイデンティティが何かなど、ただ一度も考えたことはなく、悩んでこともなかった。このままピアノを弾けないなら、自分は一体何者だ?どうやって生きてゆけばいいのか?35歳から8年間の懊悩の日々。痛みを伴って萎縮を続ける手足、たゆみない肉体の落魄と変貌を、恐怖をもって凝視しつづけながら、考えたのはその一点だった。
ベトナム戦争を尻目に、高度成長の日本のカネを目当てに、「外タレ」音楽家が引っ切りなしに来始めた頃である。
1970年、闘病を続ける娘への万感の思いを残して、父親が死んだ。娘を一流のピアニストにすること、そのことにだけ「希望」を託して希代子と名付けた父が、最後に目に焼き付けたのは、絶望に立ち往生する娘の姿だった。
■ピアノを弾けないピアノ教師
希代子はピアニストを断念する。アイデンティティの危機は、同時に、生計の危機をもはらんでいた。教師になってはどうか、の誘いもあった。そのころ、希代子と千香士は、たまたまテレビで、他愛ないカンフー映画を見ていた。AとBの二人の拳士が登場する。Aは道場を継いで後進の指導をすることになった。Bは、腕を磨き、武者修行に出発する時、Aに向かって言う。
「お前は、遂に教えるほどに弱くなったか」。
「そうよ、その通りよ」希代子の声だった。これは当時の彼女の、演奏家を断念することの無念と、教えることへのためらいの気持ちを表すエピソードである。
国立音大学長・有島大五郎に声を掛けられ、結局、希代子はピアノを弾けないピアノ教師になる。今、同付属高校でピアノを教える吉野康弘は、その初期の生徒になる。1975年、彼が高校三年生の時だった。吉野は語る。
「レッスン室に入ると、空気が違います。先生の、聴くことの集中力が伝わってくるのです。息もしていないんじゃないか……先生の前で失礼な音を出せないんです」そう言って吉野は、ショパンのバラード一番のイントロを、百回やらされたことを語ってくれた。その時、忍耐の限界を耐えていたのは、むしろ希代子の方だったろう。
吉野の国立音大卒業の課題曲は、リストの「メフィスト・ワルツ」だった。一ヶ月前に曲がきまり、すぐに希代子は脳溢血で倒れた。残された時間はあまりに少なかった。二階の寝室に希代子は横たわり、電話機を握った。階下のレッスン室の受話器をはずし、吉野はそれをピアノの横に置いた。
「お始めなさい」希代子の力弱い声が受話器から聞こえた。まさに天井からの師の声に促され、吉野は引き始めた。目の前の楽譜が、あふれる涙で掻き消えた。
「こんなにまでして私の演奏を聴いて下さる、ただそのことの感謝で一杯でした。」
今春、国立音大大学院を卒業した石島美奈子にとって、忘れられない立ち往生の場所がある。ショパンの「エチュード」作品10ハ長調。三度と六度の和音が交替するところ。
「どうしても、指に無駄な力が入ってしまうのを、先生は、指先の溶けた、グニョグニョと力ない指を、鍵盤に置いて、『そっと、手首を落とすように、楽に力を抜いて……そうよ、今のそれよ……』と、何度も仕草を繰り返し、私ができるのを待っていて下さった」
弾けない先生による、極め付きは、次の場面である。
リストの「バラード」二番、ロ短調を石島は弾く。左手で半音階のレガート。「左手は、波のうねりよ」と適切なイメージの言葉が希代子から投げられ、途中マーチがあって、主旋律にもどる。
「その時、先生は、突然そのメロディーを歌い出されたのです。ウットリと、いとおしそうに……先生の、音楽の全部が私に伝わってきた瞬間でした。」
■「石畳の道を歩きたい」
世間が、田中希代子の存在をすっかり忘れた頃、彼女のかつての演奏を録音したテープの一部が、門下生の手で、音楽評論家・相沢昭八郎のもとに届けられた。「保存状態が悪いテープを、修復・保存するにはどうしたらよいか」と彼は相談されたのである。相沢はテープを聞いた。その時の衝撃を「正気と狂気の、分水領を歩くにも似た戦慄」と後に『毎日新聞』に寄稿した。三善晃の協力を得て「田中希代子のレコードを作る会」が発足した。「私は過去の人よ」とCD化を固辞する希代子を説得し、ポーランドや東ドイツの放送局の地下室に眠っていたテープを探し出し、共演者の了解と著作権をクリアする地道な努力の末に、希代子のかつての演奏は、CD六枚の形で永く残されることになった。
相沢の毎日新聞記事を、目を洗われる思いで読んだのは、TBSラジオのプロデューサー・松井邦雄だった。彼は、すぐに希代子の半生を、そのピアノ演奏とともに構成する番組企画書を書いた。1989年2月19日、午後8時から1時間、ラジオ・スペシャル「夜明けのショパン」が放送された。
放送後、宮内庁から、番組のテープを求める連絡が松井のもとに来た。昭和天皇の逝去で聞くことが出来なかった美智子皇后の希望だった。早速、テープと、出来たばかりのCDが届けられた。 折り返し、皇后から希代子へのお見舞いと、スタッフへの感謝のことばが寄せられた。
今では貴重極まりない希代子の肉声が、番組の中でこう語る。
「……もし、神様が、お前からは随分いろいろなものを奪ったけれども、お皿を洗う能力は返してあげよう、といったら、私は跳び上がって喜ぶでしょうねぇ。お皿を洗うことだって、立派な自己表現ですもの……」
そのあと、若い女性が彼女に尋ねる。
「もう一度、行ってみたい場所は?」
彼女は、すぐには答えられず「何をするために?」と問い返した。移動すること、旅行することなど、彼女はとっくに断念している。思い直して、希代子は答える。
「……そりゃあ、パリよ」
「パリで、何をしたいですか?」
若い女性の質問はあくまで残酷だった。
「そうねぇ、誰もいない石畳の道を歩きたいわ……もし歩けるものならねぇ」
■神様のような方
媚びることない、ひとりの大人の女性が、そこにいる。田中希代子の音楽にまず感じるのは、そのスケールの大きさである。箱庭を拒否し、大海の広がりに船出してゆく音楽だ。小さな完成に目もくれず、むしろ巨大な未完成であろうとする。そして「アンビヴァレンツ」。ため息のような静寂と、とどめようのない熱狂。底知れぬ孤独感と、天国的な官能。相矛盾するものが同居し、互いに光と影となって、ノミで彫り上げたような陰影を音楽全体につくり上げている。それは、新しい秩序の予感をたたえている。
予感はまた、新しいピアニストの登場でもある。田部京子は満9歳から希代子のレッスンを受け、ベルリンを拠点に、今や世界中で演奏活動をしている。7月11日、埼玉県北本市での、彼女のリサイタルに私は行ってきた。吉松隆作曲「真夜中のノエル」における、深い静寂。この人は「しじま」を美しく表現することを、間違いなく紀代子から受け継いでいる、と私は思った。
田部京子は言う。
「先生のレッスンにおける、沈黙の時のすばらしさが、私の今の音楽を作ってくれたと思います。私が弾き終わると、長い沈黙があり、やがて『とてもいい』と一言があり、そして、また長い沈黙がありました。……亡くなられたのは、天からのお迎えが来たとしか思えません。私は天から先生に見守られています。生きていらっしゃる時から、私にとって神様のような方でした」
田中希代子は、この世のステージから旅立っていった。点滴や、車椅子や、地上のくびきから、すべて解放されて、いま田中希代子は18歳の少女の足取りで、パリの石畳を踏み締めていることだろう。
(文中敬称略
<1996年10月「現代」掲載>
石井信平
1996年2月22日午後、いつものように田中希代子のレッスンを受けに来た生徒が、呼び鈴を押した。返事がない。同じ敷地の母屋に住む甥が駆けつけ、合鍵で玄関を開けた。そこに、希代子は車椅子から前のめりに投げ出される姿勢で倒れていた。脳溢血だった。
2月26日午前、練馬区の病院で希代子の心臓と呼吸が停止した。遺体は自宅のレッスン室に帰った。窓辺に頭を寄せ、グランドピアノの脇に、横たえられた。午後になって、宮内庁の車が着き、職員が口上した。「皇后陛下からの、悲しみで一杯です、とのお言葉を、お伝えに参りました」。そこで渡されたのは野の草花で、緑のリボンが目に鮮やかだった。美智子皇后が、自ら庭で草花を摘んで作った花束だった。それは、「希代子さんの演奏は、私の、心の支えでした」と親しい人に語った皇后が、余人の理解を超えた苦労で同時代をともに生きた芸術家の死に贈る、別れのしるしだった。
かつて、1955年当時、パリやニースで希代子と交流した作曲家・三善晃は、葬儀の弔辞で、希代子の写真に語りかけた。
「桐朋学園のピアノ科に、評判の暴れん坊がいます。ある時、彼の母親が、希代子さんのCDを彼に聴かせました。やがて彼は別室に駆け込むと、そこで嗚咽していました。『この世に、こんなピアノを、弾く人がいたのか……』そう言ったのです。希代子さん、あなたの音楽は、今、確実に若い人に伝えられているのです」
■鮮烈なデビュー
私は、田中希代子の演奏を、ナマで聴いたことはない。30歳代の半ばで演奏をやめた彼女の音楽を愛惜する人人が、残された録音テープをもとにCDをつくった。その1枚を聴いて、私は衝撃を受けた。サン・サーンス作曲、ピアノ協奏曲第五番。1965年録音、彼女が33歳の時である。それを聴いた時の感動は、今でも覚えている。狂うような激しさ、そして、それと隣り合わせの、みなし児のような孤独感。「メリハリがある」などという、のどかな表現ではおさまり切らない音楽が、疾風のように駆け抜けて行った。
ピアニスト田中希代子が生まれたのは、1932年(昭和7年)。父はバイオリニスト田中詠人、母は声楽家・田中伸枝。妊娠中毒により母子ともに危険な状態での誕生は、波乱に満ちた希代子の生涯を暗示していた。
中国戦線がドロ沼化する頃、時代に抵抗するように、4歳の娘・希代子のピアノ・レッスンが開始された。1945年、国敗れて、音楽が残された。焦土に国民がへたり込んでいた時、田中家からは希代子の弾くピアノが、うなりをあげて聞こえて来た。安川可寿子に師事したことは、さらに彼女の才能に弾みをつけた。1949年、日本音楽コンクール特別賞を受ける。17歳の時である。「東京裁判」と軍事指導者たちの公職追放が相次ぐ時、希代子の鮮烈なデビューは、水泳の古橋・橋爪の世界記録とともに、時代の転換を象徴していた。音楽評論家・遠山一行はその時の希代子の演奏について「この先この少女が準備している音楽の世界をはかりかね、茫然とした」と記している。
1950年、戦後初めてのフランス政府給費留学生に選ばれた6人のなかに、18歳の田中希代子の名前があった。インド洋を横切る40日間の船旅の後、9月25日、パリ到着。思いは、選ばれしことの恍惚と不安。300人の受験者中、トップの成績でパリ国立高等音楽院(コンセルバトワール)に入学した。パリではラザール・レヴィに師事した。レヴィからの安川宛て書簡にはこうある。「……また繰り返すようだが、実に感動的だ。彼女のタッチは、深みがあると同時に、幽玄である。一言に言えば、参ってしまった」。
希代子の演奏が与えた衝撃は、ひとりレヴィに対してだけではなかった。翌年6月、コンセルバトワール卒業試験を受けた希代子は、一等を受賞した。
一等を得た者はパリの大新聞に写真入で掲載され、もはや音楽院の教育をこれ以上必要としない。つまり在学一年に満たないで、希代子は卒業した。レヴィの記憶では、これは、1933年、やはりレヴィ門下のロシア人、オボレスカ嬢以来のことであった。
■皇太子妃とのツーショット
卒業後も、希代子はパリにとどまった。1952年、ジュネーブ国際コンクールで1位なしの2位受賞。53年、パリのサル・ガヴォーでデビュー・リサイタル。同年、ロン・ティボー国際コンクールで4位。そして、1955年3月、ショパン国際コンクールに日本人として初めて10位に入賞した。
1位、ハラシェヴィチ、2位、アシュケナージ。時は冷戦の真っただ中で上位入賞は東欧からの出場者が占拠した。審査員のひとりだったイタリア人ミケランジェリは、希代子への採点の不当を訴えて、最終表決にサインすることを拒否した。
この夏の夜、23歳の若い、美貌のピアニストは日本に凱旋帰国する。日比谷公会堂でのコンサート。まだ少女の面影を残すポニーテールの髪は、カメラのフラッシュに輝いた。メディアが、いつの時代も表層を撫でるだけであるのに対し、音楽評論の重鎮・野村光一は、希代子の本質に触れて、当時、次のように寄稿している。
「彼女の内に、深く沈潜している、その何ものかを表す唯一の機会は、ピアノを弾いているとき、その音を通して、爆発する以外にないのである。だから、彼女の演奏には、低気圧のようなものが、いつも底の方にひそんでいて、それが一種の不気味ささえも催させる。これが、彼女の魅力といえばいえる……」
新進ピアニストの魅力が「不気味さ」とは―。ここに希代子の出現が、並のデビューではない、一種ただならぬ空気を漂わせていたことが窺える。
拠点をパリに置き、欧米はもちろん、遠くブラジルまで演奏旅行を続ける生活が始まった。57年には、日本人の新進作曲家と結婚。パリは25歳の希代子にとって、祝福された「花の都」だった。しかし、祖国が安保闘争で揺れる頃、希代子の身辺にも異変が起こった。1961年、離婚を機会に、希代子は11年住み慣れたパリを去り、ウィーンに移住する。大好きなパリ、第二の母国語フランス語を捨て、新しい跳躍に彼女は賭けた。29歳、真っ赤なオペルを運転してウィーンの街を颯爽と走る希代子には、なお無限の未来が、目の前に広がっていた。
このころ、60年代初め、一時帰国した希代子は聖心女子大学に招かれ演奏した。これを聴いた美智子・皇太子妃(当時)は演奏後の歓談の時、率直な感動のことばを希代子に伝えたという。この時撮られたツーショットの写真は、死ぬまで希代子のピアノの上に飾られた。
■病魔の拷問がはじまった
ウィーンと東京を行き来する生活をつづけるうち、希代子は時々、高熱と疲れを訴えることが多くなった。2年先まで予定された演奏会のスケジュールをこなしながら、体の体調は次第に由々しい事態になってきた。疲れは、痛みに変わり、40度の高熱が1ヶ月つづいた。1968年3月、京都会館での京響との共演、ショパンのピアノコンチェルト第一番を弾いたのが、その時だった。以後予定されていたヨーロッパでのコンサートはキャンセルされた。田中希代子の姿は音楽界から消えた。「消えた」というのは、雲や霧が消えたことを連想させる表現だが、当人にとっては、消えることなき病魔の拷問を受けつづける、七転八倒の始まりだった。
しかし、本人は事態をそれほど深刻に受け止めていなかったフシがある。病気だからいずれは治る、と信じていた。あまりに多忙な日々をふりかえれば、少し休息する良い機会だと思っていた。
「これで、初心に帰れるわ。音階から、みっちり磨き直すんだ」希代子がそう言っていたのを弟・千香士(N響コンサートマスター)は忘れない。今となっては悲しいが、毎朝の練習は休みなく続けられた。
急性の肝機能障害、これが聖路加病院での最初の診断だった。しかし投薬、静養をつづけても容態は一向に好転しなかった。やがては、医療の限りを尽くしながら、遠くに「効くらしい」うわさの祈祷師ありときけば、まず行って、その霊験にすがりついた。
田中家に残された写真入れの箱に、私は異様な一枚を見た。全身を包帯で巻かれ、そのあまりのぶ厚さのゆえに、まるで雪ダルマのなかにスッポリと体を入れたような一人の女が、かろうじて苦しげな顔だけを出しているスナップ写真だった。ある民間団体による温熱療法を受けている田中希代子の姿である。「一ヶ月間、この状態を我慢しました」。千香士の妻の述懐である。
ある新興宗教の教祖からは、「副腎皮質ホルモンをやめない限り治らない。病は気からだ」と言われ、薬をやめた。それがさらに病状を悪化させ、「食堂憩室」という食堂に小さな袋が出来る病気を併発して手術を受ける羽目になった。それらの「騒ぎ」をよそに、確実に進行していたのは精神の絶望であった。そして、最終的に「膠原病」の診断が下された。
原因も治療法も分からぬ難病だった。高熱に伴うその苦痛は、千香士の言葉によれば「からだをケサがけに刀で切り刻まれる痛さ」だった。当時の医師の説明によると、この病気により、内臓を包む膜が溶けてなくなる結果、それぞれの臓物が直接ふれあうことによる痛みだという。それを、なんとか和らげるための手術が何度も行われた。
希代子が、もはや自力では入浴できなくなった時から、その介護は千香士の役目となった。男の力でなければ支え切れない介護の時、いつしか二人は、これを週に一度の「お風呂会議」と呼んだ。足腰が確実に衰え、次第に手の指が変形を始めた。希望がひとつひとつ摘み取られて行く。会議とは、それを二人で確かめ合うことでしかなかった。
ああ、やっぱり。もう、ピアノを弾くことは駄目かもしれない。うろたえること、自分を見失うこと、絶望すること。この残酷な三連音符を、ただ、それだけを、死ぬまで演奏をつづけよと、音楽の神は、彼女に命令したのである。
生まれた時からピアニストになることを約束されていた。そして、世界中のコンサートホールがピアニスト・キヨコを待望し、熱狂して迎えた。彼女は、自分が何者か、自分のアイデンティティが何かなど、ただ一度も考えたことはなく、悩んでこともなかった。このままピアノを弾けないなら、自分は一体何者だ?どうやって生きてゆけばいいのか?35歳から8年間の懊悩の日々。痛みを伴って萎縮を続ける手足、たゆみない肉体の落魄と変貌を、恐怖をもって凝視しつづけながら、考えたのはその一点だった。
ベトナム戦争を尻目に、高度成長の日本のカネを目当てに、「外タレ」音楽家が引っ切りなしに来始めた頃である。
1970年、闘病を続ける娘への万感の思いを残して、父親が死んだ。娘を一流のピアニストにすること、そのことにだけ「希望」を託して希代子と名付けた父が、最後に目に焼き付けたのは、絶望に立ち往生する娘の姿だった。
■ピアノを弾けないピアノ教師
希代子はピアニストを断念する。アイデンティティの危機は、同時に、生計の危機をもはらんでいた。教師になってはどうか、の誘いもあった。そのころ、希代子と千香士は、たまたまテレビで、他愛ないカンフー映画を見ていた。AとBの二人の拳士が登場する。Aは道場を継いで後進の指導をすることになった。Bは、腕を磨き、武者修行に出発する時、Aに向かって言う。
「お前は、遂に教えるほどに弱くなったか」。
「そうよ、その通りよ」希代子の声だった。これは当時の彼女の、演奏家を断念することの無念と、教えることへのためらいの気持ちを表すエピソードである。
国立音大学長・有島大五郎に声を掛けられ、結局、希代子はピアノを弾けないピアノ教師になる。今、同付属高校でピアノを教える吉野康弘は、その初期の生徒になる。1975年、彼が高校三年生の時だった。吉野は語る。
「レッスン室に入ると、空気が違います。先生の、聴くことの集中力が伝わってくるのです。息もしていないんじゃないか……先生の前で失礼な音を出せないんです」そう言って吉野は、ショパンのバラード一番のイントロを、百回やらされたことを語ってくれた。その時、忍耐の限界を耐えていたのは、むしろ希代子の方だったろう。
吉野の国立音大卒業の課題曲は、リストの「メフィスト・ワルツ」だった。一ヶ月前に曲がきまり、すぐに希代子は脳溢血で倒れた。残された時間はあまりに少なかった。二階の寝室に希代子は横たわり、電話機を握った。階下のレッスン室の受話器をはずし、吉野はそれをピアノの横に置いた。
「お始めなさい」希代子の力弱い声が受話器から聞こえた。まさに天井からの師の声に促され、吉野は引き始めた。目の前の楽譜が、あふれる涙で掻き消えた。
「こんなにまでして私の演奏を聴いて下さる、ただそのことの感謝で一杯でした。」
今春、国立音大大学院を卒業した石島美奈子にとって、忘れられない立ち往生の場所がある。ショパンの「エチュード」作品10ハ長調。三度と六度の和音が交替するところ。
「どうしても、指に無駄な力が入ってしまうのを、先生は、指先の溶けた、グニョグニョと力ない指を、鍵盤に置いて、『そっと、手首を落とすように、楽に力を抜いて……そうよ、今のそれよ……』と、何度も仕草を繰り返し、私ができるのを待っていて下さった」
弾けない先生による、極め付きは、次の場面である。
リストの「バラード」二番、ロ短調を石島は弾く。左手で半音階のレガート。「左手は、波のうねりよ」と適切なイメージの言葉が希代子から投げられ、途中マーチがあって、主旋律にもどる。
「その時、先生は、突然そのメロディーを歌い出されたのです。ウットリと、いとおしそうに……先生の、音楽の全部が私に伝わってきた瞬間でした。」
■「石畳の道を歩きたい」
世間が、田中希代子の存在をすっかり忘れた頃、彼女のかつての演奏を録音したテープの一部が、門下生の手で、音楽評論家・相沢昭八郎のもとに届けられた。「保存状態が悪いテープを、修復・保存するにはどうしたらよいか」と彼は相談されたのである。相沢はテープを聞いた。その時の衝撃を「正気と狂気の、分水領を歩くにも似た戦慄」と後に『毎日新聞』に寄稿した。三善晃の協力を得て「田中希代子のレコードを作る会」が発足した。「私は過去の人よ」とCD化を固辞する希代子を説得し、ポーランドや東ドイツの放送局の地下室に眠っていたテープを探し出し、共演者の了解と著作権をクリアする地道な努力の末に、希代子のかつての演奏は、CD六枚の形で永く残されることになった。
相沢の毎日新聞記事を、目を洗われる思いで読んだのは、TBSラジオのプロデューサー・松井邦雄だった。彼は、すぐに希代子の半生を、そのピアノ演奏とともに構成する番組企画書を書いた。1989年2月19日、午後8時から1時間、ラジオ・スペシャル「夜明けのショパン」が放送された。
放送後、宮内庁から、番組のテープを求める連絡が松井のもとに来た。昭和天皇の逝去で聞くことが出来なかった美智子皇后の希望だった。早速、テープと、出来たばかりのCDが届けられた。 折り返し、皇后から希代子へのお見舞いと、スタッフへの感謝のことばが寄せられた。
今では貴重極まりない希代子の肉声が、番組の中でこう語る。
「……もし、神様が、お前からは随分いろいろなものを奪ったけれども、お皿を洗う能力は返してあげよう、といったら、私は跳び上がって喜ぶでしょうねぇ。お皿を洗うことだって、立派な自己表現ですもの……」
そのあと、若い女性が彼女に尋ねる。
「もう一度、行ってみたい場所は?」
彼女は、すぐには答えられず「何をするために?」と問い返した。移動すること、旅行することなど、彼女はとっくに断念している。思い直して、希代子は答える。
「……そりゃあ、パリよ」
「パリで、何をしたいですか?」
若い女性の質問はあくまで残酷だった。
「そうねぇ、誰もいない石畳の道を歩きたいわ……もし歩けるものならねぇ」
■神様のような方
媚びることない、ひとりの大人の女性が、そこにいる。田中希代子の音楽にまず感じるのは、そのスケールの大きさである。箱庭を拒否し、大海の広がりに船出してゆく音楽だ。小さな完成に目もくれず、むしろ巨大な未完成であろうとする。そして「アンビヴァレンツ」。ため息のような静寂と、とどめようのない熱狂。底知れぬ孤独感と、天国的な官能。相矛盾するものが同居し、互いに光と影となって、ノミで彫り上げたような陰影を音楽全体につくり上げている。それは、新しい秩序の予感をたたえている。
予感はまた、新しいピアニストの登場でもある。田部京子は満9歳から希代子のレッスンを受け、ベルリンを拠点に、今や世界中で演奏活動をしている。7月11日、埼玉県北本市での、彼女のリサイタルに私は行ってきた。吉松隆作曲「真夜中のノエル」における、深い静寂。この人は「しじま」を美しく表現することを、間違いなく紀代子から受け継いでいる、と私は思った。
田部京子は言う。
「先生のレッスンにおける、沈黙の時のすばらしさが、私の今の音楽を作ってくれたと思います。私が弾き終わると、長い沈黙があり、やがて『とてもいい』と一言があり、そして、また長い沈黙がありました。……亡くなられたのは、天からのお迎えが来たとしか思えません。私は天から先生に見守られています。生きていらっしゃる時から、私にとって神様のような方でした」
田中希代子は、この世のステージから旅立っていった。点滴や、車椅子や、地上のくびきから、すべて解放されて、いま田中希代子は18歳の少女の足取りで、パリの石畳を踏み締めていることだろう。
(文中敬称略
<1996年10月「現代」掲載>