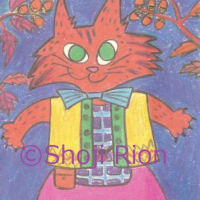父のアルバム
私の箪笥の引出しには、お気に入りのブラウスと一緒に、父のペンタックスと一冊の古いアルバムが入っている。
父は、このカメラで家族の写真を撮り、アルバムに残した。
私には、カメラの値打ちはわからない。
けれど、日曜日の午後など、ネルの布でレンズの手入れをしている、あぐらをかいた前かがみの父の背中は憶えている。
父はこのカメラを私が生まれてすぐに買ったようだ。
なぜなら、父が残したこのアルバムは、生まれて間もない赤ん坊の私の寝顔から始まるからだ。
おそらく父はこのカメラを、そうとうに無理をして買ったのだろう。
このカメラは、父の宝物だった。
私など、持ち上げて眼の高さに構えるだけでも、腕がふら付くような重みがあり、ピントを合わせるにも一苦労しそうな代物だ。
父はこのカメラで撮った写真の一枚一枚を、何冊ものアルバムに収めた。そして、そのアルバムは、家族の宝物となった。
父は自分の宝物で宝物を作って、私たちに残していったのだ。
そしてそのアルバムの最初の一冊が、父のカメラと共に、今、私の手元にある。
幾度かの引越しのときも、私は自分のバックに入れて運び、荷造りのダンボールにしまうことはなかった。
この一冊めのアルバムは、そのほとんどが私の乳幼児期の写真で埋まっている。
古さの染み込んだ赤い布張りのアルバムは、ページを開くと、なぜか、ラムネの香りがする。
淡い色合いの儚い甘い香りだ。
私が一番好きな写真は、父と二人で撮られた一枚である。
私はまだ、オムツをあてている歳で、やっと、よちよち歩き出した頃だろう。
父は大きく脚を広げて立っている。
その二本の脚の間にしゃがんで、私はよだれを垂らさんばかりにカメラに向かって笑っている。
おませにも私はベレー帽をかぶっている。
私の小さな両手は、両側に突っ立っている父のズボンを握っている。
ちょうど脛のあたりを握っているのだ。
つまり写っているのは、私と、膝から下の、父の黒いズボンを履いた二本の脚だけなのだ。
このモノクロの写真が、いつ何処で撮られたのか、誰が撮ってくれたものなのか、父がいない今となっては、もう知ることはできない。
脚しか写っていない父は、そのとき、どんな顔をして私を見下ろしていたのだろう。
そう考えるとき、私は小さな幼子に戻って、上を見上げている自分に気付く。
けれど、私の視線の先に、私をのぞき込む父の顔はない。
父は静かな人で、大きな声を出すということはなく、また大きな声で笑うこともなかった。
とても背が高く、本人に確かめたことはなかったが、母が言うには185センチもあったそうだ。
母は、150センチそこそこの小柄。
二人が歩くと、その身長差に人目を引き、気恥ずかしかったそうで、
母は、そんな父との話をするとき、わざと顔をしかめていた。
父は、首をちょっと前加減に出し、背中を丸めて歩く癖があった。
若い頃は野球やテニスをしたそうで、水泳も得意だった。
細身の体型で長い脚と腕をしていた。
手の指も長く器用で、大きなカメラを扱うにはちょうど良かったろう。
私は父のその手を受け継いでいる。
細長い指や、平たい爪の形や、母に言わせるとふとした手の動かし方まで似ているらしい。
「女の私より綺麗な手だった。」
と母は父の話をするとき、よく口にした。
私は父が好きだった。
父は小さな私を連れてよく出かけてくれた。
散歩はもとより、デパート、映画、海、遊園地など、誰かに「ここは行ってよかった」と聞けば、すぐに私を連れて行こうと予定を立てたそうだ。
背の高い父は、私の手を引いて歩くことはあまりなかった。
小さな私の手を引いて歩くには、父は背が高すぎた。
一度、横浜駅の西口の人混みで、私は危うく迷子になりかけたことがあった。
あれは幾つのときだったのだろう。
6歳にはなっていなかったのではないかと思う。
いつものように父のズボンの端を握っていた私の手が、知らないうちに離れてしまったのだ。
ところが、父は私に気付かずに歩いていってしまった。
決して早い歩き方ではなかったのだが、コンパスのある父は、みるみる私から遠くなってしまった。
一瞬、私は父を完全に見失った。
たくさんの大人の背中、大人の腕、そして大人の靴。
どれもが黒や灰色で、私は突然、真っ暗な万華鏡のなかに、たったひとりで立たされているかのように、頭がぐらぐらしたのを憶えている。
私の目は父を捜した。
人混みに視界を遮られ、遠くはわずかに一瞬見えるだけだった。
瞬きするのも怖かった。
今ならば、身長が180センチほどの人なら街にざらにみかける。
けれど、幸い当時はまだ少なく、かなり目立つ存在だった父は、他の人々から頭一つ飛び出ていた。
私は、僅かな隙間に、父の肩と、横顔を見つけた。
全速力で、といっても親鳥のあとを追うヒヨコみたいだったろうが、とにかく必死になって走ったことを憶えている。
私は人混みに飛び出た父の頭を目指して走った。
「お父さん!」と叫べばよかったのだろうが、私はそうはしなかった。
私はそういう子供だった。
ただ、ひたすら父を見失わないように、眼をみひらいて走った。
結局、私は父のズボンに再びしがみつくことが出来た。
ズボンを引っ張られたことに気付いた父は、私を眠そうな笑顔で見下ろした。
息を弾ませながら父を見上げた私も、にっこり父に笑い返した。
ずっとあとになって、私が父にそのときの話をすると、父は「そんなことあったのかぁ?」とのんびり言っただけだった。
父には、そんなふうなところがあった。
アルバムをひらくと、1ページめに私の写真が貼られている。
私は薄い髪の毛を頭のてっぺんでチョンチョリンに結び、哺乳瓶を抱えている。
籐で作られたゆりかごの中で私はぼんやりとした顔をしている。
写真の横には、父の字で「おっぱい、リボンがすてき」と書かれている。
父の書く文字は、筆圧がゆるく、その体型に似てほっそりとしている。
父がいなくなった今、そんな父の書いた文字も懐かしい。
その下に貼られた写真は、風呂上りなのだろうか。
裸の私は水玉模様のタオルに包まれ母に抱っこされている。
「早くおべべ着せてよ。あんまり見ないでね」と書いてある。
私を抱いている母の若いこと。
花柄の半袖ブラウスにショートの髪がかわいい。
畳の上には象のぬいぐるみやガラガラなどのおもちゃが散らばっている。後ろの襖は、竹の柄が描かれている。
父は私が生まれる少し前に家を建てた。
横浜の郊外に住んでいた母の実家の道ひとつ隔てた向かいに、35坪ほどの土地を借りて建てたのだ。
その家は、今で言う2DKで、南に2畳ほどの縁側のついた平屋だった。
三十そこそこの父が始めて建てた家だった。
その後、この家は少しずつ増改築された。
このアルバムのなかにおさめられている竹の柄の襖も縁側も、今はもうない。
父は私を肩車して、よく一緒に散歩してくれた。
近くにある小高い丘からから、父といっしょに自分たちが住むその家を見おろすことが好きだった。
赤い屋根の小さなその家は、周りを畑と田んぼに囲まれ、
春にはタンポポの黄色い帯が家をぐるりと縁取った。
夏には、緑の稲が海のように波打ち、渡る風が見えた。
そして、秋には、スズメが黒雲のように群れをなして低く飛び、
冬の朝には、霜で白くなった田んぼが、和紙を敷き詰めたように広がっていた。
あの家は、まるで子供の頃に読んだ絵本の1ページのように
私の記憶のなかに色鮮やかに残っている。
ふと振り向けば、そこにそのままある世界のように。
しかし、このアルバムに残る写真には、色は無く、少しセピアがかっていて、そこで笑っている私も、両親も、止まったままの世界の中にいる。
写真を撮る役回りだった父と一緒に写っている写真は少ない。
それでも数枚張ってある。
母はカメラなどいじれる人ではないから、どこかにカメラを固定してセルフタイマーで撮ったのだろう。
父はゆりかごで眠る私に自分の顔を寄せてこちらを見ている。
シャッターが切れるまでじっとそのかっこうをしていたのだろう。
父の額には何本も深い皺がよっている。
余白に「おとうちゃんと」と書いてある。
どの写真も若い夫婦の初めての子供に対する喜びが伝わってくる。
ここに写っている若い夫婦が自分の両親で、その腕に抱かれている赤ん坊が自分自身であると言うことが、とても不思議に感じられる。
私の着ている産着は小花模様だったり、犬の柄だったり、同じ服が何度も出てくることは少ない。
色のついていないその写真をじっと見ていると、私には自分が着せられていた服の色が見えてくる。
父の給料は、私の産着やおもちゃに消えていったのだろう。
私は多くの愛情を注がれて育ったのだ。
写真のなかの私の顔は、どの顔も安心しきった表情をしている。
しかし、ページをめくっていくと、私にとって見たくはない、けれど見なければならなかった1枚の写真に突き当たる。
それは生後三ヶ月の私だ。
私にはこのときの記憶はもちろん無い。
しかし、このたった一枚の写真が、あの時、私に何が起きたのかを、否応無しに語っている。
生まれて僅か3ヶ月で、私は自分の人生に一生付きまとう荷を背負った。どうして父はこんな写真を撮ったのだろう。
この写真を見るたびに、私はこの疑問を反復した。
どうして父は、この写真を撮ったのだろう・・・。
しかし、とうとう父にこのことを訊くことはなかった。
何故私は父に尋ねなかったのだろう。
結局、私たちはこの一枚の写真について、一度も語り合うことがないままになってしまった。
その写真のなかに写る私は、父が手作りした乳母車に乗っている。
生後3ヶ月の検診で、私は股関節脱臼と診断された。
両脚の大腿骨の発育が悪く、脱臼と言うよりは、骨頭がつぶれていたのだ。
特に左脚はひどかった。
それで当時の治療としては私の両脚は蛙のように開いた格好で何ヶ月も石膏で固められることとなったらしい。
それで当然、市販の乳母車には乗れず、日曜大工が得意だった父が私のために特製の乳母車を作ったのだ。
私の開いた脚の形に合わせ、底が平らで手前には小さなテーブルがついている。
座っている私は無表情だ。
痛そうでもなく、つらそうでもなく、無表情だ。
ただ、父の構えるカメラのレンズだけを見つめている。
石膏で固めた両脚は、どうやって産着を着せたのかと思うほど、ごつごつに膨らんでいる。
両脚を左右に開き、足首から先だけがだらりと垂れている。
父は、真正面から私を撮影しているのだ。
「早くあんよがしたいよ」
そう書いてある。
私がギプスをはめられていた時の写真はこれ1枚きりだ。
父は私がギプスをはめられていた数ヶ月間、たった一枚だけ写真を撮った。
父はこのときどんな気持ちでシャッターを切ったのか・・・。
こののち、父はしばらく写真を撮らなかったようだ。
この写真の次に貼られているのは、もうギプスが外れ、ヒキガエルのようにひろがった脚で掴まり立ちしている私になっている。
あの乳母車に両手をかけ、二本の脚で立っている私の姿。
私はこちらを見上げている。
父を見上げているのだ。
あの写真から、この日まで、何ヶ月あったのだろう。
その写真のすぐ下には、私が砂利道の中央を、オムツが丸見えで歩いている写真が貼ってある。
両腕を左右に大きく振っている。
ひらひらした大きなリボンが付いた靴を履いている。
立て続けに、私が立ったり歩いたりしている写真が続く。
そして、それまで家の中や近所の風景の中だけにいた私は、しばらくすると、私自身の記憶の中からすでに消えてしまった背景の中に登場する。
父はあちこち私を連れ出したようだ。
鎌倉の大仏の前に座っている私がいる。
髪をショートにして花飾りのついた帽子をかぶり、半袖のワンピースを着ている。
膝小僧をちゃんとそろえている。
砂浜で一人座っている私。右手におにぎりを持っている。
大仏で写っていた服装を同じだから、由比ガ浜辺りだろう。
あの頃の私が大仏から由比ガ浜まで歩けたわけはないから、たぶん父は私を肩車して連れて行ったに違いない。
背の高い父がしてくれる肩車は私の一番のお気に入りだった。
私がせがんだのかもしれない。
まだ海水浴には早い時期だったのか、ずっと遠くの砂浜まで他に誰も写っていない。
そばに水筒と父のショルダーバックが無ければ、まるで私は一人ぼっちで置き去りにされたように見える。
父は、レンズの向こうから、少しおませになった娘を見つめていたのだろうか。
カメラは少し引き加減で私を捕らえている。
石膏で固められていた間の記憶は、私には当然ない。
生後3か月の赤ん坊だったからこそ、否応なしに我慢できたのかもしれない。
歩けるようになった私の表情は、どれも明るい笑顔がいっぱいだ。
しかし、私は成長と共に自分の足の欠陥を認識していった。
治療後も脚の状態が良くなかったため幼稚園には行かれず、その後も治療は続き、結局小学校も一年遅れることになった。
いきなり集団生活に入れられたときのことはよく憶えている。
普通の子供が知っている遊びを私は知らなかった。
「ハンカチ落とし」に初めて参加したとき、ハンカチを拾わずに、私は鬼を追いかけた。ゆっくり歩きながら。
最も走りたい、飛び回りたい時期に私にはそれが許されなかった。
「決して走ってはいけません。決して跳んではいけません。」
母は私に厳しく言った。
母にしてみれば、「やっと、ここまで良くなった」という思いだったのだろう。
体育の授業は見学。一つ年上であることはクラスのみんなが知っていた。
「一年遅れっ子」と呼ばれた。
見た目には何の違いも無さそうな私の脚は、父に似て細く長く、
走ればきっと誰よりも速く走れるに決まっている、私はそう思っていた。空想の世界で、私は広い校庭を、いつも先頭を切って走っていた。
その頃から、私は自分の赤ん坊の頃の写真がおさめられているこのアルバムをこっそり見るようになった。
なにもこっそり見なければいけない理由はどこにもなかったが、
それでも私は、母が夕食の仕度をしているときなどを選んで、このアルバムをひらいた。
和室に置かれた父専用の洋服ダンスの扉をひらき、ハンガーにかかる背広をかきわけると、薄暗い影の中にそのアルバムは、カメラと共に置かれていた。
あのときのドキドキした思いは今も憶えている。
私が見たかったのは、ただ一枚である。
あの、石膏で固められた、醜い脚の写った一枚だった。
私はどうしてもそこに写っているのが自分自身だと認めたくなかった。
と同時にこれは自分なのだということを確実に知っていた私は、
この写真を見ることがとても怖かった。
それでも私はあの時、この写真を見ずにはいられなかったのだ。
一度、思いがけず早めに帰ってきた父に、見つかってしまったことがあった。
振り返ると、父が茶の間の明かりを背にして立っていた。
父はなにも言わず、着ていた背広を脱ぎ、それを掛けると、「撮ってやろう」と言って、奥にあるカメラを持ち出した。
私はぞんざいな言い方で「いいよ」と言って逃げ出した。
その後、何度もその写真を見るにつれ、私の人格のなかでこの写真の中の私は、もう一人の私になっていった。
私は写真の私に話しかける。まるで姉妹のように。
「なんでこんな脚なの?」
「わからない。」
「やりたいこと、ぜんぜんできないわよ」
「でも歩けてる。できないことばかり言わないでよ。」
私は写真を睨みつけた。そして私は乗り越えてきた。
大学は美術を専攻した。
運動ができない私に母が3歳から習わせた絵が、結局そのまま続いたのだ。
特別絵を描くことが好きだったわけではなかったが、やりたいスポーツができない分、私は絵に集中した。
私が大人になるに連れて、私と父は一緒に出かけることも少なくなっていった。
時々父は私を誘ったが、私はいつも何か理由をつけて断った。
父が私の写真を撮ることも少なくなっていった。
父が嫌いになったわけではなかった。
だんだん歳をとっていく父に気付き、それを感じるのが嫌だった。
私にとって父はいつまでもあの頃の父のままでいてほしかった。
あの頃とは、私を肩車してくれたあの頃だった。
父の死は突然訪れた。
電話が鳴った。
数日来、胸の痛みを感じていた父は、その日検査のため一人で病院へ行った。
会社には午後から出ると電話していたそうだ。
その検査の最中に発作を起こしたのだ。
私と母が駆けつけたときには、医師が心臓マッサージをしていた。
ベッドに横たわる父のあの長い腕と脚は、医師の施すマッサージの弾みでゆさゆさと揺れていた。
急性心不全だった。
私と母は一言の言葉も出すことができなかった。
父が私を最後に写真に撮ったのは、亡くなる数ヶ月前だった。
父と母と3人で昼の食事をしていると、窓の外から大きな野良猫が部屋の中をのぞいていた。
「お、このあたりのボスだ。」
そう言って父はカメラを持ち出し外へ出た。
「撮ってやるよ」
父に促されて、私も庭へ下りた。
猫は人馴れしていて、私の腕のなかでじっとしていた。
小さな庭で取られたこの写真の中で、私は柔らかな猫を抱き白い歯を見せて笑っている。
父の撮る写真のなかで、私はいつまでも子供のようだ。
何事につけ事細かに物を言う母にくらべ、父はほとんど何も言わない人だったが、今、こうして父の作ったアルバムをひらくと、そこにはたくさんの父の言葉が詰まっているように思われる。
私がギプスをはめていたあのとき、父は一枚だけ、あの私を写真に残した。
たった一枚しか撮られることのなかったその空白が、何より、父の思いを語っているのだ。
私の生きてきた道をたどっていくと、あの1枚にたどり着く。
私が足踏みをしているときなど、ぽんと背中をたたいて、私に勇気を与えてくれたような気がする。
父はあの写真が私にとって、無くてはならないものになることを知っていたのだろうか。
晩年、父は友人とよく山へ登った。
父の遺影はそのときに撮られたものだ。
それがどこの山なのか、誰が撮ってくれたものなのか、母にも私にもわからなかった。
山登りの写真の束は、紙の手提げ袋に無造作につめこまれていて、まったく整理されないまま、父の洋服ダンスの奥に置かれていた。
父は自分の写った写真はアルバムに収めなかったのだ。
葬儀のあわただしい準備の中、母と私は、ばらばらの写真を畳の上にひろげ、その中から遺影となる写真を選んだ。
額縁に入った父の顔は穏やかに微笑んでいる。
きっと、山頂に登ったときに撮ったものだろう。
父の目は空を見上げている。
だから、私が仏壇の前で父に手を合わせるとき、父の顔を見ても、写真の中の父とは目が合わない。
照れ屋の父らしい。
カメラは父の形見として私のもとにきた。そして今、1冊目のアルバムと共に私の箪笥の引き出しの中にある。
今でも時々、私はあの写真を見るためにアルバムをひらく。
カメラを取り出し、構えてみる。
父は幾度となく、このファインダーの中に、私を見たのだ。
結局、私がこのカメラを父に向けてシャッターを切ることはなかった。
父の死後このカメラは、一枚の写真も撮ってはいない。
私の箪笥の引出しには、お気に入りのブラウスと一緒に、父のペンタックスと一冊の古いアルバムが入っている。
父は、このカメラで家族の写真を撮り、アルバムに残した。
私には、カメラの値打ちはわからない。
けれど、日曜日の午後など、ネルの布でレンズの手入れをしている、あぐらをかいた前かがみの父の背中は憶えている。
父はこのカメラを私が生まれてすぐに買ったようだ。
なぜなら、父が残したこのアルバムは、生まれて間もない赤ん坊の私の寝顔から始まるからだ。
おそらく父はこのカメラを、そうとうに無理をして買ったのだろう。
このカメラは、父の宝物だった。
私など、持ち上げて眼の高さに構えるだけでも、腕がふら付くような重みがあり、ピントを合わせるにも一苦労しそうな代物だ。
父はこのカメラで撮った写真の一枚一枚を、何冊ものアルバムに収めた。そして、そのアルバムは、家族の宝物となった。
父は自分の宝物で宝物を作って、私たちに残していったのだ。
そしてそのアルバムの最初の一冊が、父のカメラと共に、今、私の手元にある。
幾度かの引越しのときも、私は自分のバックに入れて運び、荷造りのダンボールにしまうことはなかった。
この一冊めのアルバムは、そのほとんどが私の乳幼児期の写真で埋まっている。
古さの染み込んだ赤い布張りのアルバムは、ページを開くと、なぜか、ラムネの香りがする。
淡い色合いの儚い甘い香りだ。
私が一番好きな写真は、父と二人で撮られた一枚である。
私はまだ、オムツをあてている歳で、やっと、よちよち歩き出した頃だろう。
父は大きく脚を広げて立っている。
その二本の脚の間にしゃがんで、私はよだれを垂らさんばかりにカメラに向かって笑っている。
おませにも私はベレー帽をかぶっている。
私の小さな両手は、両側に突っ立っている父のズボンを握っている。
ちょうど脛のあたりを握っているのだ。
つまり写っているのは、私と、膝から下の、父の黒いズボンを履いた二本の脚だけなのだ。
このモノクロの写真が、いつ何処で撮られたのか、誰が撮ってくれたものなのか、父がいない今となっては、もう知ることはできない。
脚しか写っていない父は、そのとき、どんな顔をして私を見下ろしていたのだろう。
そう考えるとき、私は小さな幼子に戻って、上を見上げている自分に気付く。
けれど、私の視線の先に、私をのぞき込む父の顔はない。
父は静かな人で、大きな声を出すということはなく、また大きな声で笑うこともなかった。
とても背が高く、本人に確かめたことはなかったが、母が言うには185センチもあったそうだ。
母は、150センチそこそこの小柄。
二人が歩くと、その身長差に人目を引き、気恥ずかしかったそうで、
母は、そんな父との話をするとき、わざと顔をしかめていた。
父は、首をちょっと前加減に出し、背中を丸めて歩く癖があった。
若い頃は野球やテニスをしたそうで、水泳も得意だった。
細身の体型で長い脚と腕をしていた。
手の指も長く器用で、大きなカメラを扱うにはちょうど良かったろう。
私は父のその手を受け継いでいる。
細長い指や、平たい爪の形や、母に言わせるとふとした手の動かし方まで似ているらしい。
「女の私より綺麗な手だった。」
と母は父の話をするとき、よく口にした。
私は父が好きだった。
父は小さな私を連れてよく出かけてくれた。
散歩はもとより、デパート、映画、海、遊園地など、誰かに「ここは行ってよかった」と聞けば、すぐに私を連れて行こうと予定を立てたそうだ。
背の高い父は、私の手を引いて歩くことはあまりなかった。
小さな私の手を引いて歩くには、父は背が高すぎた。
一度、横浜駅の西口の人混みで、私は危うく迷子になりかけたことがあった。
あれは幾つのときだったのだろう。
6歳にはなっていなかったのではないかと思う。
いつものように父のズボンの端を握っていた私の手が、知らないうちに離れてしまったのだ。
ところが、父は私に気付かずに歩いていってしまった。
決して早い歩き方ではなかったのだが、コンパスのある父は、みるみる私から遠くなってしまった。
一瞬、私は父を完全に見失った。
たくさんの大人の背中、大人の腕、そして大人の靴。
どれもが黒や灰色で、私は突然、真っ暗な万華鏡のなかに、たったひとりで立たされているかのように、頭がぐらぐらしたのを憶えている。
私の目は父を捜した。
人混みに視界を遮られ、遠くはわずかに一瞬見えるだけだった。
瞬きするのも怖かった。
今ならば、身長が180センチほどの人なら街にざらにみかける。
けれど、幸い当時はまだ少なく、かなり目立つ存在だった父は、他の人々から頭一つ飛び出ていた。
私は、僅かな隙間に、父の肩と、横顔を見つけた。
全速力で、といっても親鳥のあとを追うヒヨコみたいだったろうが、とにかく必死になって走ったことを憶えている。
私は人混みに飛び出た父の頭を目指して走った。
「お父さん!」と叫べばよかったのだろうが、私はそうはしなかった。
私はそういう子供だった。
ただ、ひたすら父を見失わないように、眼をみひらいて走った。
結局、私は父のズボンに再びしがみつくことが出来た。
ズボンを引っ張られたことに気付いた父は、私を眠そうな笑顔で見下ろした。
息を弾ませながら父を見上げた私も、にっこり父に笑い返した。
ずっとあとになって、私が父にそのときの話をすると、父は「そんなことあったのかぁ?」とのんびり言っただけだった。
父には、そんなふうなところがあった。
アルバムをひらくと、1ページめに私の写真が貼られている。
私は薄い髪の毛を頭のてっぺんでチョンチョリンに結び、哺乳瓶を抱えている。
籐で作られたゆりかごの中で私はぼんやりとした顔をしている。
写真の横には、父の字で「おっぱい、リボンがすてき」と書かれている。
父の書く文字は、筆圧がゆるく、その体型に似てほっそりとしている。
父がいなくなった今、そんな父の書いた文字も懐かしい。
その下に貼られた写真は、風呂上りなのだろうか。
裸の私は水玉模様のタオルに包まれ母に抱っこされている。
「早くおべべ着せてよ。あんまり見ないでね」と書いてある。
私を抱いている母の若いこと。
花柄の半袖ブラウスにショートの髪がかわいい。
畳の上には象のぬいぐるみやガラガラなどのおもちゃが散らばっている。後ろの襖は、竹の柄が描かれている。
父は私が生まれる少し前に家を建てた。
横浜の郊外に住んでいた母の実家の道ひとつ隔てた向かいに、35坪ほどの土地を借りて建てたのだ。
その家は、今で言う2DKで、南に2畳ほどの縁側のついた平屋だった。
三十そこそこの父が始めて建てた家だった。
その後、この家は少しずつ増改築された。
このアルバムのなかにおさめられている竹の柄の襖も縁側も、今はもうない。
父は私を肩車して、よく一緒に散歩してくれた。
近くにある小高い丘からから、父といっしょに自分たちが住むその家を見おろすことが好きだった。
赤い屋根の小さなその家は、周りを畑と田んぼに囲まれ、
春にはタンポポの黄色い帯が家をぐるりと縁取った。
夏には、緑の稲が海のように波打ち、渡る風が見えた。
そして、秋には、スズメが黒雲のように群れをなして低く飛び、
冬の朝には、霜で白くなった田んぼが、和紙を敷き詰めたように広がっていた。
あの家は、まるで子供の頃に読んだ絵本の1ページのように
私の記憶のなかに色鮮やかに残っている。
ふと振り向けば、そこにそのままある世界のように。
しかし、このアルバムに残る写真には、色は無く、少しセピアがかっていて、そこで笑っている私も、両親も、止まったままの世界の中にいる。
写真を撮る役回りだった父と一緒に写っている写真は少ない。
それでも数枚張ってある。
母はカメラなどいじれる人ではないから、どこかにカメラを固定してセルフタイマーで撮ったのだろう。
父はゆりかごで眠る私に自分の顔を寄せてこちらを見ている。
シャッターが切れるまでじっとそのかっこうをしていたのだろう。
父の額には何本も深い皺がよっている。
余白に「おとうちゃんと」と書いてある。
どの写真も若い夫婦の初めての子供に対する喜びが伝わってくる。
ここに写っている若い夫婦が自分の両親で、その腕に抱かれている赤ん坊が自分自身であると言うことが、とても不思議に感じられる。
私の着ている産着は小花模様だったり、犬の柄だったり、同じ服が何度も出てくることは少ない。
色のついていないその写真をじっと見ていると、私には自分が着せられていた服の色が見えてくる。
父の給料は、私の産着やおもちゃに消えていったのだろう。
私は多くの愛情を注がれて育ったのだ。
写真のなかの私の顔は、どの顔も安心しきった表情をしている。
しかし、ページをめくっていくと、私にとって見たくはない、けれど見なければならなかった1枚の写真に突き当たる。
それは生後三ヶ月の私だ。
私にはこのときの記憶はもちろん無い。
しかし、このたった一枚の写真が、あの時、私に何が起きたのかを、否応無しに語っている。
生まれて僅か3ヶ月で、私は自分の人生に一生付きまとう荷を背負った。どうして父はこんな写真を撮ったのだろう。
この写真を見るたびに、私はこの疑問を反復した。
どうして父は、この写真を撮ったのだろう・・・。
しかし、とうとう父にこのことを訊くことはなかった。
何故私は父に尋ねなかったのだろう。
結局、私たちはこの一枚の写真について、一度も語り合うことがないままになってしまった。
その写真のなかに写る私は、父が手作りした乳母車に乗っている。
生後3ヶ月の検診で、私は股関節脱臼と診断された。
両脚の大腿骨の発育が悪く、脱臼と言うよりは、骨頭がつぶれていたのだ。
特に左脚はひどかった。
それで当時の治療としては私の両脚は蛙のように開いた格好で何ヶ月も石膏で固められることとなったらしい。
それで当然、市販の乳母車には乗れず、日曜大工が得意だった父が私のために特製の乳母車を作ったのだ。
私の開いた脚の形に合わせ、底が平らで手前には小さなテーブルがついている。
座っている私は無表情だ。
痛そうでもなく、つらそうでもなく、無表情だ。
ただ、父の構えるカメラのレンズだけを見つめている。
石膏で固めた両脚は、どうやって産着を着せたのかと思うほど、ごつごつに膨らんでいる。
両脚を左右に開き、足首から先だけがだらりと垂れている。
父は、真正面から私を撮影しているのだ。
「早くあんよがしたいよ」
そう書いてある。
私がギプスをはめられていた時の写真はこれ1枚きりだ。
父は私がギプスをはめられていた数ヶ月間、たった一枚だけ写真を撮った。
父はこのときどんな気持ちでシャッターを切ったのか・・・。
こののち、父はしばらく写真を撮らなかったようだ。
この写真の次に貼られているのは、もうギプスが外れ、ヒキガエルのようにひろがった脚で掴まり立ちしている私になっている。
あの乳母車に両手をかけ、二本の脚で立っている私の姿。
私はこちらを見上げている。
父を見上げているのだ。
あの写真から、この日まで、何ヶ月あったのだろう。
その写真のすぐ下には、私が砂利道の中央を、オムツが丸見えで歩いている写真が貼ってある。
両腕を左右に大きく振っている。
ひらひらした大きなリボンが付いた靴を履いている。
立て続けに、私が立ったり歩いたりしている写真が続く。
そして、それまで家の中や近所の風景の中だけにいた私は、しばらくすると、私自身の記憶の中からすでに消えてしまった背景の中に登場する。
父はあちこち私を連れ出したようだ。
鎌倉の大仏の前に座っている私がいる。
髪をショートにして花飾りのついた帽子をかぶり、半袖のワンピースを着ている。
膝小僧をちゃんとそろえている。
砂浜で一人座っている私。右手におにぎりを持っている。
大仏で写っていた服装を同じだから、由比ガ浜辺りだろう。
あの頃の私が大仏から由比ガ浜まで歩けたわけはないから、たぶん父は私を肩車して連れて行ったに違いない。
背の高い父がしてくれる肩車は私の一番のお気に入りだった。
私がせがんだのかもしれない。
まだ海水浴には早い時期だったのか、ずっと遠くの砂浜まで他に誰も写っていない。
そばに水筒と父のショルダーバックが無ければ、まるで私は一人ぼっちで置き去りにされたように見える。
父は、レンズの向こうから、少しおませになった娘を見つめていたのだろうか。
カメラは少し引き加減で私を捕らえている。
石膏で固められていた間の記憶は、私には当然ない。
生後3か月の赤ん坊だったからこそ、否応なしに我慢できたのかもしれない。
歩けるようになった私の表情は、どれも明るい笑顔がいっぱいだ。
しかし、私は成長と共に自分の足の欠陥を認識していった。
治療後も脚の状態が良くなかったため幼稚園には行かれず、その後も治療は続き、結局小学校も一年遅れることになった。
いきなり集団生活に入れられたときのことはよく憶えている。
普通の子供が知っている遊びを私は知らなかった。
「ハンカチ落とし」に初めて参加したとき、ハンカチを拾わずに、私は鬼を追いかけた。ゆっくり歩きながら。
最も走りたい、飛び回りたい時期に私にはそれが許されなかった。
「決して走ってはいけません。決して跳んではいけません。」
母は私に厳しく言った。
母にしてみれば、「やっと、ここまで良くなった」という思いだったのだろう。
体育の授業は見学。一つ年上であることはクラスのみんなが知っていた。
「一年遅れっ子」と呼ばれた。
見た目には何の違いも無さそうな私の脚は、父に似て細く長く、
走ればきっと誰よりも速く走れるに決まっている、私はそう思っていた。空想の世界で、私は広い校庭を、いつも先頭を切って走っていた。
その頃から、私は自分の赤ん坊の頃の写真がおさめられているこのアルバムをこっそり見るようになった。
なにもこっそり見なければいけない理由はどこにもなかったが、
それでも私は、母が夕食の仕度をしているときなどを選んで、このアルバムをひらいた。
和室に置かれた父専用の洋服ダンスの扉をひらき、ハンガーにかかる背広をかきわけると、薄暗い影の中にそのアルバムは、カメラと共に置かれていた。
あのときのドキドキした思いは今も憶えている。
私が見たかったのは、ただ一枚である。
あの、石膏で固められた、醜い脚の写った一枚だった。
私はどうしてもそこに写っているのが自分自身だと認めたくなかった。
と同時にこれは自分なのだということを確実に知っていた私は、
この写真を見ることがとても怖かった。
それでも私はあの時、この写真を見ずにはいられなかったのだ。
一度、思いがけず早めに帰ってきた父に、見つかってしまったことがあった。
振り返ると、父が茶の間の明かりを背にして立っていた。
父はなにも言わず、着ていた背広を脱ぎ、それを掛けると、「撮ってやろう」と言って、奥にあるカメラを持ち出した。
私はぞんざいな言い方で「いいよ」と言って逃げ出した。
その後、何度もその写真を見るにつれ、私の人格のなかでこの写真の中の私は、もう一人の私になっていった。
私は写真の私に話しかける。まるで姉妹のように。
「なんでこんな脚なの?」
「わからない。」
「やりたいこと、ぜんぜんできないわよ」
「でも歩けてる。できないことばかり言わないでよ。」
私は写真を睨みつけた。そして私は乗り越えてきた。
大学は美術を専攻した。
運動ができない私に母が3歳から習わせた絵が、結局そのまま続いたのだ。
特別絵を描くことが好きだったわけではなかったが、やりたいスポーツができない分、私は絵に集中した。
私が大人になるに連れて、私と父は一緒に出かけることも少なくなっていった。
時々父は私を誘ったが、私はいつも何か理由をつけて断った。
父が私の写真を撮ることも少なくなっていった。
父が嫌いになったわけではなかった。
だんだん歳をとっていく父に気付き、それを感じるのが嫌だった。
私にとって父はいつまでもあの頃の父のままでいてほしかった。
あの頃とは、私を肩車してくれたあの頃だった。
父の死は突然訪れた。
電話が鳴った。
数日来、胸の痛みを感じていた父は、その日検査のため一人で病院へ行った。
会社には午後から出ると電話していたそうだ。
その検査の最中に発作を起こしたのだ。
私と母が駆けつけたときには、医師が心臓マッサージをしていた。
ベッドに横たわる父のあの長い腕と脚は、医師の施すマッサージの弾みでゆさゆさと揺れていた。
急性心不全だった。
私と母は一言の言葉も出すことができなかった。
父が私を最後に写真に撮ったのは、亡くなる数ヶ月前だった。
父と母と3人で昼の食事をしていると、窓の外から大きな野良猫が部屋の中をのぞいていた。
「お、このあたりのボスだ。」
そう言って父はカメラを持ち出し外へ出た。
「撮ってやるよ」
父に促されて、私も庭へ下りた。
猫は人馴れしていて、私の腕のなかでじっとしていた。
小さな庭で取られたこの写真の中で、私は柔らかな猫を抱き白い歯を見せて笑っている。
父の撮る写真のなかで、私はいつまでも子供のようだ。
何事につけ事細かに物を言う母にくらべ、父はほとんど何も言わない人だったが、今、こうして父の作ったアルバムをひらくと、そこにはたくさんの父の言葉が詰まっているように思われる。
私がギプスをはめていたあのとき、父は一枚だけ、あの私を写真に残した。
たった一枚しか撮られることのなかったその空白が、何より、父の思いを語っているのだ。
私の生きてきた道をたどっていくと、あの1枚にたどり着く。
私が足踏みをしているときなど、ぽんと背中をたたいて、私に勇気を与えてくれたような気がする。
父はあの写真が私にとって、無くてはならないものになることを知っていたのだろうか。
晩年、父は友人とよく山へ登った。
父の遺影はそのときに撮られたものだ。
それがどこの山なのか、誰が撮ってくれたものなのか、母にも私にもわからなかった。
山登りの写真の束は、紙の手提げ袋に無造作につめこまれていて、まったく整理されないまま、父の洋服ダンスの奥に置かれていた。
父は自分の写った写真はアルバムに収めなかったのだ。
葬儀のあわただしい準備の中、母と私は、ばらばらの写真を畳の上にひろげ、その中から遺影となる写真を選んだ。
額縁に入った父の顔は穏やかに微笑んでいる。
きっと、山頂に登ったときに撮ったものだろう。
父の目は空を見上げている。
だから、私が仏壇の前で父に手を合わせるとき、父の顔を見ても、写真の中の父とは目が合わない。
照れ屋の父らしい。
カメラは父の形見として私のもとにきた。そして今、1冊目のアルバムと共に私の箪笥の引き出しの中にある。
今でも時々、私はあの写真を見るためにアルバムをひらく。
カメラを取り出し、構えてみる。
父は幾度となく、このファインダーの中に、私を見たのだ。
結局、私がこのカメラを父に向けてシャッターを切ることはなかった。
父の死後このカメラは、一枚の写真も撮ってはいない。