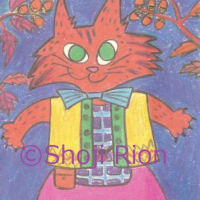あぁ、三日月が出ている。
東の夜空の高いところに、羽毛で織ったような雲がかかっている。
その雲の切れ間にいる三日月。
歳を重ね、近視と乱視の私の目には、幾つもの三日月が手裏剣の軌跡のように見える。
桜の便りが聞こえてくるこの季節の夜空は、ほんのり薄紅がかって美しい。
そんな、まったりした夜空には、銅鏡のように輝く満月もいいけれど、刃物のように鋭利に堅く光る三日月のほうが私は好きだ。
子供の頃は、この三日月を見ると、夜空がニッと笑っているように思えたものだ。
スマイルマークのあの口。
いや、ピエロのように泣き笑いしている口だったか。
あの口に梯子をかけて上まで行けたら、と想像したことがある。
満月よりは引っかけやすそうに思えて、上に登れば、月の魔力でどこまでもどこまでも先の先まで見渡せると思えた。
知らないところ、行ったことのないところを見たかった。
いつか、その知らないところ、行ったことのないところを目指して、へとへとに疲れるまで歩いて行けば、銀河鉄道に乗って行ったあのカンパネルラが、もう一つの三日月を背にして武将のように道の真ん中に立っている。私は、私の三日月を背にして、ギラギラと笑いながらカンパネルラの前に立つ。
そう想像するとわくわくした。
そう、確かにいつかは、誰しもカンパネルラに出会う道を行くことになるのだろうけれど・・・。
笑っている。夜空が笑っている。
一年のうちでも、この桜の時期が、その笑みが一番穏やかに感じられる。
子供の頃の思い出がある。
やはり桜の季節だった。
私は小学生に上がったばかりの年だったろう。
祖父母と3人でお風呂屋さんへ行った帰り道のこと。
桜の花に隠れながら、三日月は、私たちのあとを付いてきていた。
風呂屋の煙突にぶつかっても、音もしない。
藍色の夜空にレモンの果汁が一滴すべったように、瑞々しい輝きを放っていた。
「なに上ばかり見てるの? 転びますよ」
祖母は振り返り、すぐにまた、洗面器に入った石鹸箱の音をカタカタさせながら、砂利道を足早に歩いて行こうとする。
祖父のほうは、もうだいぶ先を歩いていて、道の角を曲がって行く後ろ姿が見えた。せっかちな祖父は、足も速い。
「早くしなさい。行っちゃうよ」
「ばあばあ、あのね、お月さん、私の手が届きそう。」
私は歩きながら両手を夜空に向かって伸ばした。
両手10本の指の間で、ころころ三日月が転がっている。
祖母は足をとめて振り返り、空を見上げた。
「あぁ、お月さん、見てたんだね」
「ずっと付いてきてるの。いつも、そう思うの」
祖母は、ふうと息を吐き、祖母と同時に歩みを止めた祖母の月を見上げた。
しばらくして祖母は
「届きそうだね」
そう言って、右手をパッとひろげ、甲虫でも取るように素早く空を切った。
握った手の平を、そっと開き、
「あれ? 取れなかった」
祖母は私の顔を見てわざと残念そうに言った。
「ねぇ、ばあばあ、お月さん、今日は笑ってるよね」
「そうだね。あれは笑っているんだろうね。」
「ね、笑っているでしょ」
「ばあばぁが子供のときも、笑ってたよ。大人になってからも、ずっと笑っているねぇ。」
「どうして笑っているの?」
「そりゃぁ・・・」
言いかけて、祖母は私の顔をじっと見た。
「面白いからねぇ。人間は面白いからね」
「お月さまは人間を見てるの?」
「そう。お月さんはね、人間を見てるのよ。」
「私のことも? 見てる?」
「そうでしょうよ。おチエさんも面白いから、ねぇ」
祖父母は私の名前に「お」を付けて呼んだ。
他の孫にはそういう呼び方はしなかった。
私だけ、名前に「お」を付け、「さん」も付けて「おチエさん」と呼んだ。
祖母の家と私の家は、道をはさんで向かい合わせに住んでいた。
私たちは、ほぼ毎日顔を合わせ、毎日なんらかの時間を一緒に過ごしていた。
私は、祖母と共に過ごす時間が多かった。
実の母親ということもあって、気兼ねがなかったのだろう。
母は、祖母の家に行ったまま、何時間も帰ってこない私を怒ることはなかった。
祖母は、本を読んだり、あや取りを教えてくれた。
「私のことが面白いのかな?」
「おチエさんだけじゃなくて、人間みんなを見てるのよ。ずっとねぇ、昔から。ばあばあも、子供の頃から見られていたんだろうね。」
「そうなの?」
すると祖母は、にっこり笑いながらこう言った。
「いろんなことがいっぱいあったからねぇ・・・」
祖母はまた三日月を見上げた。
いや、その目は、もっと遠くのなにかを見ていたのかもしれない。
遠くのなにか。
今、私が三日月を見上げ、祖母を思い出しているように、あのときの祖母もなにかを思い出していたのだろうと、今は、そう思う。
あの夜、祖母は着物を着ていた。
薄緑色で細かい麻の葉の柄だった。
洗いたての白髪の混じった髪を束ね、櫛で器用に留めていた。
そういえば、祖母が洋服を着ていた記憶はない。
いつも、着物に割烹着。
着物は自分で洗い張りをし、縫い直し、祖母はそうやって着物を着続けていた。
子供頃の私は、祖母のそれまでの人生なんて、考えることすらなかった。
「春のうららの隅田川」で始まる「花」という歌が好きで、洗濯物を干しながらよく歌っていた。
昼ごはんには大好きなゴマ汁を作ってくれた。
電化製品の扱いが苦手で、困ったことが起こると、向かいに住む母を大声で呼んだ。
電話が鳴ると、「はいはい」と言いながら立ち、普段より高い声で「もしも~し」と言って出た。
私にとって、祖母は最初から祖母だった。
大正生まれの祖母は、関東大震災や太平洋戦争も経験している。
日本の歴史と照らし合わせてみても、穏やかな時代とはいえない。
平坦な人生ではなかったと思う。
祖母は関東大震災で、実の姉を亡くしている。
祖母が何人兄弟だったのかはわからないが、末っ子だったそうだ。
年が離れていたその姉は、母のように祖母の面倒をみてくれていた。
あの大震災の日、祖母の姉は仕事にでかけていた。
その姉が震災で行方不明になって、連絡がない。
父親はあの暑さのなか、昼夜、寝ずに瓦礫のなかを探し続けたそうだ。
一週間も過ぎたころ、姉は、グシャグシャに崩れた勤め先のビルのトイレのなかで死んでいた。
昔は、柱の多いトイレが安全と言われていたから逃げ込んだのかもしれない、と祖母は言う。
ようやっと娘を見つけた父親は、その一か月後に過労で亡くなった。
「お父さんはね、とっても美男子だったのよ。お姉さんはお父さん似だっかからきれいな人だった。
ばあばあはお母さん似だったから、まぁ、10人なみだねぇ」と言って笑っていた。
一家の大黒柱を失い、残された家族の生活は大変だったろうと思う。
太平洋戦争では、横浜大空襲で家を焼かれた。
すでに祖父と結婚していて、3人の子供があった。
母はその2番目の娘だ。
空襲の最中、家族は防空壕に避難した。
隣の家の防空壕に焼夷弾(しょういだん)が直撃し、炎が上がった。
一家は全滅したという。
焼夷弾の落下地点がほんの数メートルずれていれば、私はこの世にいないことになる。
焼夷弾は、「燃やし尽くすための爆弾」と、母は言った。
木と紙で出来ている日本の家屋を燃やし尽くし、そこに住む人間を焼き尽くすための爆弾だったと、母は言った。
当時小学生だった母の話によれば、横浜に落とされた焼夷弾は、最初、町を丸く囲むように落とされた。
いくつもの炎の輪が、竜巻のような風を起こした。
次に、焼夷弾は、その炎の輪の中に×の字を書くように規則正しく落とされていった。
炎の輪に囲まれた人々は、どこにも逃げることができなくなった。
「ネズミ一匹逃げられないというのは、ああいうことだ」と母は言っていた。
そこにいるすべてを焼き尽くすために落とされた、それが焼夷弾だった。
祖母たちの防空壕も火の海に巻かれ、一家は、戦火の中を走り出す。
飛行機からの機銃掃射が、容赦なく追ってきた。
女性も子供も年寄りも関係なく狙い撃ちしていく。
耳のすぐ横を無数の乾いた音が走っていく。
飛行機から打たれる弾は、「バンバン」なんて音は立てないのだという。
かすれた風を切る音と、それに打たれた人間が、僅かな声を上げてパタパタ前のめりに倒れていく。
赤ん坊を抱いた若い女性が、母たちのすぐ前を走っていたが、バタッと倒れて身動き一つしなかった。
祖母は、母たち二人の子供の手を引いて走り続けた。
祖父はもう一人の赤ん坊を背負い、祖母の肩を鷲づかみに引いて走った。
母親に千切れんばかりに腕を引かれながら、母はこのとき一瞬振り返って空を見上げている。
このとき母は、今、まさに自分を殺そうと迫る操縦席に座るアメリカ兵の顔を見たそうだ。
「自分は死ぬ」
そう思った。
そのときだった。
走る母たちの後方から一人の大男が走ってきた。
アメリカ兵だった。
アメリカ兵の捕虜だった。
母が住む家の近所には、捕虜収容所があった。
のちに聞いた話では、空襲の最中、人命救助優先の判断から捕虜は開放されていたそうだ。
母が見たアメリカ兵は、その開放された捕虜だった。
彼は3歳くらいの日本人の子供を脇に抱え、背中には小さなお婆さんを背負って走っていた。
子供は「お母ちゃん!お母ちゃん!」と泣き叫んでいた。
母は、このときの、この二つの光景を鮮やかに憶えている。
「アメリカを恨んだり憎んだりする気持ちは無い」とこの話をするとき、よく言っていた。
「あの捕虜は、日本人の子供とお婆さんを助けようと必死に走っていたの。おんなじ人間。憎しみ合ったらまた戦争が起こるだけ。」
どこをどう逃げたのかはわからない。
けれど一家は生き延びた。
気が付けば、辺りは何も無くなっていた。
いや、何も無かったわけではない。
焼け焦げた屍が無数に横たわっていたという。
空襲で焼け野原になった横浜から一家は祖父の実家がある田舎に逃れたが、実家とはいえ、三男坊の祖父の家族に、手厚いもてなしはなかった。
一家は、雨をしのげるだけの納屋に住まわせてもらったそうだ。
祖母には針の筵(むしろ)だった、と母は言ったが、それがどういうことだったのかは、わからない。
「みんな生きるのに精いっぱいで、他の家族の面倒なんて、みれなかったんでしょう」
そう言っただけだった。
祖父の実家に長居することもできず、焼け野原になった横浜に戻った家族が見たものは、自分たちの家のあったところに、他人のバラックが建っている現実だった。
どう交渉しても相手は立ち退いてはくれない。
結局、家も土地も失った一家は、生き残った命五つに感謝して、一から生活をはじめることとなった。
その後の一家がどうやって命を繋いだのかは、私は聞いていない。
当時の私は、母が話すことを聞いているだけで、質問することはしなかった。
まるで映画の一場面の話を聞いているようで実感がなかった。
やがて、終戦を迎え、世の中がやっと少し落ち着いた頃、英会話ができた祖父は、貿易会社に勤めた。
自分の生きてきた世界が、でんぐり返しのように変わってしまったとき、というよりも、ガチャンとガラス玉が割れるように飛び散って消失したとき、祖母たちは、どのような思いで、次の一歩を踏み出して行ったのだろう・・・。
私には想像すらできない。
アルバムの写真を見ると、縁側に座った祖父母は、何事もなかったかのように笑っている。
祖父は縁側にあぐらをかき、その横で祖母は赤ん坊の私を抱いてこちらを見ている。足元には犬が寝ている。
父が撮った写真だろう。
私は初孫だった。
白黒の写真には、ゆったりした時間と陽だまりの暖かさがあふれている。
祖父母から、戦争の体験を聞いたことは一度もない。
焼夷弾の話も、隣りの家族が全滅したことも、赤ん坊を抱いた女性の話も、のちに母から聞いた話だ。
私が知っている祖父母は、すでに白髪が生え、老人となった祖父母である。
人生の最初から年をとっていたかのように、生活が落ち着いて、穏やかに日々を送る姿だ。
「じいじい」
「ほいよ、おチエさん?」
「ばあばあ、あのね」
「はぁい、なあに?」
けれど、そんな会話を繰り返す日々だけが、祖父母の人生のすべてではなかった。
関東大震災で姉と父を亡くしたとき、戦火の中を子供を抱いて走った時、
その夜、祖母は、どんな月を見上げたのだろう。
風呂屋を出た祖母は私の数歩前を歩いていた。
その背中は丸い。
祖母の上には三日月がいて、祖母のあとを付いていく。
祖母を見てきた祖母の月だった。
少し前かがみの背中に、電柱の明かりが揺れ、祖母の影が私の足元で左右に揺れていた。
家に近付くと、私の家の窓から先に帰った祖父の詩吟の声が聞こえてきた。
「あ、爺じい、「川中島」歌ってるよ」
「あればっかりだよ」
祖父の十八番である。
母がお勝手の窓から顔を出し、「お母さん、コロッケ揚げたから夕飯一緒に食べてって」と声をかけた。
祖母は「おやまぁ、ありがと」と言って、勝手口から上がっていく。
振り向くと、三日月がまだそこにいた。
電信柱によりかかって、「今日はここまでか」と名残惜しそうだ。
私は三日月に小さく手を振った。
祖母に続いて私も家にあがり、すぐに母の割烹着の横にくっついた。
カレーの香りのする揚げたてのコロッケは、母の味である。
御膳の上には、山になったコロッケが大皿に乗っている。
祖父、祖母、母、
そろそろ父も帰ってくるだろう。
柱時計を見上げながら母が言った。
「先に始めてましょう」
「いただきます」
みんなで声を揃えて言う。
「お父さん、まだかな」
私はコロッケを一口、口に含んだまま、玄関へ行こうと立ちあがった。
「ちゃんと座って食べなさい。お行儀がわるいですよ」
祖母のきりりとした声が制止した。
今夜のように、桜の向こうに浮かぶ三日月を見ると、あの夜のことを思い出す。
手をパッとひろげ、三日月をつかもうとした祖母のことを。
そして、手を開いて「取れなかった」と残念そうに笑った祖母のことを。
祖母は、亡くなる数年前から自宅の居間でよく漢字の勉強をしていた。
「年をとると、漢字を忘れてしまうよ。ばあばあも勉強しなくちゃねぇ」
そう言って、辞書を開いては、眉を寄せながら虫眼鏡で睨んでいた。
お膳に帳面をひろげ、鉛筆で何度も書く。
年を重ねた祖母は、ますます小さく縮んで、お膳に埋まりそうに座っていた。
ときどき、立ち上がっては腰をたたき、縁側にあるカニシャボテンの花ガラを摘んでいた。
祖母の子供時代がどんなであったかは知らない。
どんな勉強をしたのかも知らない。
ただ、祖母がやりたかった勉強を、十分にできる環境ではなかったのだろうと、今さらながら、やっとそのことに私は気づいている。
風呂屋へ一緒に行った祖母も祖父も、すでにこの世にはいない。
父も母も、いない。
祖母は、コスモスの咲く秋に、この世を去っていった。
秋の満月がきれいな夜だった。
祖母がコスモスの揺れる風に手を引かれ、満月の夜空へ向かって軽やかな足取りで昇っていく、その笑顔が見えるような気がした。
今夜の三日月は、のんびりしているようだ。
まだ私を見ている。
あかんべぇをしても、怒らない。
満ちては欠け、新月となって見えなくなるが、居なくなるわけではない。
ふたたび、ニッと笑いながら姿を見せる。
優しく微笑んでいるようにも、そして、悲しくて悲しくて泣きながら笑っているようにも。
見上げる人間の数だけ、その笑顔は違って見えるのだろう。
月は、なにか、言いたげだ。
けれど、その声に、誰かが耳を傾けることは、今までも、これからも、ないのかもしれない。
今、この瞬間、私は私の人生を歩んでいる。
今までも、これからもそうなのだ。
いろんなことがあるから・・・。だから面白いと。
祖母が言っていた。
祖母たちは、もうカンパネルラに出会って、その面白かった人生を長々と話しているのかもしれない。
たくさん話すことがあるだろう。
一歩、歩けば、一歩ぶん、ちゃんと私に付いて来ている。
「だるまさんが転んだ!」
振り向くと、おちゃめな三日月だ。
ありがたいことだ。
東の夜空の高いところに、羽毛で織ったような雲がかかっている。
その雲の切れ間にいる三日月。
歳を重ね、近視と乱視の私の目には、幾つもの三日月が手裏剣の軌跡のように見える。
桜の便りが聞こえてくるこの季節の夜空は、ほんのり薄紅がかって美しい。
そんな、まったりした夜空には、銅鏡のように輝く満月もいいけれど、刃物のように鋭利に堅く光る三日月のほうが私は好きだ。
子供の頃は、この三日月を見ると、夜空がニッと笑っているように思えたものだ。
スマイルマークのあの口。
いや、ピエロのように泣き笑いしている口だったか。
あの口に梯子をかけて上まで行けたら、と想像したことがある。
満月よりは引っかけやすそうに思えて、上に登れば、月の魔力でどこまでもどこまでも先の先まで見渡せると思えた。
知らないところ、行ったことのないところを見たかった。
いつか、その知らないところ、行ったことのないところを目指して、へとへとに疲れるまで歩いて行けば、銀河鉄道に乗って行ったあのカンパネルラが、もう一つの三日月を背にして武将のように道の真ん中に立っている。私は、私の三日月を背にして、ギラギラと笑いながらカンパネルラの前に立つ。
そう想像するとわくわくした。
そう、確かにいつかは、誰しもカンパネルラに出会う道を行くことになるのだろうけれど・・・。
笑っている。夜空が笑っている。
一年のうちでも、この桜の時期が、その笑みが一番穏やかに感じられる。
子供の頃の思い出がある。
やはり桜の季節だった。
私は小学生に上がったばかりの年だったろう。
祖父母と3人でお風呂屋さんへ行った帰り道のこと。
桜の花に隠れながら、三日月は、私たちのあとを付いてきていた。
風呂屋の煙突にぶつかっても、音もしない。
藍色の夜空にレモンの果汁が一滴すべったように、瑞々しい輝きを放っていた。
「なに上ばかり見てるの? 転びますよ」
祖母は振り返り、すぐにまた、洗面器に入った石鹸箱の音をカタカタさせながら、砂利道を足早に歩いて行こうとする。
祖父のほうは、もうだいぶ先を歩いていて、道の角を曲がって行く後ろ姿が見えた。せっかちな祖父は、足も速い。
「早くしなさい。行っちゃうよ」
「ばあばあ、あのね、お月さん、私の手が届きそう。」
私は歩きながら両手を夜空に向かって伸ばした。
両手10本の指の間で、ころころ三日月が転がっている。
祖母は足をとめて振り返り、空を見上げた。
「あぁ、お月さん、見てたんだね」
「ずっと付いてきてるの。いつも、そう思うの」
祖母は、ふうと息を吐き、祖母と同時に歩みを止めた祖母の月を見上げた。
しばらくして祖母は
「届きそうだね」
そう言って、右手をパッとひろげ、甲虫でも取るように素早く空を切った。
握った手の平を、そっと開き、
「あれ? 取れなかった」
祖母は私の顔を見てわざと残念そうに言った。
「ねぇ、ばあばあ、お月さん、今日は笑ってるよね」
「そうだね。あれは笑っているんだろうね。」
「ね、笑っているでしょ」
「ばあばぁが子供のときも、笑ってたよ。大人になってからも、ずっと笑っているねぇ。」
「どうして笑っているの?」
「そりゃぁ・・・」
言いかけて、祖母は私の顔をじっと見た。
「面白いからねぇ。人間は面白いからね」
「お月さまは人間を見てるの?」
「そう。お月さんはね、人間を見てるのよ。」
「私のことも? 見てる?」
「そうでしょうよ。おチエさんも面白いから、ねぇ」
祖父母は私の名前に「お」を付けて呼んだ。
他の孫にはそういう呼び方はしなかった。
私だけ、名前に「お」を付け、「さん」も付けて「おチエさん」と呼んだ。
祖母の家と私の家は、道をはさんで向かい合わせに住んでいた。
私たちは、ほぼ毎日顔を合わせ、毎日なんらかの時間を一緒に過ごしていた。
私は、祖母と共に過ごす時間が多かった。
実の母親ということもあって、気兼ねがなかったのだろう。
母は、祖母の家に行ったまま、何時間も帰ってこない私を怒ることはなかった。
祖母は、本を読んだり、あや取りを教えてくれた。
「私のことが面白いのかな?」
「おチエさんだけじゃなくて、人間みんなを見てるのよ。ずっとねぇ、昔から。ばあばあも、子供の頃から見られていたんだろうね。」
「そうなの?」
すると祖母は、にっこり笑いながらこう言った。
「いろんなことがいっぱいあったからねぇ・・・」
祖母はまた三日月を見上げた。
いや、その目は、もっと遠くのなにかを見ていたのかもしれない。
遠くのなにか。
今、私が三日月を見上げ、祖母を思い出しているように、あのときの祖母もなにかを思い出していたのだろうと、今は、そう思う。
あの夜、祖母は着物を着ていた。
薄緑色で細かい麻の葉の柄だった。
洗いたての白髪の混じった髪を束ね、櫛で器用に留めていた。
そういえば、祖母が洋服を着ていた記憶はない。
いつも、着物に割烹着。
着物は自分で洗い張りをし、縫い直し、祖母はそうやって着物を着続けていた。
子供頃の私は、祖母のそれまでの人生なんて、考えることすらなかった。
「春のうららの隅田川」で始まる「花」という歌が好きで、洗濯物を干しながらよく歌っていた。
昼ごはんには大好きなゴマ汁を作ってくれた。
電化製品の扱いが苦手で、困ったことが起こると、向かいに住む母を大声で呼んだ。
電話が鳴ると、「はいはい」と言いながら立ち、普段より高い声で「もしも~し」と言って出た。
私にとって、祖母は最初から祖母だった。
大正生まれの祖母は、関東大震災や太平洋戦争も経験している。
日本の歴史と照らし合わせてみても、穏やかな時代とはいえない。
平坦な人生ではなかったと思う。
祖母は関東大震災で、実の姉を亡くしている。
祖母が何人兄弟だったのかはわからないが、末っ子だったそうだ。
年が離れていたその姉は、母のように祖母の面倒をみてくれていた。
あの大震災の日、祖母の姉は仕事にでかけていた。
その姉が震災で行方不明になって、連絡がない。
父親はあの暑さのなか、昼夜、寝ずに瓦礫のなかを探し続けたそうだ。
一週間も過ぎたころ、姉は、グシャグシャに崩れた勤め先のビルのトイレのなかで死んでいた。
昔は、柱の多いトイレが安全と言われていたから逃げ込んだのかもしれない、と祖母は言う。
ようやっと娘を見つけた父親は、その一か月後に過労で亡くなった。
「お父さんはね、とっても美男子だったのよ。お姉さんはお父さん似だっかからきれいな人だった。
ばあばあはお母さん似だったから、まぁ、10人なみだねぇ」と言って笑っていた。
一家の大黒柱を失い、残された家族の生活は大変だったろうと思う。
太平洋戦争では、横浜大空襲で家を焼かれた。
すでに祖父と結婚していて、3人の子供があった。
母はその2番目の娘だ。
空襲の最中、家族は防空壕に避難した。
隣の家の防空壕に焼夷弾(しょういだん)が直撃し、炎が上がった。
一家は全滅したという。
焼夷弾の落下地点がほんの数メートルずれていれば、私はこの世にいないことになる。
焼夷弾は、「燃やし尽くすための爆弾」と、母は言った。
木と紙で出来ている日本の家屋を燃やし尽くし、そこに住む人間を焼き尽くすための爆弾だったと、母は言った。
当時小学生だった母の話によれば、横浜に落とされた焼夷弾は、最初、町を丸く囲むように落とされた。
いくつもの炎の輪が、竜巻のような風を起こした。
次に、焼夷弾は、その炎の輪の中に×の字を書くように規則正しく落とされていった。
炎の輪に囲まれた人々は、どこにも逃げることができなくなった。
「ネズミ一匹逃げられないというのは、ああいうことだ」と母は言っていた。
そこにいるすべてを焼き尽くすために落とされた、それが焼夷弾だった。
祖母たちの防空壕も火の海に巻かれ、一家は、戦火の中を走り出す。
飛行機からの機銃掃射が、容赦なく追ってきた。
女性も子供も年寄りも関係なく狙い撃ちしていく。
耳のすぐ横を無数の乾いた音が走っていく。
飛行機から打たれる弾は、「バンバン」なんて音は立てないのだという。
かすれた風を切る音と、それに打たれた人間が、僅かな声を上げてパタパタ前のめりに倒れていく。
赤ん坊を抱いた若い女性が、母たちのすぐ前を走っていたが、バタッと倒れて身動き一つしなかった。
祖母は、母たち二人の子供の手を引いて走り続けた。
祖父はもう一人の赤ん坊を背負い、祖母の肩を鷲づかみに引いて走った。
母親に千切れんばかりに腕を引かれながら、母はこのとき一瞬振り返って空を見上げている。
このとき母は、今、まさに自分を殺そうと迫る操縦席に座るアメリカ兵の顔を見たそうだ。
「自分は死ぬ」
そう思った。
そのときだった。
走る母たちの後方から一人の大男が走ってきた。
アメリカ兵だった。
アメリカ兵の捕虜だった。
母が住む家の近所には、捕虜収容所があった。
のちに聞いた話では、空襲の最中、人命救助優先の判断から捕虜は開放されていたそうだ。
母が見たアメリカ兵は、その開放された捕虜だった。
彼は3歳くらいの日本人の子供を脇に抱え、背中には小さなお婆さんを背負って走っていた。
子供は「お母ちゃん!お母ちゃん!」と泣き叫んでいた。
母は、このときの、この二つの光景を鮮やかに憶えている。
「アメリカを恨んだり憎んだりする気持ちは無い」とこの話をするとき、よく言っていた。
「あの捕虜は、日本人の子供とお婆さんを助けようと必死に走っていたの。おんなじ人間。憎しみ合ったらまた戦争が起こるだけ。」
どこをどう逃げたのかはわからない。
けれど一家は生き延びた。
気が付けば、辺りは何も無くなっていた。
いや、何も無かったわけではない。
焼け焦げた屍が無数に横たわっていたという。
空襲で焼け野原になった横浜から一家は祖父の実家がある田舎に逃れたが、実家とはいえ、三男坊の祖父の家族に、手厚いもてなしはなかった。
一家は、雨をしのげるだけの納屋に住まわせてもらったそうだ。
祖母には針の筵(むしろ)だった、と母は言ったが、それがどういうことだったのかは、わからない。
「みんな生きるのに精いっぱいで、他の家族の面倒なんて、みれなかったんでしょう」
そう言っただけだった。
祖父の実家に長居することもできず、焼け野原になった横浜に戻った家族が見たものは、自分たちの家のあったところに、他人のバラックが建っている現実だった。
どう交渉しても相手は立ち退いてはくれない。
結局、家も土地も失った一家は、生き残った命五つに感謝して、一から生活をはじめることとなった。
その後の一家がどうやって命を繋いだのかは、私は聞いていない。
当時の私は、母が話すことを聞いているだけで、質問することはしなかった。
まるで映画の一場面の話を聞いているようで実感がなかった。
やがて、終戦を迎え、世の中がやっと少し落ち着いた頃、英会話ができた祖父は、貿易会社に勤めた。
自分の生きてきた世界が、でんぐり返しのように変わってしまったとき、というよりも、ガチャンとガラス玉が割れるように飛び散って消失したとき、祖母たちは、どのような思いで、次の一歩を踏み出して行ったのだろう・・・。
私には想像すらできない。
アルバムの写真を見ると、縁側に座った祖父母は、何事もなかったかのように笑っている。
祖父は縁側にあぐらをかき、その横で祖母は赤ん坊の私を抱いてこちらを見ている。足元には犬が寝ている。
父が撮った写真だろう。
私は初孫だった。
白黒の写真には、ゆったりした時間と陽だまりの暖かさがあふれている。
祖父母から、戦争の体験を聞いたことは一度もない。
焼夷弾の話も、隣りの家族が全滅したことも、赤ん坊を抱いた女性の話も、のちに母から聞いた話だ。
私が知っている祖父母は、すでに白髪が生え、老人となった祖父母である。
人生の最初から年をとっていたかのように、生活が落ち着いて、穏やかに日々を送る姿だ。
「じいじい」
「ほいよ、おチエさん?」
「ばあばあ、あのね」
「はぁい、なあに?」
けれど、そんな会話を繰り返す日々だけが、祖父母の人生のすべてではなかった。
関東大震災で姉と父を亡くしたとき、戦火の中を子供を抱いて走った時、
その夜、祖母は、どんな月を見上げたのだろう。
風呂屋を出た祖母は私の数歩前を歩いていた。
その背中は丸い。
祖母の上には三日月がいて、祖母のあとを付いていく。
祖母を見てきた祖母の月だった。
少し前かがみの背中に、電柱の明かりが揺れ、祖母の影が私の足元で左右に揺れていた。
家に近付くと、私の家の窓から先に帰った祖父の詩吟の声が聞こえてきた。
「あ、爺じい、「川中島」歌ってるよ」
「あればっかりだよ」
祖父の十八番である。
母がお勝手の窓から顔を出し、「お母さん、コロッケ揚げたから夕飯一緒に食べてって」と声をかけた。
祖母は「おやまぁ、ありがと」と言って、勝手口から上がっていく。
振り向くと、三日月がまだそこにいた。
電信柱によりかかって、「今日はここまでか」と名残惜しそうだ。
私は三日月に小さく手を振った。
祖母に続いて私も家にあがり、すぐに母の割烹着の横にくっついた。
カレーの香りのする揚げたてのコロッケは、母の味である。
御膳の上には、山になったコロッケが大皿に乗っている。
祖父、祖母、母、
そろそろ父も帰ってくるだろう。
柱時計を見上げながら母が言った。
「先に始めてましょう」
「いただきます」
みんなで声を揃えて言う。
「お父さん、まだかな」
私はコロッケを一口、口に含んだまま、玄関へ行こうと立ちあがった。
「ちゃんと座って食べなさい。お行儀がわるいですよ」
祖母のきりりとした声が制止した。
今夜のように、桜の向こうに浮かぶ三日月を見ると、あの夜のことを思い出す。
手をパッとひろげ、三日月をつかもうとした祖母のことを。
そして、手を開いて「取れなかった」と残念そうに笑った祖母のことを。
祖母は、亡くなる数年前から自宅の居間でよく漢字の勉強をしていた。
「年をとると、漢字を忘れてしまうよ。ばあばあも勉強しなくちゃねぇ」
そう言って、辞書を開いては、眉を寄せながら虫眼鏡で睨んでいた。
お膳に帳面をひろげ、鉛筆で何度も書く。
年を重ねた祖母は、ますます小さく縮んで、お膳に埋まりそうに座っていた。
ときどき、立ち上がっては腰をたたき、縁側にあるカニシャボテンの花ガラを摘んでいた。
祖母の子供時代がどんなであったかは知らない。
どんな勉強をしたのかも知らない。
ただ、祖母がやりたかった勉強を、十分にできる環境ではなかったのだろうと、今さらながら、やっとそのことに私は気づいている。
風呂屋へ一緒に行った祖母も祖父も、すでにこの世にはいない。
父も母も、いない。
祖母は、コスモスの咲く秋に、この世を去っていった。
秋の満月がきれいな夜だった。
祖母がコスモスの揺れる風に手を引かれ、満月の夜空へ向かって軽やかな足取りで昇っていく、その笑顔が見えるような気がした。
今夜の三日月は、のんびりしているようだ。
まだ私を見ている。
あかんべぇをしても、怒らない。
満ちては欠け、新月となって見えなくなるが、居なくなるわけではない。
ふたたび、ニッと笑いながら姿を見せる。
優しく微笑んでいるようにも、そして、悲しくて悲しくて泣きながら笑っているようにも。
見上げる人間の数だけ、その笑顔は違って見えるのだろう。
月は、なにか、言いたげだ。
けれど、その声に、誰かが耳を傾けることは、今までも、これからも、ないのかもしれない。
今、この瞬間、私は私の人生を歩んでいる。
今までも、これからもそうなのだ。
いろんなことがあるから・・・。だから面白いと。
祖母が言っていた。
祖母たちは、もうカンパネルラに出会って、その面白かった人生を長々と話しているのかもしれない。
たくさん話すことがあるだろう。
一歩、歩けば、一歩ぶん、ちゃんと私に付いて来ている。
「だるまさんが転んだ!」
振り向くと、おちゃめな三日月だ。
ありがたいことだ。