この間、赤羽に居らっしゃる大叔母さんの所へ遊びに行きました。
そもそも、今年のはじめに大叔母さんよりお手紙を戴いて
何やらいろいろ話しておきたい事が有るから一度車でおいでなさい。との事。
時期も4月の終わりごろがよろしいでしょう。と
母と一緒に相談して日程を調整して大叔母さんへ電話、4月30日にしましょうと確認を取ると
電話に出たお嫁さんは何も聞かされてなかった様でびっくりされて居ました。
けれども事情がわかると何よりも喜んでくれました。
トリコさんは7月で90歳(大正12年うまれ)になる、結婚記念日は6月で70年の節目に当たる。
当日午後に赤羽に着くと、以前の40年以上の昔、母が独身時代にお世話になった大叔母さん夫婦
の話を聞く。森永歯科は西が丘で戦前から営業をして居た。戦後は下宿人もたくさんの出入りして居た事
でも、今回は、それに加えて、森永信光の事をお話してもらえた。
仲人は森永信光であったと言う事が判明(森永信光の当時の友人を介して)
お見合い写真は、(割烹着)写真屋さんに遊びに行った時に撮った写真、
偶然間違えて渡してしまった所、逆にこれがいかにも働き者に見えて気に入られたそうです。(実際、働き者で信光以外にも大変多くの方がお世話になりました)
そうしたお話のあと昭和16年の森永信光の写真を(目黒の雅叙園での結婚式の時のを)見せてもらった。。
福井県、殿下(てんが)に本家がある森永与右衛門の次男森永信光は、拓殖大学を出て、台湾へ行き
日本に終戦前に帰ってきて居た。
台湾の役職を退いたのは、大正12年3月1日とある、そこで思い出したのが、もう一人の曾祖父である片岡巖。
彼も同じく大正12年5月1日に地方法院通訳を退官している。
大正12年3月1日と5月1日両方とも4月を挟んではいるが、同じ様な年度変わりの時期で重なる。
この奇妙な一致した偶然に何か裏付ける理由が有りそうだと感じた。
何かが変わった大正12年(1923年)、何が変わった台湾。
1、まずは、台湾総督府
1921年に委任立法制度となる。
文官時代の総督、田健二郎から内田嘉吉へ
皇太子(後の昭和天皇)の台湾訪問4月17日~26日(台南の成功大学にガジュマルの樹を植えられた。)
翌大正13年(1922年) 皇太子ご成婚
2、次に、台湾人の環境
林献堂たちによる台湾文化協会が1921年10月発足
台湾人による 台湾の歴史、漢文や公衆衛生、法律講座、経済学講座などを地域社会に広める。
3、当時の日本政府の政治の面
関東大震災9月1日
虎ノ門事件12月27日→山本内閣総辞職
4、西洋の動向
前年の1922年のアイルランド内戦を経て、アイルランドが独立した。
ネパールもイギリスから独立
うーん。
まだまだわからない事も多いけれど、何か激動の昭和の入り口が見えてきた時期。
台湾人にとっては、武力抵抗にとってかわる独立心、自立が目指された時期だと思う。
今から振り返ると、歴史の折り返し地点でもあるような気がする。
そもそも、今年のはじめに大叔母さんよりお手紙を戴いて
何やらいろいろ話しておきたい事が有るから一度車でおいでなさい。との事。
時期も4月の終わりごろがよろしいでしょう。と
母と一緒に相談して日程を調整して大叔母さんへ電話、4月30日にしましょうと確認を取ると
電話に出たお嫁さんは何も聞かされてなかった様でびっくりされて居ました。
けれども事情がわかると何よりも喜んでくれました。
トリコさんは7月で90歳(大正12年うまれ)になる、結婚記念日は6月で70年の節目に当たる。
当日午後に赤羽に着くと、以前の40年以上の昔、母が独身時代にお世話になった大叔母さん夫婦
の話を聞く。森永歯科は西が丘で戦前から営業をして居た。戦後は下宿人もたくさんの出入りして居た事
でも、今回は、それに加えて、森永信光の事をお話してもらえた。
仲人は森永信光であったと言う事が判明(森永信光の当時の友人を介して)
お見合い写真は、(割烹着)写真屋さんに遊びに行った時に撮った写真、
偶然間違えて渡してしまった所、逆にこれがいかにも働き者に見えて気に入られたそうです。(実際、働き者で信光以外にも大変多くの方がお世話になりました)
そうしたお話のあと昭和16年の森永信光の写真を(目黒の雅叙園での結婚式の時のを)見せてもらった。。
福井県、殿下(てんが)に本家がある森永与右衛門の次男森永信光は、拓殖大学を出て、台湾へ行き
日本に終戦前に帰ってきて居た。
台湾の役職を退いたのは、大正12年3月1日とある、そこで思い出したのが、もう一人の曾祖父である片岡巖。
彼も同じく大正12年5月1日に地方法院通訳を退官している。
大正12年3月1日と5月1日両方とも4月を挟んではいるが、同じ様な年度変わりの時期で重なる。
この奇妙な一致した偶然に何か裏付ける理由が有りそうだと感じた。
何かが変わった大正12年(1923年)、何が変わった台湾。
1、まずは、台湾総督府
1921年に委任立法制度となる。
文官時代の総督、田健二郎から内田嘉吉へ
皇太子(後の昭和天皇)の台湾訪問4月17日~26日(台南の成功大学にガジュマルの樹を植えられた。)
翌大正13年(1922年) 皇太子ご成婚
2、次に、台湾人の環境
林献堂たちによる台湾文化協会が1921年10月発足
台湾人による 台湾の歴史、漢文や公衆衛生、法律講座、経済学講座などを地域社会に広める。
3、当時の日本政府の政治の面
関東大震災9月1日
虎ノ門事件12月27日→山本内閣総辞職
4、西洋の動向
前年の1922年のアイルランド内戦を経て、アイルランドが独立した。
ネパールもイギリスから独立
うーん。
まだまだわからない事も多いけれど、何か激動の昭和の入り口が見えてきた時期。
台湾人にとっては、武力抵抗にとってかわる独立心、自立が目指された時期だと思う。
今から振り返ると、歴史の折り返し地点でもあるような気がする。













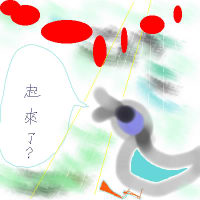
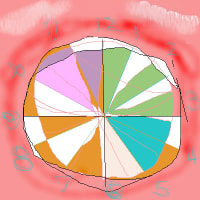

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます