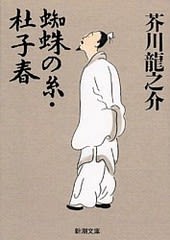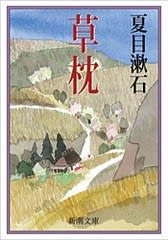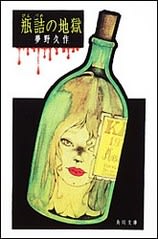地獄に落ちた男が、やっとのことでつかんだ一条の救いの糸。ところが自分だけが助かりたいというエゴイズムのために、またもや地獄に落っこちる『蜘蛛の糸』。
大金持ちになることに愛想がつき、平凡な人間として自然のなかで生きる幸福をみつけた『杜子春』。
魔法使いが悪魔の裁きを受ける神秘的な『アグニの神』。
健康で明るく、人間性豊かな少年少女のために書かれた作品集。
出版社:新潮社(新潮文庫)
ここに収録されている作品は、すべて一度は読んだことがある作品ばかりだ。
だがどの作品も、再読にもかかわらず、楽しんで読むことができる。
年少者向けに書かれたということもあり、たとえば『犬と笛』『アグニの神』『仙人』『白』などは物足りなさはあるものの、基本的にエンタテイメント性があって、退屈するということはなかった。
芥川龍之介という作家の上手さを体感することができる。
しかし、ずいぶん久しぶりに読む作品ばかりなので、作品から受ける印象が変わっているものも多い。
特に表題作の『蜘蛛の糸』などはそうだ。
正直こんなに偽善的な作品だったのか、と読み終えた後では驚いている。
『蜘蛛の糸』と言うと、カンダタのエゴイズムについて触れられる場合が多い。
けれど、本当に言及すべきは、御釈迦様の行動にあるのではないだろうか、と今回は思った。
苦しんでいるやつがいる⇒かわいそうだな⇒じゃあ支援をしてあげよう⇒でもそれが原因で何かが起きても当人たちの問題だよね、俺には関係ないよ。
この話の中の御釈迦様の行動は、そう言っているのと同じと僕には見える。
確かに極楽に登れるか否かは、カンダタの自己責任と言われればそれまでだ。
だが最後まで面倒を見、責任を取る気がないのに、希望を少しでも見せようとした、御釈迦様の行動は残酷でもあるのだ。
それは御釈迦様の偽善めいた、ただの自己満足ではないか。強者が強者であることを利用して、弱者を手のひらで弄んでいるだけではないか。
俗っぽい僕はそう思わなくもない。
僕は偽善のすべてを否定するつもりはない。そもそもすべての善には偽善の匂いがつきまとう。
だがこの御釈迦様の行動は、仏教の最高位にいる存在のわりには、ずいぶん身勝手な偽善である。
そういう意味、この世には完璧な存在などいない、という教訓を本作は含んでいるのかもしれない。
もちろん深読みだ。
『蜜柑』も以前読んだときとは印象が違っていて驚いた。
だがこちらは『蜘蛛の糸』のようにネガティブな変化ではない。
こんなにも美しい作品だったのか、というさわやかでポジティブな印象である。
以前読んだときも、それなりに良いと思ったものの、ただの小品だなという以上の印象を受けなかった。
だが、今回再読し、ラストまで読んだとき、ただの小品という印象は吹き飛んでしまった。
そう思った理由の一つは、少女が蜜柑を投げ上げるシーンの美しさにあるのだ。
そのシーンは描写も鮮やかで、余韻も美しい。そしてそれゆえに、むちゃくちゃ心に沁みるのである。
まさに名シーンだ。
そしてもう一つは、「私」の心の変化にある。
それまで倦怠感を漂わせ、ある種の意地の悪い気持ちで少女を眺めていたのに、少女の行動を見て、マイナスに沈んでいた感情は、プラスへと変化する。
その心象のダイナミズムが小気味よくて、読みながら深く感動してしまう。
紙数は少ないけれど、芥川の作品では、まちがいなく上位に入る一品と、確信した。
そのほかにもおもしろい作品はある。
皮肉の利いたラストが心に残る『魔術』。
説教臭い話なのに、それを感じさせず、楽しく読ませてくれる『杜子春』。
昂揚感から不安へと変化していく少年の心理を、短くも的確に描写していて印象的な『トロッコ』。
芥川らしいアイロニカルな視点が楽しい『猿蟹合戦』、など。
物足りない部分こそあるものの、芥川龍之介の才気を味わうことができる。納得の小品集である。
評価:★★★★(満点は★★★★★)
そのほかの芥川龍之介作品感想
『河童・或阿呆の一生』
『戯作三昧・一塊の土』
『奉教人の死』
『羅生門・鼻』