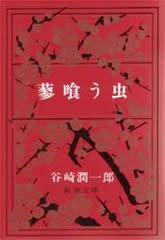僕とクミコの家から猫が消え、世界は闇にのみ込まれてゆく。――長い年代記の始まり。
出版社:新潮社(新潮文庫)
基本的にこの作品に対する感想は、おもしろい、の一語で充分と言えば充分なのだ。
溢れんばかりの奔放なイマジネーションには圧倒されるばかりだし、物語展開の予測もつかない。おもしろすぎて、ページをめくる手も本当に止まらないのだ。
加えて、たとえば笠原メイの手紙のように、笑える内容なくせして、実に深いことを語るところなど、センスは抜群である。
『ねじまき鳥クロニクル』を読むのは今回で3回目だが、それでもまるで初めて読んだときのように、いくつも新しい発見があって、飽きるということはなかった。
個人的な好みで言うなら、一番好きな春樹作品ではないのだが、作品世界が持つ広がり、深み、重み等、質の観点で言うなら、まちがいなく現時点で、村上春樹全作品の中でもトップの出来だろう。
『ねじまき鳥クロニクル』はまちがいなく、すばらしいまでの傑作である。僕は心から思う次第だ。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかの村上春樹作品感想
『アフターダーク』
『海辺のカフカ』
『東京奇譚集』
『走ることについて語るときに僕の語ること』
『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』
『若い読者のための短編小説案内』
『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』 (河合隼雄との共著)
◎蛇足すぎる上、無駄に長い追記
以下に、僕がこの作品から受け取った印象と、物語の意味の解釈と、僕が理解したことを書いてみる。
はっきり言って、物語を解釈するなんて、野暮ったいことこの上ない。
それでもこんな文章を書くのは、基本的に僕個人の自己満足でしかないことだけは先に述べておく。
この作品は表層的な物語と、裏側で進行する物語の二種類があると僕個人は感じた。
表層的な物語は読めばわかるとして、裏側で進行する物語とは、抽象的に語るなら、「具体的な事実」でなく「ボーイではなくボーイの振りをした何か」を捕らえることである。
要は、作中にあるメタファーを通して語られること。それが、僕が感じる裏側で進行する物語だ。
そしてそれらを通して見たところ、僕は『ねじまき鳥クロニクル』という作品を次のように解釈した。
それは――
個人同士の人間関係による要因、社会的な要因、時代背景による要因、事件や理不尽な事故等の要因で、人の心が傷ついてしまうということ。
そして傷ついた個人が(そして傷ついた個人と関わる人々が)その心の傷をどのように受け入れていくかということ。
それを象徴的に描いた作品だということである。
非常に乱暴な要約ではあるけれど、それが僕が得た結論だ。
実際、この作品では、多くの人が心に傷を負っている。
間宮中尉は、ノモンハンで悪夢のような光景に出くわし、その後の人生を無感覚のように生きることになるし、クミコも加納クレタも(二人はどう見ても象徴的な意味で分身だ)、抽象的に語られているが綿谷ノボルによって傷つけられている。
そして傷ついているという点では、具体的にはまったく語られないけれど、妻に逃げられた主人公の僕だって同じなのである(あるいは彼のあざは心に負った傷のメタファーかもしれない)。
だがそのような暴力は誰にだって「起こりうる」ことなのである。
自分とは違う他人に、何か悲惨なことが起きたとする。たいていの人はそんな暴力を、文字通り他人事のようにながめるだけだ。
けれど、それは必ずしも他人事とは限らない。
その場、そのとき、その状況下、無意味にしか見えかねない行為によって、自分も同じように誰かの手により傷つけられることもありうる。
自分が傷ついていないのは、たまたまそこに自分がいなかったというだけのことでしかないのだ。
それは、女の子の家に泊まって妻を怒らせるような事態から、戦争下の生き死に関わる問題まで、傍目で見る分の程度の大小はちがうけれど、様々な形で襲い来るものだ。
だが言い換えるならば、人に傷つけられる可能性があるということは、逆に人を傷つけてしまうこともあるということでもある。
そして、それもやっぱり誰にでも起こりうることなのだろう。
人に傷つけられること、人を傷つけてしまうこと、どちらも避けられるのなら、避けていたい行為だ。
けれど、そう願ったとしても、ときには「自由意志などというものは無力」なときもありうるのである。
「みんながいつでもやっていることなのだ」と言い訳しながら、何かや誰かを傷つけざるをえない状況だって起こりうるのだ。
代表的なのは戦争だ。命令されれば、殺すしかない。
そして傷つけてしまったという行為に、傷つけた側の人間も、心に傷を負ってしまうこともあるのだ。
物語では、そのような傷つけられる、あるいは傷つけてしまうという状況を、メタファーを駆使して執拗なくらい、綿密に描いている。
だが『ねじまき鳥クロニクル』は、そのような状況を描くだけに終始しているわけではないのだ。
傷つけるものが近くに迫っているとき、あるいはすでに何ものかに傷ついてしまったときに、人はどうすればいいのか。
それに対するある程度の指針が示されているように、僕には見えた。
心を傷つけてしまうような暴力的なことが自分の身にせまっているとき、人はどうすればいいのだろう。
まずはその点について見てみよう。
それに対する本作での答えは実にシンプルである。
それは、ときとして「叩かれれば叩きかえ」すことも必要だ、ということだ。
だがシンプルな答えの割に、それが成功する可能性は必ずしも高くない。
実際、間宮中尉はボリスに勝てなかったし、どう見ても、それが彼個人の心の傷を大きくしている。
だがそれでも、人はバットを手にして立ち向かい、「それ(要は世の理不尽で無意味な暴力)に勝たなくてはならない」ときもある。
ナイフが「ただのナイフ」であるのと同じように、暴力はただの暴力だ。
その暴力に対して、しっかりノーと言わなければいけない瞬間だってあるのだ。
もちろん暴力に対してノーと言う行為も、必要悪と言え、ひとつの暴力である。
だからこそ、暴力を受ける側は、暴力を与える側の状況に対して、「想像してはいけない」のかもしれない。
たとえば、ボリスの薬指に指輪が光っている意味を考えたりしてはいけない(個人的にはノモンハンでのその一文が印象に残っている)。
または想像することで、暴力を振るうという行為に恐怖を持ってもいけないのである。
自分、他人、社会を守るため、暴力を排除するときは、機械的なまでに、「やるべきこととしてそれをやらなくてはならない」。
そのような力強いメッセージを、僕個人は本作から受け取った。
では、すでに何かによって傷つけられてしまった場合は、どうすればいいのだろうか。
それは自分個人の場合と、他人の場合では対応が異なってくる。
まず自分個人単品の場合。
そのときは、時間をかけて克服していくしかない、と言っているように僕には見えた。
そしてそれこそ、傷つけたものに対する、ある意味では「洗練されたかたちでの復讐」なのだろう。
そして時間が来たら、井戸に降りるように、自分の意識の核の中に降りて、傷を与えたものや、傷を与えた人と向き合って対峙するしかない。
では自分ではなく、誰か他人が、何かに傷ついてしまった場合はどうだろう。
誰でもいいから助けてほしいと願う相手の場合。
それならば、「意識の娼婦」のような形で、手助けはできる。
特に自身も傷を負った人間だったら、誰かに対して優しくなれるものだ。
それ相応の適性と言うか、資格は必要だが、誰でもいいから人と触れ合いたいという相手には、ただ手を差し伸べればいいのだろう、と思う。
でも本当に近しい人間の場合は、そういうわけにもいかない。
近しい人間だと、相互に意志を通わせない限り、傷ついた相手とは正確な意味では向き合えないからだ。
それでも。自分の傷を、心を開いてすんなりと教えてくれたら、まだ対処のしようもある。
だが傷ついた相手が、その傷を秘密として抱えてしまったときは、対処のしようがない。
「十分間でお互いの気持ちがよくわかりあえる」ことも、現実にはあるのだろう。
だが、それは心の傷も含めた秘密をさらけ出さなければ、お互いの気持ちもわかりあえないのだ。
では、そういう、相手が自分の傷をさらけ出せない場合はどうすればいいのだろう。
結論としては辛抱強く待つしかない、ということなのだろう。
「まちがった時間」のときに、強引にわかり合おうとしても、物事をよけいひどく混乱させるだけなのだ。
それは考えようによっては悲惨なことだろう。
待つという行為は、自分が傷を負う側になったとき以上にしんどいのかもしれない。
けれど、もっとひどいことにだってなりえたのだ、そう思って、耐えるしかないのかもしれない。
最後は結局時間が解決するしかないのだ。
まとまりはない上に、無駄に長いけれど、僕は大体以上のように、この作品を理解した。
はっきり言って、ここまで来たら妄想の域である。
あと、何となく読んでいる最中、
『夜と霧』を思い出した。別に訴えていることの内容は似ても似つかないけれど、何となく。
もちろん人によって、上記以外の受け取り方があっても、全然ありなのだろう。それだけの懐を併せ持った深い作品だ。
とにもかくにも、『ねじまき鳥クロニクル』はまちがいなく傑作だと僕は信じる次第である。