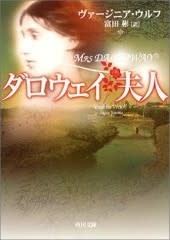現代アメリカ文学を代表する作家、ポール・オースターのニューヨーク三部作を締めくくる作品。
幼なじみのファンショーが妻子と原稿を残して失踪。「僕」は彼が残した作品の出版を協力していくうちにファンショーの妻を愛するようになる……
物語自体はスリリングだ。プロットに起伏があるし、エンターテイメントとしても飽きさせずに読む工夫がなされている。大抵の人は少なくとも読んでいる最中にこの作品を退屈と思うことはないであろう。
特にファンショーの手紙は効果的だ。そこから派生していくキャラクターの不安の様がすばらしく、ファンショーを追うことで気付いていく彼に対する憎悪と殺意に関しては読んでいても面白いものがあった。
そして頭の中の鍵のかかった部屋について述べるシーン。ひとつの事物、あるいは一人の人間がこうも、個人に大きな爪あとを残し、圧倒的な存在に膨れ上がっていく様子はどこか空恐ろしいものさえ感じられる。
そのためか、その後に描かれる「これから帰る」という電文に僕は淡い感動を覚えるのである。そこにはひとつの苦悩を乗り越えた人間の姿を垣間見るようで清々しくさえある。
そういう意味、僕はこの作品を一人の人間が、別の人間が与えた影響を払拭していく物語とも読み取った。
と、一応好意的な感想を書いたけれど、だから何なのだ、という気もちょっとしたりする。基本的にそれを言ってはおしまいかもしれないけれど、それは僕がこれまで読んできたオースターの作品(「幽霊たち」、「ムーンパレス」)にも抱いた印象だった。
オースターはつまらない作家では決してない。示唆に富む部分もあるし、感銘も受ける。しかし読み続けたい作家ではないな、と思う。
ここまで来ると感性の問題だろう。
評価:★★(満点は★★★★★)