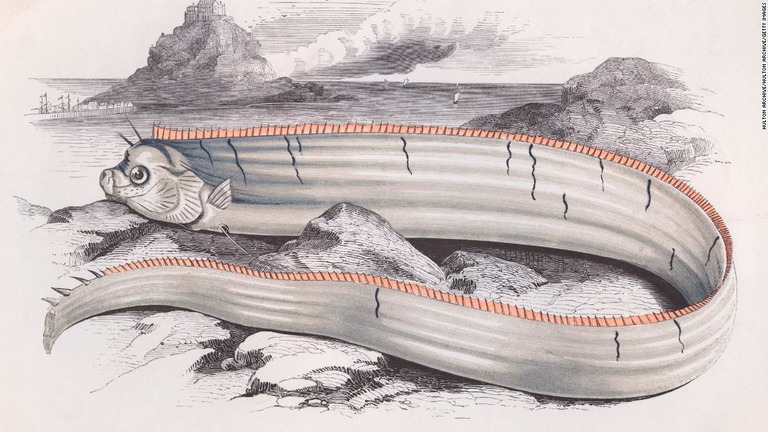日経が報じていたが、高齢者住宅に安いほど要介護老人が集中していて、公的福祉費用が膨らむ事を懸念される。
人生b100年時代と言われているこの御時勢、寝たきり老人を出来るだけ出さないようにしないと、若い世代に負荷が掛かるだけ。そのためにも、定年退職したら、知力、体力があっても仕事がなく、趣味の世界で時間を過ごしている老人が多すぎる。張りがないから、10年20年と趣味だけの世界では元気ではいられない。
政府は、庭園退職者の元気を維持できるような政治そして、老人を活用し、価値を生み出す様な仕事を創出するようにする。そうすれば、健康保険の赤字補てんの問題もなくなるし、更に価値を創生するからGDPが上がる。
もっと役人を使って人生100年時代に対応した政治を考案すべし!

見守りなどのサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)。日本経済新聞が全国の利用実態を調べると、家賃月8万円未満の安い住戸は多くの介助が要る「要介護3以上」の入居者が5割を占めた。自立した高齢者向けとの想定に反し、特別養護老人ホーム(特養)が対応すべき低所得で体が不自由な人が流入している。安いサ高住は介護報酬で収入を補おうと過剰に介護を提供しがちで、特養よりも公費の支出が膨らむ懸念がある。
■揺らぐ特養との役割分担
サ高住は国が2011年につくった制度。バリアフリーで、安否確認などの要件を満たした民間賃貸住宅を自治体が登録する。18年末時点で全国に約7200棟、23万8千戸が存在する。
法律上「住宅」なので介護は義務ではない。訪問介護などを使いたい入居者は介護事業者と契約するが、実際は介護拠点を併設し、事業者が同じケースは多い。明治大の園田真理子教授は「家賃を安くして入居者を募り、自らの介護サービスを多く使わせる動きが起きやすい」と指摘する。

本来、要介護3以上の低所得者の受け皿は公的な色彩が濃い特養だ。毎月一定額の利用料も相対的に安く、その範囲で食事や介護を提供する。必要以上にサービスを増やして、介護報酬を稼ぐ動きは起きにくい。ただ職員不足で受け入れを抑える特養が目立ち、全国に30万人の待機者がいる。行き場を失った高齢者がサ高住になだれ込む。
■家賃8万円未満、「要介護3」以上は約5割
日経新聞はサービス費を含む家賃と入居者の要介護度のデータが公開されている1862棟を対象に、その相関を分析した。家賃の平均は約10万6千円。全戸数に占める要介護3以上の住民の比率は34%だった。家賃別にみると、8万円未満の同比率は48%に達していた。金額が上がるほど比率は下がり、14万円以上は20%にとどまった。
「介護報酬を安定的に得るため、要介護度の高い人を狙い、軽い状態の人は断っている」。関東で数十棟を営む企業の代表は打ち明ける。1月に茨城県ひたちなか市のサ高住を訪ねると、併設デイサービスに約10人が集まっていた。多くが車いすに乗る。住民の4分の3が要介護3以上だ。
介護報酬の1~3割は利用者負担。残りは税金と介護保険料で賄う。要介護度が進むと支給上限額は増える。介護保険受給者は平均で上限額の3~6割台しか使っていないが、同社の計画上は住民が85%を使う前提だ。「夜勤の人件費を捻出するのに必要。暴利は貪っていない」と主張する。
兵庫県で家賃が安いサ高住の管理人も「上限額の90%を併設サービスで使ってもらっている」と話す。16年の大阪府調査では、府内のサ高住は上限額の86%を利用し、要介護3以上は特養より費用がかさんでいた。

■「寝ていればいい」
安いサ高住に要介護度の高い人が集まる傾向は都市圏で顕著だ。8万円未満の物件に住む要介護3以上の比率は首都圏が64%、関西圏が57%。都市圏は土地代が高く、家賃を下げた分を介護報酬で補うモデルが広がっている懸念がある。「デイサービスを『行って寝ていればいい』と職員に説得されて仕方なく使った」。サ高住の業界団体にこんな苦情も集まる。
日本社会事業大の井上由起子教授は「国も学者もこれほど介護施設化すると考えていなかった。一部のサ高住が介護報酬を運営の調整弁に使うと、介護保険制度の持続性が揺らぐ」と警戒する。運営費は家賃のみで吸収するのが筋だとの立場だ。東京通信大の高橋絋士教授は「高齢者への家賃補助を検討すべきだ」と訴える。
すべてのサ高住が過剰に介護をしているわけではないが、個別の実態を捉えるのは難しい。一般社団法人の高齢者住宅協会は「介護状況の開示や法令順守を事業者に強く促していく」という。
民間主導のサ高住は行政も運営状況や整備計画を把握していない。それがサ高住の乱立につながり、介護報酬で経営を成り立たせようとする動きを招く。介護施設との役割分担を明確にし、立地の最適配分も考えなければ悪循環は断ち切れない。