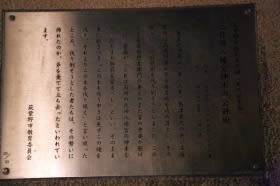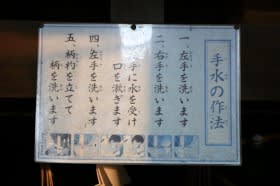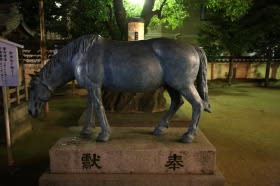鵜戸神宮(日南)(1) 参拝日 2014.1.5(日)[HomePage][Yahoo!地図]


・こちらは宮崎県南部の海岸沿い。宮崎駅前よりバスに乗り1時間半ほど揺られて目的地にたどり着きました。神社最寄りのバス停より一つ手前でバスを降り、歩いて神社へ向かうことに。



・海際にたつ大きな鳥居と神社の看板。

・写真を撮っていてふと足元を見ると、ネコがいました。


・鳥居をくぐり、海際の道を進む。

・途中見かけた民宿の看板。「伊勢えび料理生造り定食3150円~(時価)」が気になります。

・民家の敷地にあった小さな祠。


・太陽が照り輝き、歩いていると汗ばむような陽気です。正月とはとても思えず。


・坂の上へとのびる長い石段。今回は階段ではなく海沿いの道を歩くことに。


・茂みの中に見つけたお地蔵様。


・穏やかな海の様子。海水は透き通ったきれいな青色をしています。


・しばらく歩くと、波打ち際の地形に変化が見られます。


・この不思議な地形は『鵜戸千畳敷奇岩』と呼ばれる岩棚です。

・この眺めは、もし神社最寄りのバス停までバスに乗っていたら見られなかった風景。


・道はやがて上り坂に。海の反対側は崖になっています。


・鵜戸千畳敷奇岩の標柱や解説板。

・坂の上からの海の眺め。


・岩山の合間を通過。


・道の途中に変わった形の灯台がたっていました。これは『鵜戸埼灯台』。解説板によると石灯籠の形の灯台は非常に珍しいとのこと。


・灯台の周りを一周。それほど大きくはありません。

・ここまで1kmほど歩いたでしょうか。「鵜戸神宮この先300m直進」の看板が現れました。


・道は上り坂から下りに転じ、その先に駐車場が見えてきました。


・駐車場の向こうに楼門などが見え、やっと神社の境内らしい雰囲気に。

・車のお祓いを行う御祈祷所。

・『鵜戸山の磨崖仏』の方向を示す石盤。道が険しそうだったので寄るのはやめておきました。
(続く)
[Canon EOS 5D3 + EF24-105L]


・こちらは宮崎県南部の海岸沿い。宮崎駅前よりバスに乗り1時間半ほど揺られて目的地にたどり着きました。神社最寄りのバス停より一つ手前でバスを降り、歩いて神社へ向かうことに。



・海際にたつ大きな鳥居と神社の看板。

・写真を撮っていてふと足元を見ると、ネコがいました。


・鳥居をくぐり、海際の道を進む。

・途中見かけた民宿の看板。「伊勢えび料理生造り定食3150円~(時価)」が気になります。

・民家の敷地にあった小さな祠。


・太陽が照り輝き、歩いていると汗ばむような陽気です。正月とはとても思えず。


・坂の上へとのびる長い石段。今回は階段ではなく海沿いの道を歩くことに。


・茂みの中に見つけたお地蔵様。


・穏やかな海の様子。海水は透き通ったきれいな青色をしています。


・しばらく歩くと、波打ち際の地形に変化が見られます。


・この不思議な地形は『鵜戸千畳敷奇岩』と呼ばれる岩棚です。

・この眺めは、もし神社最寄りのバス停までバスに乗っていたら見られなかった風景。


・道はやがて上り坂に。海の反対側は崖になっています。


・鵜戸千畳敷奇岩の標柱や解説板。

・坂の上からの海の眺め。


・岩山の合間を通過。


・道の途中に変わった形の灯台がたっていました。これは『鵜戸埼灯台』。解説板によると石灯籠の形の灯台は非常に珍しいとのこと。


・灯台の周りを一周。それほど大きくはありません。

・ここまで1kmほど歩いたでしょうか。「鵜戸神宮この先300m直進」の看板が現れました。


・道は上り坂から下りに転じ、その先に駐車場が見えてきました。


・駐車場の向こうに楼門などが見え、やっと神社の境内らしい雰囲気に。

・車のお祓いを行う御祈祷所。

・『鵜戸山の磨崖仏』の方向を示す石盤。道が険しそうだったので寄るのはやめておきました。
(続く)
[Canon EOS 5D3 + EF24-105L]