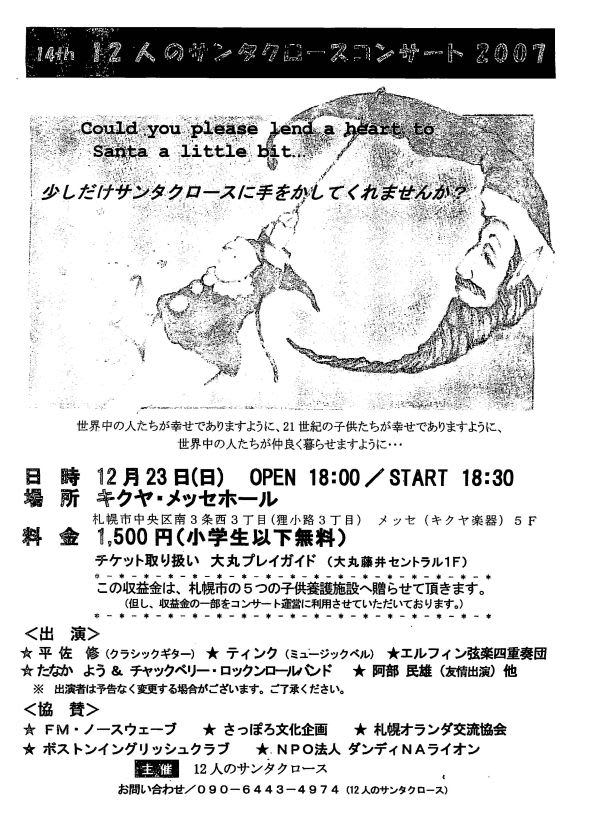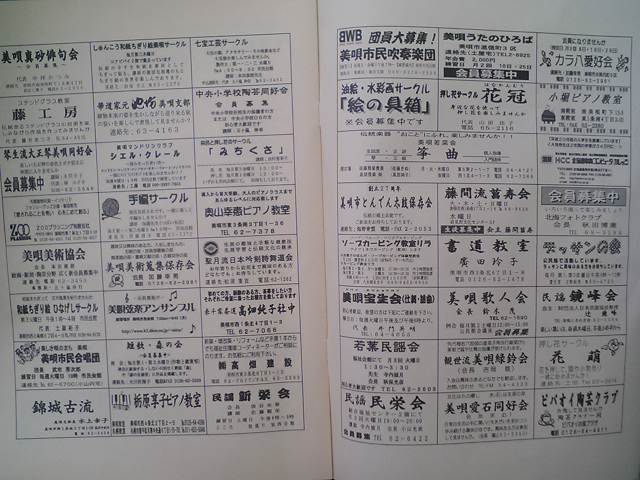2007年 演奏記録 まとめ
2007年の終わりにあたり、今年の【演奏記録】を振り返ってみたいと思います。まずは印象に残った演奏会ベスト3を。
【1】弾いててゾクゾクしたで賞
オーケストラ・アンサンブル・ブリランテ 第1回 定期演奏会
特にブラ1は奇蹟の演奏でした。この『ゾクゾク感』を味わいたいがために楽器を続けているようなものです。団体自体は残っているものの、この団体名での第2回定演はもう無くなってしまったのが、ちょっと寂しい気がします。
【2】裏方大変だったで賞
夕張メロンオーケストラコンサート 1・2
演奏そのものではなく、その裏方(インスペクター・仕切り役)として大忙しだったイベント。自分としてはもう二度とあんな仕事は出来ない、という限界を超えた仕事っぷりでした。「次回もよろしく♪」とよく声をかけられますが、次回は他の方にお願いします。
【3】曲に思い入れあったで賞
札幌市民オーケストラ 第64回アトリエコンサート
ブラームスのバイオリンとチェロのための二重協奏曲。死ぬまでに一度は弾きたい憧れの曲を弾く事ができました。感謝。次はマーラー『復活』?
その他のトピックスを以下に。
★年間本番数過去最高を更新(43回)
昨年の41回で、「もうこれ以上つめこむのは無理!」と思いましたが、あっさり自己記録を塗り替えてしまいました。改めて、「もうこれ以上つめこむのは無理!」 来年はさすがに減る、はず。
★異文化コミュニケーションの増進
私自身、今年も新たな出会いがいろいろありましたが、それ以上に、SBYオケ・夕張メロンオケ・ブリランテ等で、私から見た知り合い同士が友達になったりと、異なる団体間の交流が活発でした。
★マイナー曲演奏
交響曲でいうと、リムスキー=コルサコフ2番『アンタール』、シベリウス6番、スヴェンセン2番等々、あまり演奏されない曲の演奏機会が多かったような気がします。有名曲をやり尽くすと、今後少しずつこういう流れになっていくのかもしれません。
★初めての曲目解説執筆
今年になって演奏会プログラムの曲目解説というものを初めて担当しました。ブラームスのドッペル@札幌市民オケ、チャイコの眠りの森@苫小牧、エルガーの威風堂々&ニムロッド@室蘭の三件です。やってみて初めて分かる大変さ。
★チェロデビュー
地味にチェロデビューしました。チェロ弾きとしてのキャリアのスタートです。今年はニ件のみですが、今後はどんどん増える、かも?
さて来年は、何と言っても『小林研一郎指揮 炎の第九in千歳』が目玉です。今から楽しみです。来年も事故無く演奏活動ができますように。
2007年の終わりにあたり、今年の【演奏記録】を振り返ってみたいと思います。まずは印象に残った演奏会ベスト3を。
【1】弾いててゾクゾクしたで賞
オーケストラ・アンサンブル・ブリランテ 第1回 定期演奏会
特にブラ1は奇蹟の演奏でした。この『ゾクゾク感』を味わいたいがために楽器を続けているようなものです。団体自体は残っているものの、この団体名での第2回定演はもう無くなってしまったのが、ちょっと寂しい気がします。
【2】裏方大変だったで賞
夕張メロンオーケストラコンサート 1・2
演奏そのものではなく、その裏方(インスペクター・仕切り役)として大忙しだったイベント。自分としてはもう二度とあんな仕事は出来ない、という限界を超えた仕事っぷりでした。「次回もよろしく♪」とよく声をかけられますが、次回は他の方にお願いします。
【3】曲に思い入れあったで賞
札幌市民オーケストラ 第64回アトリエコンサート
ブラームスのバイオリンとチェロのための二重協奏曲。死ぬまでに一度は弾きたい憧れの曲を弾く事ができました。感謝。次はマーラー『復活』?
その他のトピックスを以下に。
★年間本番数過去最高を更新(43回)
昨年の41回で、「もうこれ以上つめこむのは無理!」と思いましたが、あっさり自己記録を塗り替えてしまいました。改めて、「もうこれ以上つめこむのは無理!」 来年はさすがに減る、はず。
★異文化コミュニケーションの増進
私自身、今年も新たな出会いがいろいろありましたが、それ以上に、SBYオケ・夕張メロンオケ・ブリランテ等で、私から見た知り合い同士が友達になったりと、異なる団体間の交流が活発でした。
★マイナー曲演奏
交響曲でいうと、リムスキー=コルサコフ2番『アンタール』、シベリウス6番、スヴェンセン2番等々、あまり演奏されない曲の演奏機会が多かったような気がします。有名曲をやり尽くすと、今後少しずつこういう流れになっていくのかもしれません。
★初めての曲目解説執筆
今年になって演奏会プログラムの曲目解説というものを初めて担当しました。ブラームスのドッペル@札幌市民オケ、チャイコの眠りの森@苫小牧、エルガーの威風堂々&ニムロッド@室蘭の三件です。やってみて初めて分かる大変さ。
★チェロデビュー
地味にチェロデビューしました。チェロ弾きとしてのキャリアのスタートです。今年はニ件のみですが、今後はどんどん増える、かも?
さて来年は、何と言っても『小林研一郎指揮 炎の第九in千歳』が目玉です。今から楽しみです。来年も事故無く演奏活動ができますように。