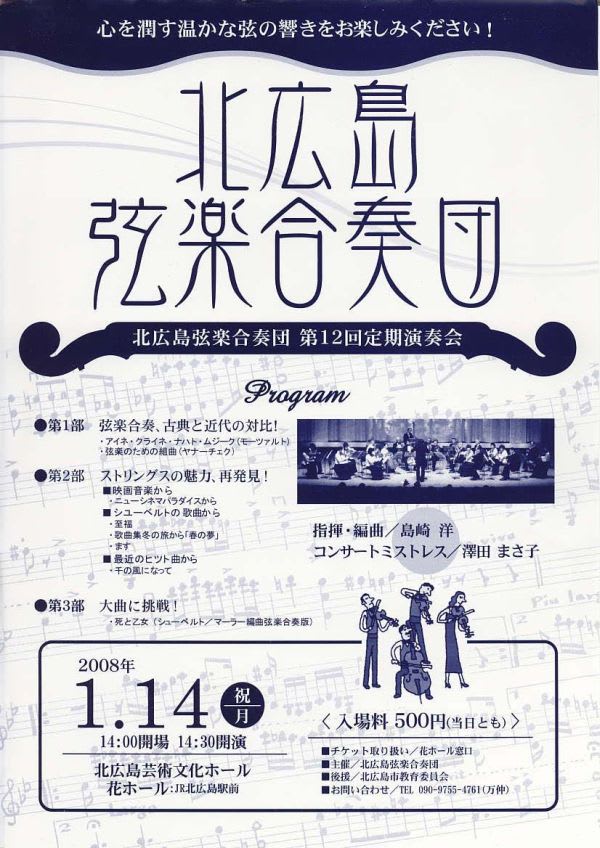平成20年度 室蘭工業大学 入学宣誓式
2008.4.4(金)9:30入場開始・10:00式開始, 室蘭工業大学 体育館, 関係者のみ
指揮 あつお, 演奏 室蘭工業大学管弦楽団, パート 1st Violin
<卒業生入場>
1.内藤淳一 式典のための行進曲「栄光をたたえて」
 2.B.グレイ 「サンダーバード」のテーマ
2.B.グレイ 「サンダーバード」のテーマ
3.シベリウス 「カレリア」組曲より 行進曲風に
4.シューベルト 軍隊行進曲
※1→2→3→4→2→3→4
<式中>
作詞 田中章彦 作曲 金田締元 室蘭工業大学 学歌 (歌メロディー入りVer. 1番のみ)
<卒業生退場>
※1→2→3
・今回は8時集合・合奏開始予定が8時20分チューニング。これでも結構マシな方。
 ・小さなバスドラムでは望みの音が出ない。しかし大きいバスドラムではたたき手が足りない。という訳で、苦肉の策のバスドラム(大)を床に直置き+フットペダル。
・小さなバスドラムでは望みの音が出ない。しかし大きいバスドラムではたたき手が足りない。という訳で、苦肉の策のバスドラム(大)を床に直置き+フットペダル。
 [撮影:くま]
[撮影:くま]
・本番前に、控え室のトレーニングルームにて衝撃の写真が撮影されました。ランニングマシンで戯れる人たち。あまりに高速で、足が消えてるー!!
●栄光:今回新たに加わった管打中心の曲。Vc以上はお休み。
●カレリア:リハ時にとんでもなく速いテンポになり、本番どうなることかと思いましたがほどほどの速さに。しかしあの快速テンポも捨てがたい。
●軍隊:特に詳しい打ち合わせをしたわけでもないのに、演奏途中で入場が完了し、指揮者の合図により区切りのいいところでピタッと演奏終了。オケの心が一つになった瞬間。指揮が回を重ねるごとに、目に見えて様になってきています。その調子。
 ●学歌:毎回出だしが上手く入れるかドキドキしてしまいます。今回は無事通過。
●学歌:毎回出だしが上手く入れるかドキドキしてしまいます。今回は無事通過。
・会場内は咳払いをすれば響き渡るような、緊張感がほのかに漂う空気。卒業式とはまた全然違ったさわやかな雰囲気です。
・学長告辞:大学の歴史について、ヨハネ・パウロ二世来日時の言葉の紹介、来年度からキャンパス内全面禁煙になるのでタバコの習慣はつけないように、など。
・朝、家を出るときは曇り空の肌寒い天気でしたが、式を終えて外へ出てみると入学式にふさわしい穏やかなポカポカ陽気に。さて、今年はどんな新入生が入ってくるでしょうか。
 ・客数約1500名[目測]:父兄の立ち見あり。卒業式よりも若干多いかもしれません。式後に、今回は来賓として参加した某名誉教授と話す機会があり、「毎年のように式に参加しているが、今回の演奏は近年になく良い演奏だった」とのお褒めの言葉をいただきました。どうも「カレリア」が良かったらしい。
・客数約1500名[目測]:父兄の立ち見あり。卒業式よりも若干多いかもしれません。式後に、今回は来賓として参加した某名誉教授と話す機会があり、「毎年のように式に参加しているが、今回の演奏は近年になく良い演奏だった」とのお褒めの言葉をいただきました。どうも「カレリア」が良かったらしい。

2008.4.4(金)9:30入場開始・10:00式開始, 室蘭工業大学 体育館, 関係者のみ
指揮 あつお, 演奏 室蘭工業大学管弦楽団, パート 1st Violin
<卒業生入場>
1.内藤淳一 式典のための行進曲「栄光をたたえて」
 2.B.グレイ 「サンダーバード」のテーマ
2.B.グレイ 「サンダーバード」のテーマ3.シベリウス 「カレリア」組曲より 行進曲風に
4.シューベルト 軍隊行進曲
※1→2→3→4→2→3→4
<式中>
作詞 田中章彦 作曲 金田締元 室蘭工業大学 学歌 (歌メロディー入りVer. 1番のみ)
<卒業生退場>
※1→2→3
・今回は8時集合・合奏開始予定が8時20分チューニング。これでも結構マシな方。
 ・小さなバスドラムでは望みの音が出ない。しかし大きいバスドラムではたたき手が足りない。という訳で、苦肉の策のバスドラム(大)を床に直置き+フットペダル。
・小さなバスドラムでは望みの音が出ない。しかし大きいバスドラムではたたき手が足りない。という訳で、苦肉の策のバスドラム(大)を床に直置き+フットペダル。 [撮影:くま]
[撮影:くま]・本番前に、控え室のトレーニングルームにて衝撃の写真が撮影されました。ランニングマシンで戯れる人たち。あまりに高速で、足が消えてるー!!
●栄光:今回新たに加わった管打中心の曲。Vc以上はお休み。
●カレリア:リハ時にとんでもなく速いテンポになり、本番どうなることかと思いましたがほどほどの速さに。しかしあの快速テンポも捨てがたい。
●軍隊:特に詳しい打ち合わせをしたわけでもないのに、演奏途中で入場が完了し、指揮者の合図により区切りのいいところでピタッと演奏終了。オケの心が一つになった瞬間。指揮が回を重ねるごとに、目に見えて様になってきています。その調子。
 ●学歌:毎回出だしが上手く入れるかドキドキしてしまいます。今回は無事通過。
●学歌:毎回出だしが上手く入れるかドキドキしてしまいます。今回は無事通過。・会場内は咳払いをすれば響き渡るような、緊張感がほのかに漂う空気。卒業式とはまた全然違ったさわやかな雰囲気です。
・学長告辞:大学の歴史について、ヨハネ・パウロ二世来日時の言葉の紹介、来年度からキャンパス内全面禁煙になるのでタバコの習慣はつけないように、など。
・朝、家を出るときは曇り空の肌寒い天気でしたが、式を終えて外へ出てみると入学式にふさわしい穏やかなポカポカ陽気に。さて、今年はどんな新入生が入ってくるでしょうか。
 ・客数約1500名[目測]:父兄の立ち見あり。卒業式よりも若干多いかもしれません。式後に、今回は来賓として参加した某名誉教授と話す機会があり、「毎年のように式に参加しているが、今回の演奏は近年になく良い演奏だった」とのお褒めの言葉をいただきました。どうも「カレリア」が良かったらしい。
・客数約1500名[目測]:父兄の立ち見あり。卒業式よりも若干多いかもしれません。式後に、今回は来賓として参加した某名誉教授と話す機会があり、「毎年のように式に参加しているが、今回の演奏は近年になく良い演奏だった」とのお褒めの言葉をいただきました。どうも「カレリア」が良かったらしい。