1
わたしたちは一般には、日頃映画を観たり音楽聴いたり本を読んだりしてもそれらの感想を書き記すことはない。芸術やスポーツなどを娯楽のようなものとして受けとめていて、一時の憂さを晴らしたりその現場の現在そのものを楽しみ味わうものと見なしているように思う。そういう作品やスポーツを味わう場合、わたしたちの中に印象や感動に伴ってなにか残余のものが漂うが、一般にはそれらを心に沈めてまた日常の生活世界に帰っていく。
わたしはそれとは違ったことをここでしようとしている。また、ネットやブログなどの普及により普通の人々が鑑賞した作品について書き記すということも増えてきているような気がする。しかしそうだとしても、この一般に「批評」と呼ばれる専門化した世界は、学校の感想文を別にすれば、普通の生活者にはほとんど関わり合いのない世界ということになる。現在の「批評」は、おそらく近代の小林秀雄をその本格的な発祥としているが、なぜ「批評」と呼ばれる世界が成り立つのか?作品は、読者(観客)の数だけ違った表情を見せる。普通の読者(観客)は、そこで終わる。ということは味わった印象や感動を心の底に沈めてまたふだんの生活に戻っていく。
そのように終わることなく、専門的な「批評」という世界が成り立つのは、次のような事情によるのではないか。作品を味わう人それぞれの固有の生い立ちや感受が、作品を通過する。作品は、人それぞれの様々な屈折率によって人それぞれの内に屈折したイメージを花開かせる。人それぞれといっても、作品の全体的な印象として、明るいと暗いのように対立することはなく大まかな点では共通するだろう。しかし、「批評」は、そのような印象やイメージの個別性で終わりたくないのである。この点から見て批評という世界は、人それぞれの個別的なイメージをかき分けて、固有の作者の固有の作品というひとつの普遍的なイメージの場所にたどり着こうとする言葉の表現の世界ではないか。では、なぜそういう批評の行為が成り立つのだろうか。作者は、単に職業だからではなく、わたしたちの日常の人と人との関わり合いのように、心のどこかで読者の存在を意識して言葉の世界を作り上げ、差し出している部分があるだろう。したがって、読者としてその部分に対話するように言葉を返すという批評の行為が成り立ち得ると思われる。
2
坂口恭平の『現実宿り』を少しずつ読み重ねて、やっと読み終えた。読みながらこれは何だろうというふしぎな感じで、気分は不明の靄に包まれていた。そんなに退屈ではなかった。それはこの作品が、三層から成っているからだと思われる。特に終わりの方ではその三層が交差したり、溶け合ったりしてくる(それに似た変容は『家族の哲学』という作品の終わりの方でもあったように記憶している)が、この三層が交互に現れることが場面の転換になっており、一般的の物語の持つ、現実に近い現実的な物語の枠組みや起伏の希薄さを埋めたり、それを代替するものになっている。こうして、一般の物語性というものが希薄なこの作品は、単調さを免れているように見える。
その三層とは、砂である「わたしたち(わたし)」の層、最初はクモだったのが鳥に食べられて鳥の目の一部と化した「おれ」の層、「わたし」や「モルン」の登場する割と現実世界の風景に近い層、である。
欧米の波を被った近代以降の物語は、ある家族や地域で育った固有の年輪を持つ、現在を物質的かつ精神的に呼吸する個が、自己を対象化して作者に変身して、物語という幻想の舞台に語り手や登場人物を派遣して、作者の抱くあるモチーフやイメージを貫徹しようとする。主に物語世界の外に居て、物語を言葉(文字)として書き記していくのは作者であるが、作者に派遣された作者の分身たちである語り手や登場人物たちは、物語世界の渦中で作者の抱くあるモチーフやイメージを貫徹しようとしたりそれに修正を加えようとしたりしながら物語世界を造型していくのに貢献する。作者は分身となったり背後に居たとしても、語り手や登場人物たちが言葉を繰り出すとき、背後の黒子のような位置に居てそれらの言葉の選択や構成にも加わり、また言葉(文字)を書き記しているから、実際には見分け難いとしても物語世界には作者の癖や好みのような無意識的な部分も足跡として残されている。また、時代のファッションや風物やイメージや考え方も物語世界の要請であると同時に作者の選択として物語世界に現れて来る。村上春樹の作品で何度か出会った、主人公の「チノパンツ」もそうしたものとしてある。なぜこのような回りくどいことを枕詞として持ってくるかといえば、他の芸術作品も同様だが、今もって作者・語り手・登場人物が織り成す物語世界の構造についての共通認識が依然としてなく、それぞれが勝手な切り取りや基準で作品を印象批評レベルで捉えがちだからである。
しかし、この『現実宿り』という作品は、それら近代以降の一般的な物語概念から少し外れているように見える。例えば、「砂」を語り手にしたり、砂が語ったりするなど、このような作品世界の表現は、外国は知らないけど、わが国ではほとんど類例がないように見える。
宮沢賢治は詩集『春と修羅』の「序」で次のように記している。
わたくしといふ現象は
假定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといっしょに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち、その電燈は失はれ)
これらは二十二箇月の
過去とかんずる方角から
紙と鑛質インクをつらね
(すべてわたくしと明滅し
みんなが同時に感ずるもの)
ここまでたもちつゞけられた
かげとひかりのひとくさりづつ
そのとほりの心象スケッチです
(「序」の一、二連)
まず、「わたし」をある抽象度で位置付け、そして、自らの言葉や詩を「心象スケツチ」と位置付けている。こういう論理性や詩的な表現は、当時では目新しく異質な言葉や詩だったように思われるが、このような言葉の出所は、宮沢賢治の生い立ち以外では化学や科学の経験と仏教の経験が大きく関与しているように思われる。坂口恭平の『現実宿り』という物語性が希薄な作品も、作者である「わたし」の「心象スケッチ」と捉えた方が分かりやすいと思う。
ところで、わたしたちは現在では、職業的な物語の作者についてもネットを通していろんな情報を目にすることができる時代になってしまった。読者としては、作者の言葉やインタビューなどが、作者の作品に込めたイメージやモチーフを、それらのひとつの大きな主流にできるだけ沿ったものとして味わう手掛かりになるということもある。ここに、『現実宿り』に関する坂口恭平のツイッターの言葉がある。
(2016.5.15)
現実宿り推敲は第30章まで完了。全部で85章まであるので、まだまだだが、推敲が面白い。いい作品になるんじゃないかと思うが、不思議な作品である。自分の思いがまったく入っていない作品。今年は変な年だ。でも悪くない。わからないけど、不安じゃない。あの子供の頃の感じに似てる。
(2016.5.15)
震災前に砂が語り手の800枚の小説書いたので、つい、震災後に感情入れて書こうとしてしまいそうだったが、そんなときは避難に必死になり今少し落ち着いて、いざ書こうとすると感情がない。おかげてただの客観的な「推敲さん」が登場してくれている。もうすでにテキストは31万字ある。ただ直すだけ
(2016.6.10)
独立国家のつくりかた、から、現実宿り、までの過程をうまく説明できない。なんでこうなっているのか自分でもよくわからない。いま、何に興味があるの、と聞かれても、わかりませんとしか言えない。興味関心で書くことをやめてから、大変になった。なぜか書くことは捗っているけど。
(2016.8.05)
とにかくぼくはプロットも構成もそもそも着想自体なく鬱のまま書き始めているので何がなんだかわからないまま書いている。書かないと死にそうだから書いているだけなので、今日の文章教室ではそのことだけを伝えます。きっとただみんなほっとするだけの会になると思います。才能の問題ではありません
(2016.10.14)
新作「現実宿り」は10月27日に発売されます。今年の1月に鬱で死にそうになっていたときに頭の中が砂漠になって布団の中でもがきながら書いた本です。自分でも何を書いたのかわかっていないので買って読んで電話で感想ください。予約開始中
(2016.10.24)
雨宿りという言葉は雨がただの避けるものではないということを示していて、気になっていた。雨音聞きながら寝ると気持ちいいし、雨の日に部屋にいると安心する。軒先を宿だと思う感覚も面白いし、軒先から見る雨は自分を守る生きた壁みたいに見えて何かが宿っているようにも見える。
(2016.10.24)
という「雨宿り」という言葉に対しての興味から、僕の仕事もただ現実からの避難所を作りたいわけじゃなく、一つそういった軒先のような空間があれば、現実に対する目も変化するのではないか、なんてことを考えながら、雨宿りから着想して「現実宿り」という造語をつくりましたー。
(2016.12.03)
「現実宿り」昨日久しぶりに数ページ読み返してみたが僕が書いたと思われる箇所がほとんどなくびっくりした。ほんと何度、ページ開いても不思議な感覚です。よく本になったなあと。そして、よくぞ他の人が読んでくれてそれぞれにいろいろ僕にくれたもんだなあと。僕に主題がないどころか僕が書いてない
(2016.12.08)
僕の場合、資料などは一切、入手しないでただ書く。目をつむらないで、目を開かないで、ぼんやりとしたあたりに、窓があって、そこからすかしてみるみたいな感じだろうか。嘘は書いちゃいけないと思っているので、創作した部分は結局最後には消すことになる。でも、そのまま書くと、ほんとむちゃくちゃ
できるだけ「作者」と「作品」の実像に迫りたくてたくさんツイートを引用した。坂口恭平のツイートを読むと、彼が「作者」に変身し、出来上がる前の作品の舞台を眺めたり、出来上がった後の作品世界を見回したときの表情や位置が表現されている。
中でも、「プロットも構成もそもそも着想自体なく鬱のまま書き始めている」「鬱で死にそうになっていたときに頭の中が砂漠になって布団の中でもがきながら書いた本です。自分でも何を書いたのかわかっていないので買って読んで電話で感想ください。」「『現実宿り』昨日久しぶりに数ページ読み返してみたが僕が書いたと思われる箇所がほとんどなくびっくりした。」、これらを坂口恭平の嘘偽りのない(とわたしには思われるが)ツイートと見なせば、この作品は一般的な作者の一般的な物語作品とは違っている。僕が書いたとは思えないというような発言を真面目に言われたら、わたしたち読者としてはびっくりするほかないだろう。この作品は、やはり先に述べたように虚構という物語性の希薄な、作者である「わたし」の切実な「心象スケッチ」と見なすべきだと思う。といっても、 「全部で85章まである」とツイートにはあるが、作品としては70章で終わっている。推敲の過程でずいぶん切り整えられて作品となっているのかもしれない。
そして、推測するに、作者は、押し寄せてくるイメージの波や洪水に放心したように浸かってただ記述しているのかもしれない。あるいは別の言い方をすれば、作者は一般に誰でも言葉に憑かれるように表現しているのだろうが、この作者の場合は巫女やシャーマンのように強度にイメージや言葉に憑かれるよう表現しているのかもしれない。だから表現から離れて振り返ると、これは誰が書いたのかという言葉になるのだろう。
わたしは、作者(坂口恭平)が抱えている、一般には病気と見なされている「躁鬱病」がどのようなものかよくわからない。前作の『家族の哲学』でそれに触れた描写に出会ったと思う。ただ、作者は、作品の中、作品の言葉としては、それを病としては見なしていなかったように思う。『家族の哲学』もこの『現実宿り』も、絶えず間欠的に襲ってきては反復する「躁鬱病」を抱えた「わたし」の、おそらく襲うように寄せてくるイメージ群の渦中で、前者は主に家族という現実世界を舞台として、後者は主に内面世界を舞台として、「心象スケッチ」されたものだと思う。
その「心象スケッチ」された寄せるイメージ群の一つ一つや相互のつながりは、作者でも分からないのが多いのかもしれないが、それらの反復されてきたイメージの感触や色合いや強度などはよくわかっているのではなかろうか。そして、「心象スケッチ」を書き続ける、描写し続けることが、「病」を乗り超えようという意志となっているように見える。
もちろん、わたしたち読者にはいずれもわかりようがない。ただ、物語の三層が進みゆく中で、砂や鳥の目やわたしが変幻し、三層が交差したり溶け合ったりして物語の終局を迎える。それでも、作品の中には、イメージの現れ方や作者よって固執された「時間」や「記憶」や「森の夢」などの言葉がある。たぶん、書き終えて醒めた状態の作者でもその作品世界に踏み込むのが難しいような、うまく対話できないようなイメージ群を記述してわたしたち読者の前に差し出しているのだろう。わたしたち読者は、難しい読みと対話を促されているのかもしれない。
最新の画像[もっと見る]
-
 水詩(みずし) #5
1週間前
水詩(みずし) #5
1週間前
-
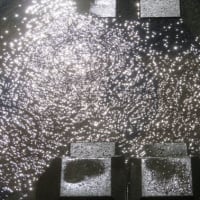 画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
2週間前
画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
2週間前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
3週間前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
3週間前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
3週間前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
3週間前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
3週間前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
3週間前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
-
 水詩(みずし) #4
1ヶ月前
水詩(みずし) #4
1ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます