宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の一節(賢治の「手帳」の画像によると、「ヒドリノトキハナミダヲナガシ」というように確かに「ヒドリ」と書いてある)を巡って「ヒドリ(日取り)」か「ヒデリ(日照り)」か、あるいはまた「ヒトリ」かという論争があるのを初めて知った。
わたしなら、「ヒドリ」が「ヒデリ(日照り)」ではないとしても、何らかのよくないことを指示している位で済ませる。つまり、「ヒドリ」が「ヒデリ」か「ヒドリ」か、あるいはまた「ヒトリ」かということの検討・考察を無意味とは思わないけれど、そこには深入りする気はない。作品にとって本質的なこととは思えないからだ。
「雨ニモマケズ」のWikipediaの「略年譜」によると、1931年「9月28日 - 花巻に帰り、再び療養生活を送る。」とあり、亡くなる二年ほど前に当たるこの年の11月に「手帳に『雨ニモマケズ』を書く。」とある。『銀河鉄道の夜』などは何度も手を入れているが、療養生活に入っていたようだからそんな推敲の余裕はなかったのかもしれない。
「雨ニモマケズ」のWikipediaに、「ヒデリ」か「ヒドリ」かという項目が設けられてまとめが載っている。この問題から少し足を伸ばしてみる。
明治期からの標準語政策とその普及の過程には、沖縄の「方言札」に限らず様々な悲喜劇があったようだ。現在では、大都市に地方から流入してきたときに起こるその悲喜劇はほぼ解消していると思う。それは学校教育やテレビ等による共通語の普及とこの列島社会の高度化や均質化と対応していることだろう。わたしたちは、いわゆる具体的な地域性を喚起する地域語(方言)から、現代では主要に学校という場を通して均質な社会性に対応する共通語を学び身に付けていく。後振り返れば、そのことは自分の中でシームレスなものに見えるのかもしれない。しかし、いろいろな齟齬(そご)があったというようなうっすらとした記憶はあるが、自分の体験した切実さの現場はもうほとんど忘れてしまっている。わたしたちは、自分の家族やその周囲という小さな世界から学校という画一的で均質な世界へ入り込んでいくのと対応して、方言と共通語の接続、使い分けなどを行わざるを得なくなる。それはそんなにスムーズに進んできたわけではないような気がする。また、自分の中から方言が消えても共通語を喋る抑揚などに方言のそれが保存されているということがありそうに思う。
人々は、明治期以来方言と共通語という二重性を言葉において生きてきた。現在では、両者の相互浸透により方言はもうずいぶん灰汁抜きになっている。つまり、共通語の方に近づいている。そうして、方言と共通語というよりも家族内の身内言葉と学校などの小社会での余所行き言葉の二重化のようになってしまっている。賢治の時代も同様の二重性だったと思うが、方言と共通語の間の断層は現在と比べてとても大きかったものと想像する。
ところで、賢治の地では「ヒデリ」と「ヒドリ」は区別された言葉らしい。つまり、地域語として一般に互いの語が移行し合うような関係にはないということである。しかし、書き言葉としてではなく話し言葉としてなら、一般的に「ヒドリ」と「ヒデリ」は互いに移行し合うような関係に見える。言いかえると、ゆっくり明確に喋ると「ヒドオリ」や「ヒデエリ」と区別されて聞こえるが、その言葉を普通に早口で話す、あるいは英語を喋るように話すと、その過程で母音の[オ]や[エ]の部分は脱落して、その部分は飛び石を飛ぶ石と石との間の間隔のように飛び越されていって同一の飛び方として同一化できるような曖昧さがある。曖昧に聞こえる話し方をすると、山(やま)と邪魔(じゃま)でも同様で、無数にその可能性が考えられる。それを防いでいるのは、話題や話の流れである。
わたしたちの日常話す言葉は、相手の言葉によくわからない部分があっても相槌を打つこともあるし、話の流れから曖昧に聞こえた言葉を察知することもある。また、相手が言葉を話すのに少し障害を抱えていてはっきりした言葉として話せない人であっても、長く付き合っていれば最初はまったくわからないとしても、次には例えば「ヒデリ」と「ヒドリ」の境目辺りのよくわからないあいまいさに聞こえ、次第に相手の話す言葉が「ヒデリ」か「ヒドリ」として分離されてわかってくるということがあるような気がする。
もちろん、ここで問題になっているのは話し言葉ではなく書き言葉の世界である。しかし、ひとりの人間の中に言葉は総体としてあり、その言葉には話し言葉も書き言葉もあるし、地域語や共通語がある。そして、それらは互いに関わり合っているはずである。人は、育っていく過程で普遍の言葉から汲み上げるようにしてひとりひとり固有の色合いに言葉を染め上げていく。(註.1)によると、
一つは、「毘沙門天の宝庫」(「口語詩稿」)という作品の下書稿において、「旱魃」という語にルビを振ろうとして、「ひど」まで書いて「ど」の字を消し、続けて「でり」と書いているのです。
ところが、現実に「ひどり」という形で残されてしまった例が、「〔雨ニモマケズ〕」以外にも存在するのです。
下の画像は、童話「グスコーブドリの伝記」が、1932年(昭和7年)に最初に『児童文学』という雑誌に発表された際の誌面の一部で、『入沢書』p.54に掲載されています(傍線は引用者)。 赤い傍線を引いた部分に、「ひどり」と書いてあります。
数少ない事例ではあるけれども、このことを踏まえれば、書き言葉だから地域語(方言)の転訛の問題ではなく、この問題は賢治の中の言葉の固有の癖のようなものから出て来ているように思われる。賢治の中の言葉の詳細な発動の機構はわからないけれども、書き言葉として表現していく過程で、たぶん音として賢治の言葉の耳とでも言うべきものが「ヒデリ」→「ヒドリ」と移行しやすい言葉の傾斜を持っていたように感じられる。フロイトの言い間違い(書き間違い)の研究を若い頃読んだことがある。その背景に人の心的な機制を想定していたように思う。賢治のこの書き間違い(だろうとわたしは見なしている)には、心的な機制というよりも話し言葉と書き言葉が共鳴し合うような言葉の習性が想定できそうだ。
最後に、付け加えとして賢治の地域語(方言)の表現について触れておく。賢治は、地域語(方言)を詩に書き記している。たぶん、その方が作者賢治にとってより切実な具体性や実感を喚起するものだったからではないかと思う。妹トシを悼んだ詩「永訣の朝」にも死にゆく妹トシ(とし子)の話す言葉として表現されている。作者から分離した「わたし」は、語り慣れしてきた共通語の書き言葉の世界にいる。一方、死にゆく妹トシ(とし子)は、その地域性の言葉の中にいる。臨終の場面の妹という存在の強度を「わたし」がそっくりそのまま受けとめ引き受けようとすると言葉はその地の言葉でないといけないという作者賢治の判断が働いているのかもしれない。兄妹である二人は異質な言葉の位相にあったとしても心通わせ合うように描写されている。妹トシが亡くなった後から、その亡くなる現場を呼び寄せて、あるモチーフの下に詩の表現として書き留めているのはもちろん作者賢治であるから、作者はその両者を表現として作品の中に統一されたものとして構成していることになる。
。
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゆとてちてけんじや)
うすあかくいつそう陰惨いんざんな雲から
みぞれはびちよびちよふつてくる
(あめゆじゆとてちてけんじや)
青い蓴菜じゆんさいのもやうのついた
これらふたつのかけた陶椀たうわんに
おまへがたべるあめゆきをとらうとして
わたくしはまがつたてつぱうだまのやうに
このくらいみぞれのなかに飛びだした
(あめゆじゆとてちてけんじや)
(「永訣の朝」部分 青空文庫より)
註.「ヒデリ」か「ヒドリ」かに関するまとめ
1.2010年7月 1日 「ヒデリ」論の私的メモ
http://www.ihatov.cc/blog/archives/2010/07/post_710.htm
2.2010年6月17日 入沢康夫『「ヒドリ」か、「ヒデリ」か』
http://www.ihatov.cc/blog/archives/2010/06/post_709.htm
(ブログ「宮澤賢治の詩の世界」より)
(補註)
ひとりの人間の中には、この世界で育つ過程でその人によって汲み上げられて言葉は総体としてあり、その総体としての言葉には話し言葉も書き言葉もあるし、地域語や共通語があり、それらは互いに関わり合っている。それは個によって汲み上げられた言葉で、外側にある地域語や共通語自体ではない。その人の言葉との固有の関わり合い方や好みや選択性が強いなどがあるはずである。そして、その総体としての言葉の現在は、自覚性として絶えず深められ更新されていくものとしてある。本文で述べていることは、賢治のそうした言葉の総体の中の揺らぎが、作品を表現する過程で現れたのではないかとわたしは見なしている。そして、それ以上の微細な発動の機構については今は言うことはできない。
ところで、わたしたちは言葉と同じように関係の意識としても、吉本さんが構造化して見せた個、対、共同性という位相の異なる三つの位相との関わり合いの意識を持っている。わたしたちは、日々その三つの位相を行きつ戻りつしたり、あるいは自分の精神に引き寄せたりして、考えたり、行動したりしている。したがって、わたしたちは、それらの三つの位相と対応した意識性とともに、対応した言葉も持っていることになる。しかし、時にその自動的、あるいは自然性にまでになった使い分けや推移の機構がふっと揺らぐことがある。次に、わたしの過去の体験を取り出してみる。
わたしがまだ若く高校の教員に成り立ての頃、自宅に帰ってわたしの奥さんにまるで学校という職場でていねいに話すように「・・・・・・です。」のように話してしまった経験がある。あるいは、学校の授業中必死で机に向かっていた生徒から突然「お母さん」と呼びかけられたことがある。ともに、場違いな表現に当たっている。これらはおそらく極度の集中や緊張がもたらしたもので、日頃、関係の意識の異なる三つの位相の場を割と無意識のように使い分けて行動したり言葉を表現したりする機構が、ふっと揺らいだところから現象したものだと思う。生徒の場合で言えば、一瞬「生徒」からある家族の中の「子ども」に変身してしまっている。こういう場違いは、誰にでも一度はありそうに思える。











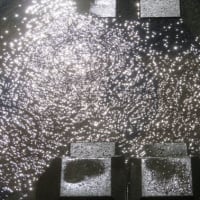








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます