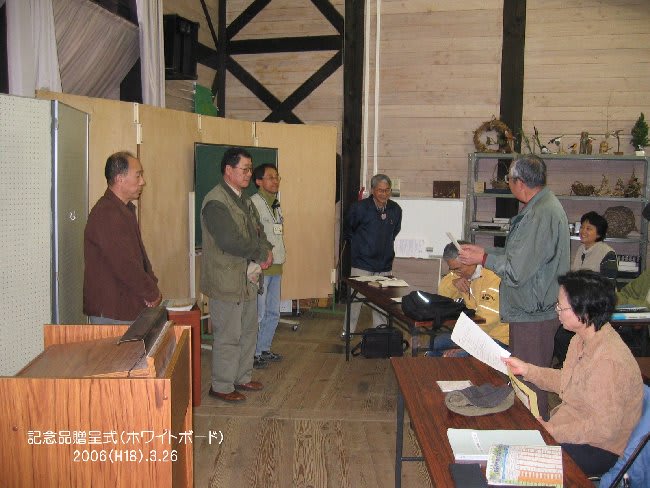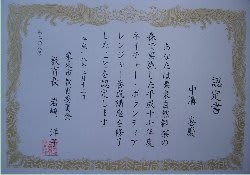20日(土)、栗東自然観察の森での「リーダーステップアップ研修」に参加する。前年度に受講したNVR養成講座に 続いての今年度も研修会に参加することにしている。今日の講義内容は、「花と昆虫」であったが講義のあとに雨でぬかるんだ森の観察道を歩いていると美しい模様のある甲虫類の「ハンミョウ」と出逢う。「ハンミョウ」を漢字では「斑猫」と書くようだが、獲物を追いかけ取り押さえる姿が猫科の動物に似ているため名付けられたという。ただ、獲物を捕獲する姿を見たことはない。人が近づくと素早く飛び上がり、2メートルほど先に着地するのを繰り返す事から、ミチオシエと呼ばれる事もあるらしい。デジカメを向けるとすぐさま飛び立つとため追いかけ、受講生の集団から遅れること10分、やっと撮影に成功する。写真そのものは何とか見られる程度だか撮影できたことが最高の喜びとなる。小さいこの写真では、分かりづらいが写真をクリックして拡大するとはっきりとハンミョウの姿をみることが出来ますよ。
20日(土)、栗東自然観察の森での「リーダーステップアップ研修」に参加する。前年度に受講したNVR養成講座に 続いての今年度も研修会に参加することにしている。今日の講義内容は、「花と昆虫」であったが講義のあとに雨でぬかるんだ森の観察道を歩いていると美しい模様のある甲虫類の「ハンミョウ」と出逢う。「ハンミョウ」を漢字では「斑猫」と書くようだが、獲物を追いかけ取り押さえる姿が猫科の動物に似ているため名付けられたという。ただ、獲物を捕獲する姿を見たことはない。人が近づくと素早く飛び上がり、2メートルほど先に着地するのを繰り返す事から、ミチオシエと呼ばれる事もあるらしい。デジカメを向けるとすぐさま飛び立つとため追いかけ、受講生の集団から遅れること10分、やっと撮影に成功する。写真そのものは何とか見られる程度だか撮影できたことが最高の喜びとなる。小さいこの写真では、分かりづらいが写真をクリックして拡大するとはっきりとハンミョウの姿をみることが出来ますよ。
ハンミョウに関する資料はインターネット上にも数多くあるのでその中から一つをリンクしておきたい。興味がある方はご覧下さい。