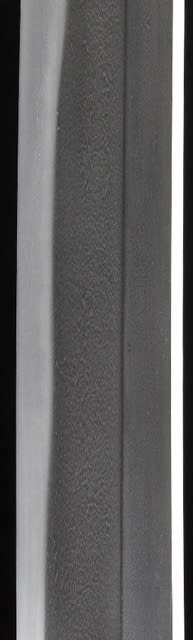剣 家久


剣 家久
室町時代後期天文頃の短剣。肌立つ板目に細直刃。これも、密教に通じた武士の持ち物であろう。剣は、武器というより法具ではなかったかと思うのだが、意外にも研磨が重ねられて身幅が狭まっている遺例が多い。特に戦国時代を遡る作では。江戸時代以降の剣を幾つか紹介してきたが、この戦国時代の剣と比較して見ると違いが良く判ると思う。戦場でも使われているのかもしれない。


剣 家久
室町時代後期天文頃の短剣。肌立つ板目に細直刃。これも、密教に通じた武士の持ち物であろう。剣は、武器というより法具ではなかったかと思うのだが、意外にも研磨が重ねられて身幅が狭まっている遺例が多い。特に戦国時代を遡る作では。江戸時代以降の剣を幾つか紹介してきたが、この戦国時代の剣と比較して見ると違いが良く判ると思う。戦場でも使われているのかもしれない。