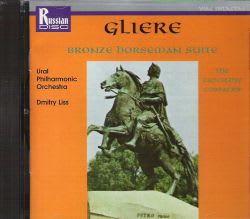グリエール ヴァイオリン協奏曲+交響曲第2番
ヴァイオリン協奏曲ト短調(作品100)~リャトシンスキーによる補筆完成版
1.Allegro moderato
交響曲第2番ハ短調(作品25)
1.Allegro pesante 2.Allegro giocoso 3.Andante con variazioni
4.Allegro vivace
西野優子(ヴァイオリン)
ヨンダーニ・バット指揮 フィルハーモニア管弦楽団
録音: 2000年 (ASV CD DCAA1129)
--------------------------------------------------------------------
20世紀に作曲された最もロマンチックな協奏曲、と言えば、真っ先に浮かんでくるのがラフマニノフのピアノ協奏曲(1~4番)だと思うが、ラフマニノフと同世代の作曲家グリエールも、香り高いロマンにあふれた協奏曲を、実に5曲も残している。
①1938年(作曲者63歳) ハープ協奏曲
②1943年(作曲者68歳) コロラトゥーラ・ソプラノと管弦楽のための協奏曲
③1946年(作曲者71歳) チェロ協奏曲
④1950年(作曲者75歳) ホルン協奏曲
⑤1956年(作曲者81歳) ヴァイオリン協奏曲
いずれも、あまり演奏される機会はないが、ロシア国民学派の作風を受け継いだ色彩豊かな叙情性と、ドイツ・ロマン派風のほの暗い雰囲気を合わせ持ち、心を打つメロディーが続出する魅力作だ。ラフマニノフあたりが好きな人には、文句なしに薦められよう。
ヴァイオリン協奏曲は、作曲者の死の直前に着手された文字通り最後の作品で、第1楽章のスケッチが出来上がった時点で、作曲者は永眠。これを弟子のリャトシンスキーがオーケストレーションを施し、単独楽章の協奏曲として完成させた。
本来は複数楽章を意図した作品なので、形式的には未完成であるが、実際に聴いてみると、未完成という印象を全く与えないほど完成度が高い。グリエールのほかの協奏曲同様、ソロとオーケストラが変幻自在に絡み合う色彩感と、ロマンチックな旋律美、懐かしい叙情性に酔いしれるばかり。まさに「17分30秒の至福」である。
グリエールは16歳でキエフ音楽院に入学した時、最初に習った楽器がヴァイオリンだったということなので、おそらくこのヴァイオリン協奏曲は、人生最後の遺言として残しておきたかった作品なのではあるまいか。そう思って聴くと、さらに感慨深いものがある。
それにしても、時すでに1956年。第2次世界大戦も終わり、すでに人工衛星が打ち上げられている時代に、これほどロマンチックな作品が書かれていたのだ。「最後のロマン派作曲家」と呼ばれている作曲家は何人かいると思うが、グリエールこそ正真正銘のザ・ラスト・ロマンチック・コンポーザーかもしれない。
2002年に発売されたこのCDは、ヴァイオリン協奏曲の世界初録音である。ソロを担当するのは西野優子。わずか10歳でメンデルスゾーンのコンチェルトを演奏してデビュー。以後、日本人若手ヴァイオリニストのホープとして、世界を舞台に活躍している。
指揮者のヨンダーニ・バットはマカオ出身。リムスキー=コルサコフ、グラズノフなどのロシア系作曲家の演奏で高い評価を得ている。フレッシュな東洋人コンビでの新録音は、21世紀におけるグリエール・ルネッサンスの幕開けを予感させる。
CDの後半は、ロシア革命以前の1908年に完成された交響曲第2番。作曲者はまだ33歳と若いが、ロマンチックな作風は若い時であろうと、晩年であろうと変わらない。この曲に関しては、以前、名曲夜話(20)でズデニェク・マーツァルの名演を紹介しているが、このヨンダーニ・バットの演奏はさらにスケールが大きい。
第1楽章は、遅いテンポで地響きを立てて進軍する勇壮なテーマに圧倒されるし、第2楽章では、木管を始めとするオーケストレーションの色彩感と、ラフマニノフを彷彿させる懐かしいホルンの旋律が絶妙な絡みを聴かせる。
第3楽章は、ロシアの民謡をモチーフにした変奏曲で、アダージョの名旋律が聴きどころ。
第4楽章は、快速テンポで疾走する終曲。民族的旋律を交えながら、壮大なクライマックスを形成し、最後はリヒャルト・シュトラウスのアルプス交響曲風のモチーフが現われて幕を閉じる。