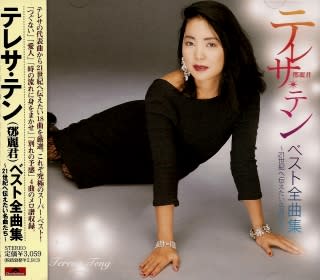★藤圭子 『新宿の女 演歌の星/藤圭子のすべて』
(2013年4月10日発売) MHCL 30048 *オリジナル盤発売日:1970年3月5日
収録曲 01.新宿の女 02.星の流れに 03.あなたのブルース 04.カスバの女 05.命かれても 06.逢わずに愛して 07.夢は夜ひらく 08.柳ヶ瀬ブルース 09.東京流れもの 10.花と蝶 11.長崎ブルース 12.生命ぎりぎり
1970年3月に発売されて以来、オリコン20週連続1位というとてつもないセールスを記録した伝説のアルバム。黒のベルベットに身を包み、白いギターをかかえた少女のジャケットが、文字通り、日本を制覇してしまったのである。
このレコードの素晴らしさを語るのに、言葉はもはや必要ない。レコードの盤面に針を乗せた瞬間から(どうしても、こういう古い表現になってしまうが)、出てくる音すべてに鮮明な躍動感がある。そのドスの効いた凄まじいまでの歌声はもちろん、バックに流れる各楽器がこれほどまでに精彩に富んだ音を出しているレコードは稀有であろう。
藤圭子が「演歌の星」 というキャッチフレーズでデビューした頃(この「○○の星」という表現は当時の流行だったわけだが)、当時小学校6年だった自分が真っ先に連想したのは、いうまでもなく「巨人の星」だった。現代の人たちが見たら実に泥臭いと思われるであろうこのアニメドラマが、当時は国民的な大ヒットを勝ち得ていたのである。
この作品のどこがそれほど魅力的なのだろうか。
実は主人公・星飛雄馬の姿からは、野球を楽しんでいる様子が、ほとんど伝わって来ない。
彼は本当に野球が好きなのだろうか? 自分の意思で「巨人の星」 を目指しているのだろうか?
どうも、そうではないように見えて仕方がない。
思い当たる理由はただ一つ。
きっと、あの執念深い父親の息子として生まれたから、好むと好まざるとに関係なく、「巨人の星」を目指さなくてはいけない羽目になってしまったのだ。
自分の意思に反して、いと高き目標を与えられ、それに向かって狂おしいまでの努力を重ねる毎日。
やめたいと言えば、ちゃぶ台をひっくり返され、ライバルに負けたら、根性なしと怒られる。
そのような泥沼のスパイラルに陥った状態を、人は「宿命」 と呼ぶ。
そんな宿命に支配された人生の中で、必死に闘い続ける主人公こそが、時代のヒーロー/ヒロインだったのである。
そういう意味で、藤圭子の登場はタイムリーだった。
まるで劇画の世界から飛び出してきたかのような、暗い影を背負った美少女。幼少の頃から浪曲師の父母とともにドサ回りの生活を続け、あまりの苦難の中で盲目になってしまった母の手を取り、冷たい夜風に身をさらし、来る日も来る日も24時間ぶっ続けの”流し”を行なう毎日。生活の糧を得るために、好むと好まざるとに関係なく、歌っていかなければならなかった。
歌が好きという次元ではなかった。歌わなければならない「宿命」のもとで、歌い続けた。
そういう暗い過去の中に、まさに当時の人たちが心の底からシビれた「ド根性」があった。
「宿命」と「ド根性」
これこそが、星飛雄馬と藤圭子に共通するキーワードだったのである。
しかし、藤圭子自身は決して悲劇のヒロインを好んだわけではなかった。
むしろ、不幸な衣を着せようという周囲の流れに反発して、過分な幸福を求めようとしたのではなかろうか。
今、あらためて彼女の歌声を聴いてみると、決して悲壮感一本槍でなかったことがわかる。
デビューシングルとなった「新宿の女」は、愛人に捨てられてネオン街に彷徨う女の心情を歌いながらも、明日もまた頑張っていこうという前向きな気概を感じさせるし、愛人の待つ宿を点々としながらさすらいの旅を続ける女を歌った「星の流れに」も、落胆を越えた希望が根底にある。
一方では、いったん悲壮な世界に落ち込んだら、徹底的に悲しみの地獄となる危険も孕んでいる。
圧巻は「あなたのブルース」 。あなた、あなた、あなたと連呼し、ラールルラ、ルルラ、ルラーと慟哭するあたり、とても10代の少女の声とは思えない迫力だ。
アルバムの発売後にシングルカットとなり、藤圭子の代名詞的な傑作として知られる「夢は夜ひらく」 は、オリジナルを歌ったのは別の歌手だった。筆者もごく最近までこれが園まりのカバー曲であることを知らずにいたのだが、それほどまでに藤圭子以外には考えられないほど、彼女の色に染め上げられていたのである。
この曲は歌声ばかりではなく、伴奏するベースのアルペジオ、さびれたサックスの音色がいい味を出しており、演歌というよりは上質なジャズとして聴けるアレンジも魅力的だ。
他のカバー曲、「柳ヶ瀬ブルース」 (美川憲一)や「長崎ブルース」(青江三奈)なども、藤圭子独特のハスキー・ヴォイスによる節回しがカッコよく、まさにブルースの真髄ここにあり、と呼びたいような仕上がりになっている。
今回の2013年盤は、最新技術でオリジナルの音質を再現するBlu-spec CD2での再発売であり、一段と音が良くなったようだ。今後も昭和歌謡曲の黄金時代を伝える記念碑的な名盤として、時代を越えて聴かれ続けることになるだろう。
ブログ・ランキングに参加しています。
ONE CLICKで順位が上がります。