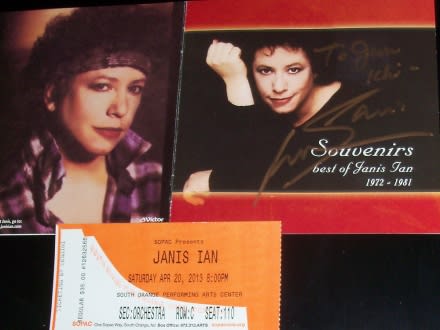毎年ニューヨークでは4月上旬の一週間、「タータン・ウイーク」と称してスコットランド関連のイベントがあちこちで行なわれる。
その一環としてNYRR(ニューヨーク・ロード・ランナーズ)の協力を得てセントラルパークで開催されるのが「スコットランド・ラン」という10Kロードレース。今年の開催日は4月5日(土曜日)だった。
この大会はレース後に本場スコットランドから招かれたアーティストによるライヴ・ステージを楽しめるのが呼び物となっているが、今年はメインに登場したロングヘアの美少女シンガー・ソングライターが注目されることになった。
「ニーナ・ネスビット」と紹介された彼女は、スコットランドのエディンバラ出身の19歳。
名前は聞いたことがあるような気がしたものの、事実上、その歌声に触れるのはこの日が始めてだった。
すでに2年くらい前からステージ活動を始め、英国内では注目を集めていたらしい。初のメジャー・デビュー・アルバムとなる『Peroxide』をリリースしたのが今年の2月11日。UKアルバム・チャートで初登場11位を記録したという。
本格的なキャリアはまだまだこれからとはいえ、キュートな笑顔とスタイル抜群な容姿、ハスキーな歌声は非凡なものを感じさせ、遠からず世界的にブレイクするのではないかという期待を抱かせる。スコットランド出身のアーティストとしては1970年代のベイ・シティ・ローラーズやシーナ・イーストン以来の大物かもしれない。
そして、この出会いは1日では終わらなかった。
帰宅後に彼女のfacebookを見ると、なんと翌日にも、セントラルパークで無料ライヴを行なうという情報が出ていたのである。
ということで、予告された午後1時、セントラルパーク72丁目にあるベセスダ・ファウンテン(Bethesda Fountain)に到着。
ほどなく取り巻きの女の子たちを従えて、若き歌姫ニーナ・ネスビットが登場する。
そしてボートを楽しむ人々でにぎわう池のほとりで、40分ほどのミニ・ライヴを行なった。
以下、写真付きで解説。
★多くの人たちでにぎわうセントラルパークの心臓部、ベセスダ・ファウンテン(Bethesda Fountain)。
★昨日とは一味違う大人っぽさを感じさせるヘア・スタイル。日差しが眩しい好天ということもあり、おしゃれなサングラスで登場する。
ボートで遊ぶ人たちも思わず振り向くようなハスキーな美声。
★時おり見せる「100万ドルの笑顔」が素晴らしい。いや、英国人だから「100万ポンド」か?
★ライヴが終わり、ファンと交流のお時間。同世代の女の子のファンが圧倒的に多く、一部男性の音楽マニアが加わるという構図。
★道行く人からサインを求められ、気軽に応じる。身長は自分より1~2cm高い程度(170cmくらい)なのだが、スタイルが抜群にいいので、遠目にはもっと長身に見える(しかもハイヒールではなく、ナイキのシューズ)。
★女の子の取り巻きが多かったので2ショットは半分あきらめかけていたのだが、ラスト・ミニッツのチャンスをモノにした。アメリカには滅多に来ないだろうから、これは貴重である。
ブログ・ランキングに参加しています。
ONE CLICKで順位が上がります。