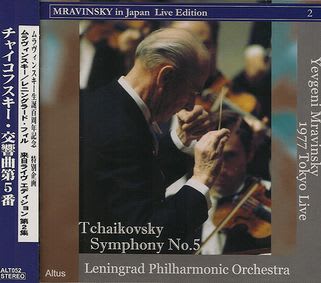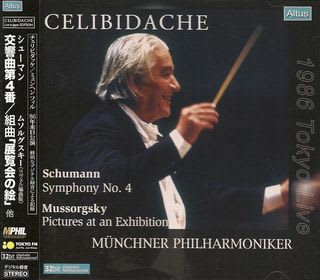ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲、モーツァルト:交響曲第40番ト短調K.550
シベリウス:交響曲第2番、ベルリオーズ:ラコッツイ行進曲~劇的物語「ファウストの劫罰」より
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
(1970年5月22日 東京文化会館: ステレオ・ライヴ録音) SICC 1073~4
クラシック音楽の演奏家の中には、もしかしたらスポーツの世界でも大成したかもしれない、と思えるような人を時たま見かけることがある。
たとえば「鋼鉄のピアニズム」 といわれたエミール・ギレリス。晩年はかなりイメージチェンジした面もあるが、若い頃はまさにアスリートそのもので、繊細な感受性よりは強靭な肉体美を想起させるような力強さで名を馳せていた。指揮者では1960年代から80年代までシカゴ交響楽団を率いていたゲオルク・ショルティがそうで、シカゴ響の金管を徹底的に鍛え上げ、圧倒的な迫力で押しまくるスタイルで観客の拍手喝采を浴びていた。
アメリカは基本的にショービジネスの国なので、この国で成功するには、一見して「すごい!」と思わせるような強烈なインパクトを持っているほうが有利である。ギレリスにしろ、ショルティにしろ、あるいはホロヴィッツなどもそうなのだが、アメリカで名声を得ることができた演奏家というのは、芸術的な深みは別にして、問答無用で聴衆を圧倒させる必殺技を持っていた。クラシック音楽といえども、あくまでショーとしての「見せ場」を心得ていなければならないのである。今回登場するジョージ・セルも似たような系列に属すると思われていた指揮者だった。
ジョージ・セルはハンガリー出身の指揮者で、戦前はおもにドイツの歌劇場を中心に活躍していたが、アメリカへの演奏旅行中に第二次世界大戦が勃発し、ユダヤ人の血が流れていたこともあって帰国を断念し、そのままアメリカに定住した。しかし災い転じて福となるとはこのことで、セルのキャリアにとっては幸運だった。同じくアメリカで活躍していたトスカニーニの援助を受けてNBC交響楽団やメトロポリタン歌劇場で経験を積むことができたからである。トスカニーニからは、おそらく「アメリカで成功するためのノウハウ」を教わったはずだ。2人に共通する演奏上の特徴がそれを物語っている。圧倒的な迫力で展開される、リズムとスピードの音楽。
在米時代のセルが1946年から1970年まで率いたクリーヴランド管弦楽団は「鉄壁のアンサンブル」といわれた。クリスタルガラスのように透明度の高い響きと、寸分の狂いもなく刻まれるリズムの正確さは、他に類を見ないものだった。
ただ、アメリカで圧倒的な支持を得たその正確無比な演奏は、繊細な情感表現を重んじる日本人の好みには今一つ合わないように思われた。正確ではあるが冷たいという風評もあり、なかなか人気が出なかったのである。
ここに紹介する演奏会が行なわれるまでは・・・
1970年、大阪万国博覧会が開催された年。大物指揮者ジョージ・セル、最初にして最後の来日公演。
特に5月22日にライヴ録音された東京文化会館での公演は「歴史的な名演」として揺るぎない評価を得ることになった。
セルはただ者ではなかった。正確なリズムだけの指揮者ではなかった。
火の玉のように熱い凝縮した音楽を奏でることができる真の巨匠である、と。
たった一度の来日公演で、従来の評価が180度、逆転したのである。
1曲目の歌劇「オベロン」序曲を聴いただけで、ただならぬ完成度に圧倒される。アンサンブルに寸分の狂いがないのはもちろん、鍛え上げられた合奏の威力をこれほどまでに思い知らされる演奏というのも、そうそうあるものではない。10分足らずの短い曲なのに大シンフォニーを聴いたような充実感がある。
2曲目はモーツァルトの交響曲第40番。この曲には以前紹介したカイルベルト/バイエルン放送響のドイツ風名盤があるが、セルの演奏も甘さを排した直球勝負でありながら、もっとインターナショナルな色合いが強い。アメリカ人が好みそうな音色といえようか。それでも決して外面的な迫力のみに陥っていないのはさすがだ。
3曲目のシベリウスの交響曲第2番はこのディスクの白眉。冷たい肌触りがシベリウスの本質にマッチしており、作曲者との相性の良さをうかがわせる。フィンランド系の指揮者とは一線を画したシンフォニックな演奏で、迫力重視でありながら決して力ずくではなく、随所に北欧の空気を感じさせる繊細なニュアンスがこめられているところが素晴らしい。晩年のセルは若い時期に比べると人間的に「丸くなってきた」ともいわれ、本来秘めていた優しさを表現できるようになったということであるが、演奏の上でも成熟ぶりが現われてきたのかもしれない。
もちろん、第3楽章でのティンパニの打ち込みや、最終楽章での輝かしい盛り上がりなど、セルならではの強靭なリズム感を存分に味わえるところも多く、交響曲というジャンルのエッセンスが詰み込まれたような魅力的な演奏となった。自分にとっては同曲1位の最有力候補として何度でも繰り返し聴きたいと思うほどの名盤である。
アンコールで演奏されたベルリオーズの「ラコッツイ行進曲」 も切れ味鋭い名演。これだけ充実した演奏会は滅多に聴くことができるものではない。当時の聴衆がどれだけ興奮したか、手にとるようにわかろうというものだ。
一期一会の日本公演で、ついに真価を知らしめた幻の指揮者ジョージ・セル。
しかし、 これが彼の人生最後の輝きだったとは、当時の人は知る由もなかった。
同年7月30日、ジョージ・セル癌のため他界。
25年の長きにわたったクリーヴランド管弦楽団の黄金時代は、ついにその幕を閉じたのである。