なぜ今年に限って、こんなに多くのツキノワグマが山から降りて出没しているのか。
今年は山のドングリが不作だったからと簡単な説明がされているが、本当にそれだけだろうか?
平成16年度、平成18年度にツキノワグマが大量に人家近くに出没し、大量に捕獲(捕殺)されたことがあった。
特に平成18年は過去に例のないほどの数のツキノワグマが、有害鳥獣駆除など許可を受けて捕殺された。その数4,679頭(環境省の平成22年度の捕獲速報値から。)
この年の狩猟による捕獲数が259頭(鳥獣統計)なので、この年だけで5,000頭近くのツキノワグマが捕殺されたことになる。
その大量捕殺されてから4年。ある程度ツキノワグマの数が回復したところで、また彼らの餌になるドングリなど堅果類が不作になり、餌を求めて里山にまで降りてきているのではないのかと思っている。
野生動物についてはまだまだわかっていないことが多いが、間違いなくいえることは彼らは、自然界で生きられる絶対数よりも多くの子孫を生み育てようとする。
もちろん事故などで成獣になる前に死ぬ個体も多いだろうが、たとえ運良く成長したとしても、餌環境の一番厳しい時期(多くは冬の時期)に、生活能力の劣る個体は餌をとることができずに死ぬ運命がまっているのではないだろうか。
それでは餌環境の一番厳しい時期に人間が餌を与えれば解消できるかといえば、それもNOである。
餌を与えることでその年だけで見れば、生き残る個体が多くなるわけであり、さもよいことをしているように錯覚するが、生き残った個体が繁殖活動をすることで、より多くの個体が生まれ、その結果として厳しい時期に死にいたる個体が増えることにつながるのである。
そしてもう1点、ツキノワグマという動物について正しい認識を持っていただきたいと思う。
人間が「かわいそう」と思って接したとしても、自然界で生きるか死ぬかの生活している彼らには、人間の気持ちや感情を理解することはできない。
人間が不用意にツキノワグマに近づけば、彼らは自分の身を守ろうと全力で向かってくる。その力とスピードには、人間は全くかなうはずもないものである。
ツキノワグマが棲息する地域で生活する人たちは、日々おびえながら生活している。
出会いがしらでツキノワグマに遭遇し、彼が本気で自分の身を守ろうと攻撃してきたら…。
常に生命の危機にひんしているといってもいいと思う。
もし街で生活しているあなたの隣に、指名手配を受けた凶悪な人物がいて、あなたを襲おうとしたら、あなたはどうするだろうか…。
あなたは必死で自分の身を守ろうとするだろうし、誰もそのことを非難することはできないだろう。
山里で暮らす人たちとってツキノワグマというのは、横にいるのが凶悪な人物ではなく、それ以上の力を持った動物というわけなのである。
ここで誤解があってはいけないが、有害鳥獣としてツキノワグマが殺されているということを全面的に肯定しているわけではない。
もちろん殺さないですむような手段を最大限努力したうえで、どうしてもやむを得ない場合にのみ、殺すことも認められていいと考えている。
ツキノワグマに限らず全ての野生動物にとっていえることだが、自然界で生きることができないのなら、できれば人の生活圏に出ずに自然の中で死んでいって欲しいものである。それが本当の自然界のルールであるのだから。
できることなら、人間とツキノワグマなどの野生動物は、共生ではなく時間と空間を上手く棲み分けらるようになることが、人と野生鳥獣の問題を解決するいちばんの近道のように感じている。
さて、野生動物が殺されることに対して「かわいそう」という感情を持つことは人間として「あたりまえのこと」であるし、「持って欲しい」感情である。
しかし、その感情だけで「野生動物を殺すこと」を批判することが、本当に正しいことなのか考えて欲しいと思う。
多くのツキノワグマが殺されている今の時期であるからこそ、この記事をしっかり読んでいただき、ぜひ自然や野生動物とどう関わるべきか考えて欲しいと思っている。













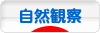

 ←応援クリックお願いします。<(_ _)>
←応援クリックお願いします。<(_ _)>












