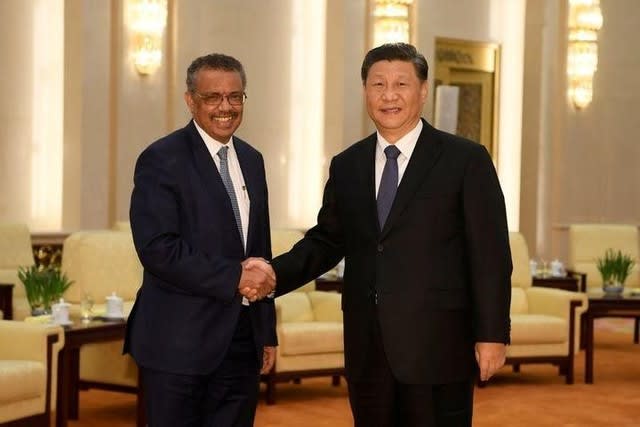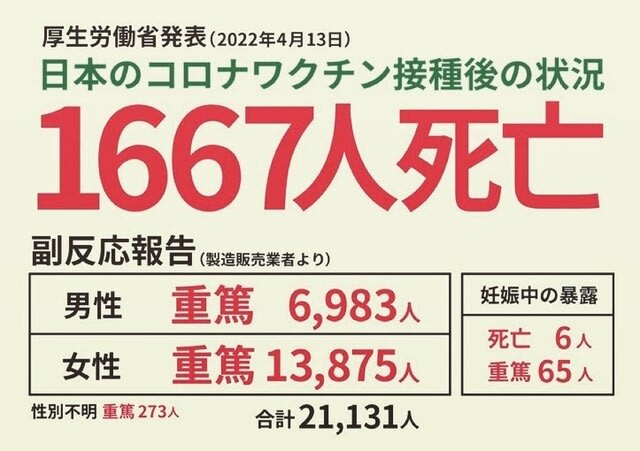2022年4月28日 衆議院 憲法審査会日本維新の会 三木圭恵くん:38:55~資金規制について。どの範囲のものまで規制の対象にするかが課題。
政党等については規制の対象にすべきとの考えもありますが、すでに政治資金規正法で透明化されています。
民間や個人にまですると事務の煩雑化により、潜脱的な支出等がおこなわれ、かえって不透明化するのではないか。
政党等以外の団体は多数にのぼると予想され、一団体あたりの上限額を設けたとしても団体数が制限できない限り無意味となるので、その意義が乏しいと考えます。個人に対してまで資金規制の対象とする必要があるかどうかは、事務の煩雑化により過度な事務負担が生じることとなります。
収支報告書の作成や公表は国民投票の期日後に行われるため、投票結果に影響を与えづらいので、過度な事務負担が生じるわりに意義が乏しいと考えられます。
仮に広告規制や資金規制を設けるにしてもそれらの違反行為には違反者の罰則等で対応するということを検討の余地があると考えます。
国民投票と国政選挙は同時に行うべきではないとの考え方もありますが、法律で一律に禁止すると、例えば、技術上の改正で高い投票率を期待しがたいような場合、国民の関心のうすいもの、例えば憲法79条や89条の改正などの場合には同時実施により投票率の向上を期することができなくなり、硬直的になってしまう。
そもそも最高裁判所の裁判官の審査は衆議院と同時に行っているということは、二つの審査投票を、同時に行えるという実績であるともいえます。
また、とくに衆議院の解散との関係で、すでに設定されていた国民投票の期日を(選挙と国民投票を同時に行うことを避けるために)機械的に延期することとなれば、多大な影響と混乱が生じることになります。
また投票にかかる経費を大幅に節約できる利点もあります。国民投票と国政選挙の同時実施の可能性を法律で排除することは柔軟な運用を阻害すると考えますので反対でございます。
だから、憲法制定権力が「国民」であることを考えれば、国会で改憲を議論すること自体に、矛盾がつきまとうわけだ。
国会議員は国民の代表であると同時に政権与党は国家権力でもあるから。
次に国民投票法改正案について2月10日に奥野幹事より配布された資料をもとに述べさせていただきます。
誰も意見を述べないのは失礼と思いますので日本維新の会から述べさせていただきます。
立憲案ではまず1-2-1に、国民投票法の広告放送の全面禁止とあります。
これは賛否の投票の勧誘である国民投票運動のための広告放送において主体を問わず全期間禁止され、また政党等は賛否の意見表明でも一律に禁止となっています。これこそ表現の自由を侵害し憲法違反のおそれがあるのではないでしょうか。(中略)ネット広告は出し手や方法に限定がなく、実効性ある規制を設けることは困難であります。(中略)そのようななかで政党等のみを対象に規制を設けてしまうと、言論空間のゆがみをかえって拡大させる恐れがあるのではないでしょうか。それがたとえ努力義務であったとしても事業者が恣意的運用をすれば表現の自由への過度な制約となりえます。
次に国民投票運動に(〈チーン〉7分経過の合図)関する支出が1千万円超す団体の届け出制及び収支報告書の提出等とありますが、団体の支出が1千万を超えるかどうかを把握することは、〈チーン〉困難でございます。
また1千万円を超す団体の数が多数にのぼると広報協議会や中央選管、都道府県選管に過度な事務の負担が生じます。先にも述べましたが収支報告書の公表は国民投票の期日後に行われるため、その意義が乏しいと考えます。
つまり選挙の場合は当選取り消しなどがございますが、国民投票で結果を覆すことは考えられないため、後日の公表は意義がうすいと考えます。支出限度の設定については5億円とありますが、複数の団体に分けて支出すると容易に規制を潜脱することができてしまい、実効性に乏しいと考えます。外国人等からの寄付の受領の禁止等とありますが外国人にも政治活動の自由が保障されており、公選法上外国人の政治活動だけではなく、選挙運動も規制はされておりません。
政治資金規正法上、政治活動に関する寄付を受けることが禁止されておりますが、それ以外の外国人等からの寄付については規制がないことを考えると選挙制度における取り扱いと整合性がはかられていないのではないかと考えます。
『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p.55より。赤、こちらで追記。「小林:なにしろ前文が象徴するように、復古主義的な路線と新自由主義的な路線とが同居しているというところが不気味です。だって前文にある「活力ある経済活動」とは、要するに我が国は、金儲けを国是としますよ、ということです。こんなものが「和」とか「家庭」とかと、どういうふうにつじつまが合うのか。」
無効事由についても国民投票が無効になる場合として、3つの事項、あきらかな虚偽や規制に重大な違反があった支出寄付行為について重大違反があったということをあげておられますが、それがどれくらい国民投票の判断に、国民の投票判断に影響を及ぼしたかを定量的に〈プーーー(時間切れやな)〉はかることは不可能でございます。
それにもかかわらず、国民代表機関である国会と主権者たる国民の判断が明確に示されたにも関わらず、司法判断で事後的に国民投票の結果が容易にくつがえることは適切ではないと考えます。
そのため無効起訴における無効事由をむやみに拡大すべきではないと考えます。
選挙運動期間と国政選挙の重複の回避とありますがそれは先に述べましたので省略いたします。またSNSのプラットフォームに対する課題は憲法の国民投票だけに関わる問題ではないと思いますので、もっと高所対処から論点を整理していただいてご議論いただくことをお願いいたします。いつまでもCM規制の件で、国民投票法案が膠着状態のままなのは問題でございます。このことを理由に本体議論ができないということは本末転倒でございます。
論点も整理されてきていることと思いますので早急に結論を出すことをお願い申し上げまして私の意見表明といたします。45:49


「森友疑獄・有印公文書変造および同行使事件」
— 空 【岸田政権打倒!】 (@kskt21) March 12, 2018
公文書から名前を消してもらってホッと一息つけて幸せだった人たち。
●安倍晋三
●安倍昭恵
●麻生太郎
●鴻池祥肇
●平沼赳夫
●杉田水脈
●中山成彬
●鳩山邦夫
●上西小百合
●三木圭恵
●北川イッセイ
2018年03月12日学校法人・森友学園(大阪市)との国有地取引に関する決裁文書の書き換え問題で、元々の文書にはあった複数の国会議員やその関係者らの名前が書き換えによって消されていたことが3月12日明らかになった。その数11人。国会議員らの名前が削除されたのは、公開された14の決裁文書のうち、近畿財務局が籠池氏の強い要望を受けて、土地の貸付けを当初予定の3年間から10年間に延長する承認を内部で求めるために作成された2つの文書だ。財務局と森友学園との交渉過程が時系列で書かれていた項目などで、当初は交渉過程で名前が上がっていた議員らの動向が書かれていたが、書き換え後にそうした記載はなくなっていた。森友学園問題をめぐっては、学園の籠池泰典・前理事長が土地取引の交渉過程で、安倍晋三首相の妻昭恵氏の名前を出すなど、政治家の「威光」によって取引を実現させようとしたとされる。議員名の削除が発覚したことで、この問題が「政治案件」だったとの疑いが強まる形になった。(中略)森友学園の概要を記した項目で、籠池氏が日本会議大阪の代表を務めていることを説明した際、麻生氏が日本会議国会議員懇談会の特別顧問を務めていると記していた。
長いのでまとめると、鴻池、平沼、鳩山邦夫の秘書は関与。安倍・麻生は日本会議なんだよって記述。昭恵は視察ですすめてくださいって言ったって記載。杉田水脈、中山成彬、上西小百合、三木圭恵が学園視察の記載。 / “森友学園、文書から「名…” https://t.co/s2lRUOXVLr
— 猫とおじさん (@gnufrfr) March 12, 2018
8月3日、日本会議地方議員の会で「国家の覚悟が問われる領土問題」と題し講演をしました。私が取り組んでおります #北方領土 #竹島 #尖閣諸島 など領土・主権に関わる問題についてお話ししました。当日の資料を公開しますのでぜひご覧ください。https://t.co/iirH6Rq4c3 #川口市 #自民党 #JNSC pic.twitter.com/TPDIlYNALE
— 新藤 義孝 (@shindo_y) August 7, 2018
(動画より抜粋)日本会議:
1997年設立。憲法改正や天皇を国家元首になどを掲げる団体。元法務大臣・長勢甚遠
憲法草案というものが発表されました。正直言って(草案に)不満があります。一番最初にどう言っているかというとですね。国民主権、基本的人権、平和主義、これは堅持するって言ってるんですよ。この3つを無くさなければですね、ほんとの自主憲法にならないんですよ。自民党 元参議院議員 磯崎洋輔 自民党憲法改正草案起草担当者なんでキリスト教の神様から与えられた天賦人権説なんか。
これ全部、削りましたから。
97条(最高法規の章の基本的人権)なんかあったけど全部ストーンと切り落としましたけど。
国民側の義務で、“緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も法律の定めるところにより国その他公の機関の指示に従わなければならない”
この文を入れておきました。基本的人権に関する規定はむしろ削ってくれという意見も結構ありました。
塚本幼稚園 籠池さんと安倍昭恵夫人。教育勅語を暗唱する園児たち。
籠池氏は日本会議大阪の代表・運営委員
第3次安倍改造内閣。閣僚20人中16人が「日本会議国会議員懇談会」に所属か。
稲田朋美氏
「国民の生活が第一なんて政治は私はまちがっていると思います。
国民の一人ひとり、皆さん方ひとりひとりが、自分の国は自分で守る。
そして、自分の国を守るためには血を流す覚悟をしなければならないのです。安倍支持改憲派 元国会議員 西村眞悟氏徴兵というのは最大の教育改革なんです。国を守るという一石二鳥ではないかと。」
Q:戦力として徴兵の兵士を備えるよりも、教育としての訓練、そういう趣旨ですか?
「一夜にして教育の改革とですね、いざとなれば、兵士になる。国を守るために体を張る青年が~」自民党参議院議員 佐藤正久氏
「個人の権利、個人の権利、個人の権利、バカじゃないかと。そこはまさにもっと大きなものを守るために、個人の権利を抑えて、今はこうです。そういう意味で憲法にそういう精神(国のために死ぬ規定)がないからよけい弱い。たしかに今回わたしはこうすべきだと思う。憲法に緊急事態条項とかあれば、もっとたぶん軽易に緊急事態を法律にもとづいて発令(部下に死ねと命令)できたのかもしれない。」
日本会議の元副会長の小田村四郎は月刊誌『正論』2005年6月号で、「日本を蝕む『憲法三原則』」と述べ、憲法改正の論議では「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の三大原理[24]は考慮する必要がないと断じた
国民投票と国政選挙は同時に行うべきではないとの考え方もありますが、法律で一律に禁止すると、例えば、技術上の改正で高い投票率を期待しがたいような場合、国民の関心のうすいもの、例えば憲法79条や89条の改正などの場合には同時実施により投票率の向上を期することができなくなり、硬直的になってしまう。
現行憲法
第 七 十 九 条
最 高 裁 判 所 は 、 そ の 長 た る 裁 判 官 及 び 法 律 の 定 め る 員 数 の そ の 他 の 裁 判 官 で こ れ を 構 成 し 、 そ の 長 た る 裁 判 官 以 外 の 裁 判 官 は 、 内 閣 で こ れ を 任 命 す る 。
② 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 の 任 命 は 、 そ の 任 命 後 初 め て 行 は れ る 衆 議 院 議 員 総 選 挙 の 際 国 民 の 審 査 に 付 し 、 そ の 後 十 年 を 経 過 し た 後 初 め て 行 は れ る 衆 議 院 議 員 総 選 挙 の 際 更 に 審 査 に 付 し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。
自民党改正草案第 七 十 九 条最 高 裁 判 所 は 、 そ の 長 で あ る 裁 判 官 及 び 法 律 の 定 め る 員 数 の そ の 他 の 裁 判 官 で 構 成 し 、 最 高 裁 判 所 の 長 で あ る 裁 判 官 以 外 の 裁 判 官 は 、 内 閣 が 任 命 す る 。2 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 は 、 そ の 任 命 後 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 民 の 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
現行憲法では、最高裁判所裁判官が10年ごとの国民審査に付されるのに対して、草案は、国民投票の内容を法律に委ねる趣旨です。法律の内容しだいでは、たとえば審査を一回限りとする仕組みも想定されます。それでは、最高裁判所が憲法保障に後ろ向きの態度をとるときに、それを是正する機能を国民審査が果たせなくなるおそれがあります。すなわち、国民主権の後退に繋がります。
現行憲法第 八 十 九 条公 金 そ の 他 の 公 の 財 産 は 、 宗 教 上 の 組 織 若 し く は 団 体 の 使 用 、 便 益 若 し く は 維 持 の た め 、 又 は 公 の 支 配 に 属 し な い 慈 善 、 教 育 若 し く は 博 愛 の 事 業 に 対 し 、 こ れ を 支 出 し 、 又 は そ の 利 用 に 供 し て は な ら な い 。
自民党改正草案第 八 十 九 条公 金 そ の 他 の 公 の 財 産 は 、 第 二 十 条 第 三 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 宗 教 的 活 動 を 行 う 組 織 若 し く は 団 体 の 使 用 、 便 益 若 し く は 維 持 の た め 支 出 し 、 又 は そ の 利 用 に 供 し て は な ら な い 。2 公 金 そ の 他 の 公 の 財 産 は 、 国 若 し く は 地 方 自 治 体 そ の 他 の 公 共 団 体 の 監 督 が 及 ば な い 慈 善 、 教 育 若 し く は 博 愛 の 事 業 に 対 し て 支 出 し 、 又 は そ の 利 用 に 供 し て は な ら な い 。
自民党改正草案( 信 教 の 自 由 )第 二 十 条信 教 の 自 由 は 、 保 障 す る 。 国 は 、 い か な る 宗 教 団 体 に 対 し て も 、 特 権 を 与 え て は な ら な い 。2 何 人 も 、 宗 教 上 の 行 為 、 祝 典 、 儀 式 又 は 行 事 に 参 加 す る こ と を 強 制 さ れ な い 。3 国 及 び 地 方 自 治 体 そ の 他 の 公 共 団 体 は 、 特 定 の 宗 教 の た め の 教 育 そ の 他 の 宗 教 的 活 動 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 社 会 的 儀 礼 又 は 習 俗 的 行 為 の 範 囲 を 超 え な い も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い
現行憲法
第 二 十 条信 教 の 自 由 は 、 何 人 に 対 し て も こ れ を 保 障 す る 。 い か な る 宗 教 団 体 も 、 国 か ら 特 権 を 受 け 、 又 は 政 治 上 の 権 力 を 行 使 し て は な ら な い 。
② 何 人 も 、 宗 教 上 の 行 為 、 祝 典 、 儀 式 又 は 行 事 に 参 加 す る こ と を 強 制 さ れ な い 。③ 国 及 び そ の 機 関 は 、 宗 教 教 育 そ の 他 い か な る 宗 教 的 活 動 も し て は な ら な い 。
現行憲法20条1項の後段で明示している、宗教団体が「政治上の権力を行使してはならない」という規定(上記太字部分ね)を、草案では除外しました。その結果、「国が宗教団体に特権を与えてはならない」とするにとどまり、宗教団体が選挙を通じて政権与党を構成し、これにより政治権力を行使することを認めたことになります。
また、現行憲法20条3項は、国の宗教活動の禁止を定めていますが、
草案20条3項は、それに但し書きを付し、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」としています。草案3項は、政教分離原則の解釈である目的・効果基準を明文化するものですが、この基準は、国家と宗教との「完全な分離」を求めず、「ゆるやかな分離」を容認する可能性があります。行為者の宗教的意識までを考慮要素とすれば、その可能性は大きく、社会的儀礼、習俗的行為の名の下に、公人がさまざまな宗教行事に参加すること(政治家の靖国参拝など)が可能になるでしょう。こうした「ゆるやかな分離」は、宗教的少数派への弾圧につながり、少数派の人権保障という立憲主義の勝ちを骨抜きにするおそれがあります。
Wikipedia「日本会議」より政教分離[編集]塚田穂高は、日本会議は愛媛県靖国神社玉串訴訟にみられる厳格な政教分離判断には反対しており、社交儀礼・国民的な習俗の範囲内と判断すべきとする立場であるとしている[5]。また、元会長で裁判官の三好達は、最高裁が政教分離関係訴訟で初めての違憲判決を下した愛媛玉串料訴訟で裁判長をつとめており、違憲判断へ反対を表明した2人の裁判官のうちの1人であることも指摘している[5]。
愛媛県靖国神社玉串料訴訟(えひめけん やすくにじんじゃ たまぐしりょうそしょう)とは、愛媛県知事が、戦没者の遺族の援護行政のために靖国神社などに対し玉串料を支出したことにつき争われた訴訟。最終的に最高裁が違憲判決を出した。この判決は最高裁が政教分離関係訴訟で下した初めての違憲判決である[1]。
Wikipedia「日本会議」より2016年の時点で、日本会議の顧問5名がのうち4名が宗教関係者(うち3人が神道関係者)であり、代表委員41名のうち17名が宗教団体・修養団体関係者、とくに、神社本庁関係者も参画しているということや[3]、神社本庁、解脱会、国柱会、霊友会、崇教真光、モラロジー研究所、倫理研究所、キリストの幕屋、佛所護念会教団、念法眞教、新生佛教教団、三五教(オイスカ)等、宗教団体や宗教系財団法人等が「守る会」以来の繋がりで参加しているとしている[3][5]。
2022年5月2日参院選で引き続き3分の2以上を確保した上で、来年にかけて両院の憲法審査会で議論を進め「24年の改憲発議」「25年の国民投票実施」にこぎ着けるシナリオがささやかれる。