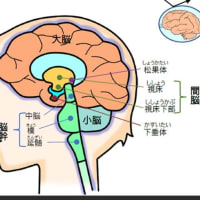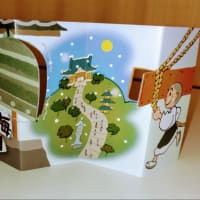(独り言)ブログ366回目に深井智明さんの「プロテスタンティズム」(中公新書)のお話を書いたが、お会いしサインをいただいた。第3版としてまもなく出るとのお話でした。確かに今月20日(2017年6月20日第3版)が出ましたのでまた、先ほど購入。で、サイン本は知人にあげた。次回、お会いする機会があれば、お約束通り購入しましたとまた、サインいただこうと思います。
◆しかし、アメリカの神はキリスト教の神に限りなく似ているがキリスト教の神ではないと言い切っている(p194)内容が気になるのでもっとお尋ねしたかったが、これだけでも本が書けそうだ。古プロテスタンティズムから新大陸へのピュ-リタンのイミグレーション。そして大陸内でのプロテスタンと旧教派のありよう、アメリカ創立の父たちの独特のキリスト教、守らねばならないとする旧教派の派閥。バプテストは、イギリスに於いて発生、クエーカーはアメリカでの発生であるが、戦後日本の昭和天皇に教育を担当されたのはクエーカーの人々であったと記憶する。原点に戻るという形での一致も考慮されたが、かなりの教派に分かれている。アメリカは、神を信じているから勝者となれるプラグマティック(実用主義)に変質した。
※(ここでまた独り言)・・・ということは、歴史上決して表に顔を出さないが、やはり宗教のような観念的な心のよりどころなどという曖昧模糊というのではなく、実際に政治的に実態のある現象をこの手につかむというような役割を世界の選ばれしエリート集団が行うこととになっているのであろう。ベースは、かの方々は、「表向教派だの何だだのとやってちょうだい、それだけで世の中動かないだろうさ!」と実際、その媒体を研究する、そして動き回る人間を研究する、そして人をして動かしめる、自らの行いとしてですから自主的に行うので問題は生じない。その良心を用いる、従順を用いる。表だっての歴史は動く。先手を打って、相手の行く先に穴を掘っておく、危ないことに気付く、どうすると穴を掘った側は駆け引きに使う。相手の中に反目しあう事象を提供して弱体化するのである。目的は、相手を知らずに取り込むこと、さらに経済で言えば運用に必要になる媒体、最終そうお金となるである。策の通りに動くよう先手をうつ。為政者は当然のこととして理解しておかないといけない。でなければ、尻の毛までむしられている事になるだろう。
◆ここまで来ると、本当に旧約聖書を学ばないといけなくなる。選民族の歴史としてだけではなく、その戦略としてその洗練された手段を採用したアメリカ国家について・・・。ここに来て、トランプさんになったのは、従来の手段ではボロが出始めたか、先手が打てなくなったからの、理想をリセットしての背に腹は代えられないと言ったところである。
◆従って、ここでまたニーバーのことを書くが、先ブログに書いたが近藤勝彦先生の言われるニーバーは、あれかこれかの現状分析で、結論としての落としどころが書かれていないということな批判がでる。しかし、アメリカの神学は必要ながらも少なくとも統括的な学問としての成立は極めて困難であろうと考える。というのは、宗教性が変じて実利面にかなり飲み込まれてしまっているからである。実利優先で、表とは裏腹の先手を知らないふりで行い、黙秘するからである。事件や事故、戦争などを・・・。例の人たちが顔を覗かせるからである。虎の尾を踏むような事態にもなりかねないから。
◆だから、ここで基本に帰ろう。イエスは、肉における人生は一度きりの私に語られているのである。誰それや集団や組織に対してではない。
*************************************************************
「私たちが信じるのはもう、あなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそまことに世の救い主であることが、わかったからである」。
(ヨハネによる福音書 第4章42節)
********************************************************* *** ・・・ Ω
◆しかし、アメリカの神はキリスト教の神に限りなく似ているがキリスト教の神ではないと言い切っている(p194)内容が気になるのでもっとお尋ねしたかったが、これだけでも本が書けそうだ。古プロテスタンティズムから新大陸へのピュ-リタンのイミグレーション。そして大陸内でのプロテスタンと旧教派のありよう、アメリカ創立の父たちの独特のキリスト教、守らねばならないとする旧教派の派閥。バプテストは、イギリスに於いて発生、クエーカーはアメリカでの発生であるが、戦後日本の昭和天皇に教育を担当されたのはクエーカーの人々であったと記憶する。原点に戻るという形での一致も考慮されたが、かなりの教派に分かれている。アメリカは、神を信じているから勝者となれるプラグマティック(実用主義)に変質した。
※(ここでまた独り言)・・・ということは、歴史上決して表に顔を出さないが、やはり宗教のような観念的な心のよりどころなどという曖昧模糊というのではなく、実際に政治的に実態のある現象をこの手につかむというような役割を世界の選ばれしエリート集団が行うこととになっているのであろう。ベースは、かの方々は、「表向教派だの何だだのとやってちょうだい、それだけで世の中動かないだろうさ!」と実際、その媒体を研究する、そして動き回る人間を研究する、そして人をして動かしめる、自らの行いとしてですから自主的に行うので問題は生じない。その良心を用いる、従順を用いる。表だっての歴史は動く。先手を打って、相手の行く先に穴を掘っておく、危ないことに気付く、どうすると穴を掘った側は駆け引きに使う。相手の中に反目しあう事象を提供して弱体化するのである。目的は、相手を知らずに取り込むこと、さらに経済で言えば運用に必要になる媒体、最終そうお金となるである。策の通りに動くよう先手をうつ。為政者は当然のこととして理解しておかないといけない。でなければ、尻の毛までむしられている事になるだろう。
◆ここまで来ると、本当に旧約聖書を学ばないといけなくなる。選民族の歴史としてだけではなく、その戦略としてその洗練された手段を採用したアメリカ国家について・・・。ここに来て、トランプさんになったのは、従来の手段ではボロが出始めたか、先手が打てなくなったからの、理想をリセットしての背に腹は代えられないと言ったところである。
◆従って、ここでまたニーバーのことを書くが、先ブログに書いたが近藤勝彦先生の言われるニーバーは、あれかこれかの現状分析で、結論としての落としどころが書かれていないということな批判がでる。しかし、アメリカの神学は必要ながらも少なくとも統括的な学問としての成立は極めて困難であろうと考える。というのは、宗教性が変じて実利面にかなり飲み込まれてしまっているからである。実利優先で、表とは裏腹の先手を知らないふりで行い、黙秘するからである。事件や事故、戦争などを・・・。例の人たちが顔を覗かせるからである。虎の尾を踏むような事態にもなりかねないから。
◆だから、ここで基本に帰ろう。イエスは、肉における人生は一度きりの私に語られているのである。誰それや集団や組織に対してではない。
*************************************************************
「私たちが信じるのはもう、あなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそまことに世の救い主であることが、わかったからである」。
(ヨハネによる福音書 第4章42節)
********************************************************* *** ・・・ Ω