
え~と、今回はなんとも言い訳事項がてんこ盛りです
 (←?)
(←?)一応最初に書いておくと、わたしが書いてるのはそのほとんどが妄想手術室みたいなことなんだと思ってください(それでいいのか☆^^;)
とりあえず、↑のような本とか、

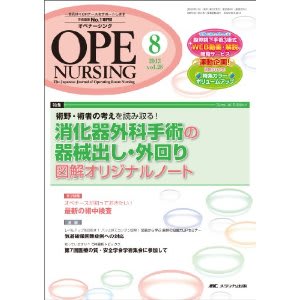
といった本を買ってみたんですけど(面白かったです!笑)、まあ当たり前のことながら、問題はそーゆーことじゃないということで(^^;)
なので、わたしの書いてることには間違いがある、何やら誤魔化しながらテキトー☆に書いてるらしいということで、よろしくお願いしますm(_ _)m
あと、花原師長のわくわく動物ランドはほとんど架空の国です(笑)
「ワシントン条約?一体なんのことですか??」という感じで、ここもあまり本気で読んではいけないと思ってくださいね
 ←
←
ではでは、ここからちょっとこうした言い訳事項が色々と続くかもしれませんm(_ _)m
それではまた~!!

動物たちの王国【第二部】-9-
五階の外科病棟のナースたちに惜しまれる形で、瑞島藍子は十月一日からK病院の手術部に籍を移すことになった。これがもし、たとえば内科や整形外科、神経内科(なんだったら精神科でもいいと瑞島は思う)といった他の病棟への異動だったとしたら、これほど気が重くはならなかっただろう。
瑞島の場合、主任補佐から昇進して看護師長になれる――という、その部分に魅力を感じてオペ室への異動を承諾したというわけではまるでなかった。とにかく、宮原総師長に「お願い、瑞島。他に手術室に行ってもいいっていう人材が誰もいないのよ。その点あんたなら、誰とでもうまくやっていけるっていう特性を持ってるでしょ?江口や園田とも顔なじみだし、ふたりともあんたが師長だっていうんなら、うまいことオペ室が回るように手伝ってくれると思うのよ。で、二年以上看護師長でいてくれたら、次のポストのことは絶対保障してあげるからっ」と頼みこまれ、嫌々ながらも仕方なく、承知せざるを得なかったのである。
(あーあ。まったく、気が重いや)
そう思いながら瑞島は、ついいつもの習慣で5のボタンを押したのち、ふと思い返して7のボタンを押し直した。そして手術部ナースの更衣室で着替えたのち、控え室兼休憩所となっている場所へ向かう。
「おはようございまーす」
まだ八時前ということもあってか、控え室にはひとりしか人がいなかった。器材洗浄室の看護助手たちもここで休むのだが、相手が自分と同じ臙脂色の手術衣を着ているのを見て、看護師なのだろうということがわかる。
「あの、今日からわたし、手術室に異動になった瑞島っていいます。どうぞよろしく」
十畳ほどの畳敷きの部屋には、漆塗りに似た艶を放つテーブルがひとつと、あとは壁際の台にテレビ、大きな本棚には手術に関係した書籍が何十冊となく詰まっていた。
瑞島が声をかけた女性は百六十センチある瑞島と大体同じくらいの身長で、髪を後ろにきっちりと結い上げて身綺麗な印象だった。おそらく年の頃は二十九の自分より少し下くらいだろうと瑞島は見当をつける。
「あの、わたしも今日こちらに来るのが初めてで……」
(うわっ、可愛い声!!)
瑞島は相手から羽生唯という名を告げられ、軽く自己紹介を受ける間――ふと、自分が彼女に対し、ある種の品定めをしていることに気づいていた。つまり、こんな清楚なお嬢さんっぽい子が、江口や園田といったガサツ女子のいるガサガサした環境で、果たして馴染んでいけるのだろうか……といったようなことを。
「あの、こちらに異動になったっていうことは、新しい手術部の師長さんですよね?」
「ええ、まあ。一応そーゆーことになってるっていうか……んー、でも結局、器械出しなんてわたしもまったくの初心者だし、そういう意味では立場は羽生さんと一緒かな。まあ、初めて来た者同士、仲良くがんばるしかないわよね」
それから瑞島は、唯が『手術の基礎知識と基本手技』といった本を見ているのに気づき、自分も鞄の中から『器械出しの基本とポイント』なる本を取り出して、一緒に笑いあった。
「わたしなんてもう、異動が決まってからずっと、この手の本と首っぴきになってて」
「わたしもです。勤務が終わって家に帰ったらもう、紙の上の知識だけでもっていう感じで、あとはネットで色々調べたりとか……」
瑞島と唯がそんなことをしゃべりあっていると、シャッと薄いピンク色のカーテンが開かれ、花原師長が赤いバッグを手にして現れた。
「早いのね。いつもは大抵、わたしが一番乗りなんだけど……お茶や給湯ポットなんかは、すぐそこにある台所に揃ってるから、好きに飲んでくれていいのよ。隣には自動販売機があって、自由に飲めるし……前までは無料だったんだけど、ちょうど前の院長がかわった頃くらいから、突然有料になってしまって。まったく、残念な限りだわ」
(相変わらず綺麗だな、花原さん)と、瑞島は思った。(女のわたしでもうっとりしちゃうくらい)
髪を止めているピンを全部外したとしたら、腰よりも長いだろう髪の毛をきっちりと乱れなく結い上げているところもまったく変わっていない。彼女は化粧をまったくしない人なのだが、高価な美白化粧品を絶対使っているに違いないと思うほど、肌が白く透明感がある。
「あの、わたし……手術室って初めてなので、よろしくお願いします」
唯がそう言って頭を下げると、花原師長は彼女が手にしていた本に少しの間目を留めている。
「勉強熱心なのね。結構なことだわ。器械出しが最初からうまいナースなんて誰もいないから、その点は安心して大丈夫よ。あなたには今日、わたしと一緒に消化器外科の加瀬先生の手術に入ってもらいます。その前に手術室を案内したりするから、一緒に来てね。それと、瑞島さん」
「は、はいっ!!」
瑞島はドキリとするあまり、手にしていた本を畳の上に落とした。脳外科時代、この人に一体どれほど口うるさく注意されたことだろう……と、過去の記憶が走馬灯のように巡っていく。
「あなたには園田主任が教育係としてつきます。だから詳しいことは園田さんが来たらお話を窺ってください。いいですね?」
「わかりました」
――このあと、休憩室に集まった二十数名の看護師たちに自己紹介し、唯と瑞島の手術室における初勤務がはじまったのだが、花原師長に器械出しを教わることになった唯は、まず手術室の一体どこに何があるかについて、一通り説明を受けることになっていた。瑞島のことは瑞島で、主任の園田が彼女のことをレクチャーするために別の場所へ連れていく。
「手術室は全部で十室あります。それで、まず順に説明するとしたら、外に家族の控え室と患者を搬送するためのエレベーターがあるのは、あなたも見たわね?」
「は、はい。そちらから患者さんがベッドやストレッチャーに乗って運ばれてきて、この受付のところにやって来るっていうことですよね」
実際今も、「頑張れよ」、「成功するように祈ってるからね」と家族に見送られてきた患者のひとりが訪れ、病棟の看護師が手術部の看護師に引き継ぎしているところだった。
「あなたもテレビのニュースなんかで、患者の取り違え事件のことを聞いたことがあるでしょう?普通に考えたら「そんな馬鹿な」っていうところだけど、ここで大真面目に看護師が引き継ぎしたとしても、起きる可能性はゼロではない……一応そう思って、頭の隅に置いておいてね。まあ、ここでの引き継ぎ業務については、外回りの仕事をする時に詳しく説明します」
「バイタルは血圧が120の80、パルスが75で安定してます。きのう、手術前ということで緊張して眠れなかったらしく、夜勤の看護師が睡眠導入剤を飲んでもらったということでした。それで……」
薄いブルーグレイの制服を着た病棟看護師が、手術帽にマスクをし、手術衣を着たオペ室ナースに、カルテを参照しながら色々と説明している。
唯としてはその様子の一部始終をまだ見ていたい気がしたが、花原師長が廊下を先に歩いていったため、慌ててそのあとを追いかけた。
「あの、師長。患者さんの手首には名前や受診カードの番号が入ったリストバンドが巻かれていますよね。それでも取り違えるなんてこと、あるんでしょうか?」
「だからさっきも言ったでしょ。可能性として低くてもゼロではないと思っておいてって。同じことをわたしに二度も言わせないで」
「は、はい……」
花原の、どこか有無を言わせぬ断固とした物言いに、唯は思わず黙りこんだ。それからも花原師長による、どこか機械的な口調の手術室内部の説明が続いた。ここが物品庫で、ここが薬品庫、麻酔器材室に滅菌器材室、先生たちが手術着に着替える更衣室などなど……そして次に花原は、その向かい側にある麻酔医の控え室のドアを叩いていた。
「この方、十三階の特別病棟から手術部に異動になった羽生唯さん。どうせ園田さんあたりから、来週の月曜から新しい師長と他にもうひとり哀れな子羊がやって来るとでも聞いてるんでしょう?先に言っておきますけど、わたしまだあと二か月はここにいますからね。羽生さんに対しても、「あの子は一体何か月で辞めるか」なんて、おかしな賭けをしないように」
「わかってますよ、師長さん」と、どこかへらへらした雰囲気の男が、椅子から立ち上がってこちらへ近づいてくる。「それはそうと可愛こちゃん。僕戸田っていうの、よろしくね」
唯に向けて白衣のポケットから握手の手が差し伸べられたが、花原はそれをピシャリとドアを閉めることで遮っていた。まるで汚い雑菌だらけの手が伸びてきたというように。
途端にドッと笑い声が奥のほうから聞こえ(麻酔医の控え室には、戸田の他に麻酔医がふたりいた)、「一体何か月後に辞めるかな、可愛こちゃん」などと、早速とばかり賭けをはじめる様子だった。
「いいのよ、羽生さん。気にしないで。あの人たちはみんな馬鹿なの。馬鹿の相手はまともにしちゃいけないっていうのが、ここの手術室では大事な鉄則なのよ。よく覚えておいてね」
「は、はあ……」
唯の心の中には、お医者さん=とても頭のいい偉い人というイメージが看護師となった今でも根強く残っている。だが先ほどの戸田という麻酔医のことは、そこから除外したほうが良いということなのだろうかと、唯は少しばかり混乱した。
「さて、ここの廊下の突き当たりにあるのが、器材洗浄室と器材準備室よ」
器材洗浄室に近づいていくと、水道の水を流す音が聞こえ、消毒薬に漬けられていたものをマスクをした看護助手数名が洗っているところだった。
「水原さん、ちょっといいかしら」
「あいよ、お嬢」
(お嬢?)
先ほどの戸田医師の「可愛こちゃん」という言葉といい、このK病院のオペ室という場所は一体どうなっているのだろうと唯は一瞬思った。
「こちら、今日から手術部に配属になった羽生唯さん。K病院に来る前は医大病院の救急部にいたんですって。教え甲斐のありそうな子だと思ってわたしも期待してるから、そういうことでよろしくね」
「ふう~ん。救急部ねえ……」
水原は頭には水色の手術帽、口にはマスク、体には給食のおばさんを思わせる白いスモッグを着ていた。全体として肉付きがよく、人を威圧するような空気があり、細い眉の下の鋭い目が特徴的であった。
その鋭い眼光で眺めまわされると、唯は自分がなんだか看護師として品定めされているような気がして、落ち着かない気分になるほどだった。
「さっき、園田の野郎が「この人が手術部の新しい師長だぴょん。よろしくだぴょん」とか言って挨拶してきましたけど……あの師長、ちゃんと使い物になるんでしょうね?」
「心配しなくても大丈夫よ。使えるようにわたしがしこんでいく予定だから」
「ま、そんならいいですけどね」
水原芽衣子という滅菌担当の責任者が、あまりにも恐ろしげなオーラを放っているため、唯はこの器材洗浄室付近にはあまり近づきたくないと、反射的に感じるほどだった。
「手術器材の中で、何か欲しいものがあって、それがどこにあるかわからないような時は、なんでも水原さんに聞きなさいね。一見怖そうな人に見えるけど、本当は動物好きの、心の優しい人なのよ」
「はい……」
(とてもそうは思えない)――という言葉は心に飲み込んでおいて、唯は花原師長に続いてブラッシングルームへ向かった。そして壁面に色々な消毒薬のセットされた手洗い場で、手や腕をどれほどゴシゴシこすって清潔にしなければならないかを唯は教わった。
「まあ、これも慣れよ。手術室の看護師には毎度のことだから、嫌でもすぐに覚えるわ」
最後に滅菌タオルで手を拭いていると、そこへまたどこかちゃらちゃらした感じの医師がひとりやって来る。そして彼は花原が新人と思しき看護師にものを教えていると気づくなり、ブラシで指先をこすりながら話しかけてきた。
「やあ、可愛こちゃん。今日はどうぞお手柔らかに頼むよ」
「羽生さん。こちらが今日の結腸癌手術の執刀医、加瀬学先生よ」
「あ、あの……よろしくお願いします」
滅菌ガウンを着、滅菌手袋をしたあとだったため、唯はぎこちなくそう言って頭を下げた。
「♪あなたの~けしてお邪魔はしなーいから~おそばに~おいて欲しいのよ~とくらあ」
唯のお辞儀にはまるで注意を払わず、加瀬は殿さまキングスの『なみだの操』を歌いながら第三手術室へ消えていく。
「あの先生、ちょっと頭がおかしいの。だから、あんまり深く色々考えちゃ駄目なのよ」
「は、はあ……」
(その頭のおかしい医師にこれから手術を受ける患者はどうなるのか)――これもまた口に出して言うことが出来ず、唯の心の海に沈んでいった言葉だった。
なんにせよ、消化器外科が専門の加瀬学は、手術室では演歌をかけるでもなく、医療機器類の機械音が響く以外は無音の中で手術を続けた。おそらく前もって花原師長から新人に器械出しを教えるということを聞いていたのだろう、「アリス鉗子の渡し方」や「自動吻合器の扱い方」について花原が唯に教えていても、加瀬も第一助手の斎木も、特にこれといって何も言わなかった。ただ、手術の終わり頃に「持針器の渡し方のポイント」といったことを花原がもう一度説明していると、「はやくはやくー、患者が死んじゃうよ~」と冗談で加瀬が急かす場面があった以外は、不測の事態が起きるでもなく、結腸切除術は無事成功していた。
「ま、これから鬼の花原師長にたっぷり色々教わりなはれ、可愛いこちゃん」
最後の縫合を第二助手の瀬棚に任せると、からかうようにそういい残して、加瀬は手術室を去っていった。やがて縫合も終わり、患者を回復室へ移すことになり、そのあとで使った器具類を片付ける作業へ移ることになる。
唯は手術室内における清潔・不潔の概念といったことを含め、医療器材を片付ける過程であらためてその名称などを教わり、最後に手術に使用した器具類をすべて器材洗浄室へ運んだ。
「あ、お嬢。第三手術室、オペ終了ですか?」
「ええ。これ、頼むわね」
使用済みの手術器材をカートごと受け取ると、水原は「三井、美沢、平木、掃除!」と、まるで一平卒に号令でもかけるように命じていた。すると、奥のほうからラテックスの手袋をはきかえる音が聞こえ、看護助手が三人外に出てくる。
「比較的小規模の病院だったら、手術器材を洗って滅菌したり、オペ室の掃除をするのも看護師の仕事なんでしょうけど、うちはそのあたり、看護助手さんが全部やってくれるの。だから水原さんみたいに厳しく監督してくれる人がいる分、こっちは手術に集中できて楽よ。わたしが来る前の手術室の師長はね、水原さんに対して「あれもやれ、これもやれ」、「あれが出来てない、これも出来てない」、「もっときちんと掃除しろ」とか、すごくうるさくいじめる人だったみたいなの。それでああいう少しキツイ性格になっちゃったのね。羽生さんも、彼女たちに感謝の念を覚えて仕事するようにしてね。自分よりも格下の器材洗いのおばさんみたいに思って接しちゃ駄目なのよ」
「はい!もちろんです」
唯はR医大病院の阿部や真田のことを思い出しながら、花原師長にそう返事していた。そしてお昼休みとなり、花原が水原に対し「動物好きの心優しい人」と言っていた理由が唯にもわかる時がやって来た。
「これ、うちのゴン太!タヌキみたいな顔してて可愛いでしょ~」
先ほどまで釣り上がっていた眉もなんのその、水原は自宅で飼っているという犬一匹と猫三匹の写真を順に唯に見せていった。ちなみにゴン太というのは、タヌキによく似た顔のただの雑種犬である。
「で、こっちが三毛猫のゴローちゃん。チンチラのミーちゃん、日本猫のタマちゃん。甘やかして育てたもんだから、みんな見事にデブっちゃって」
からからと笑って水原が言ったとおり、三匹の猫は実に丸々とよく太ったデブ猫だった。
「わあ、可愛いですねえ。うちもマンションで猫が飼えたらいいんですけど、そういうわけにもいかなくて……」
「あ、そう?ここらへんって今は結構ペット可みたいな物件、多いけどねえ。次に引っ越す時にはそういうとこ探して、猫が欲しかったらお嬢に頼んで譲ってもらうといいよ」
(あらあら、あの子まだ何も知らないもんだから、社交辞令の沼にすっかり嵌まってるわ)――などと、休憩室の他の職員が思っているとも知らず、唯はただ本当に写真の犬や猫たちが可愛いと思っていた。
「あのう……さっきも不思議だったんですけど、花原師長はどうして水原さんにお嬢って呼ばれてるんですか?もしかして物凄いお金持ちのお嬢様とか……」
花原が赤いバッグの中から大量の動物及び昆虫の写真を取りだすと、水原は「あんれま、可愛い」などと言って、カマキリやカエルの写真に見入っている。
「ああ、お嬢んちはね、おっとうが有名な動物学者だもんで、屋敷に動物の世話をしに来る大学の学生とか研究者どもが出入りしてんのさ。で、そいつらは全員まるでお嬢のしもべみたいになってて、みんな花原師長のことを「お嬢、お嬢」って呼んでるわけ。わたしも師長の家によく遊びにいくもんで、そのうちそれが移ってしまったわけさね」
「そうなんですか。えっとこの生き物、なんていうんでしたっけ……」
花原と水原と唯は、それぞれお弁当を広げながら会話していたのだったが、他に休憩室にいる六人ばかりの看護師と助手は、仲のいい者同士固まって「うえっ」などと言っていた。
それもそうだろう。みな、最初の頃こそは今の唯と同じく「可愛いですね~」などと社交辞令混じりに言っていたのだ。だがそれも、蜂の巣の中の幼虫だの、カマキリがトンボを捕食する劇的瞬間だのいう写真が出てくるまでの話だった。
「あ、それはウーパールーパーのウパちゃんとルパちゃんよ。昔、ひところ流行ったらしいんだけど、今はどのくらい飼ってる人がいるのかしらね」
「お嬢んちには、熱帯魚もわんさといるから、あんたも一度見に行ってみるといいよ。そこらへんの水族館に行くより、もしかしたら面白いかもね」
(そりゃ、自宅でジンベエザメなんか、誰も飼ってないでしょうよ)……他の職員たちの心の声も知らず、唯はただ無邪気に「ええ、是非!」などと答えていた。
なんにせよ、このお昼休みのひと時は、それからも唯にとって心楽しいものとなった。イヌワシやクマタカ、ノスリやフクロウなど、何を餌にしてどんなふうに暮らしているのか、花原が自宅の鳥獣舎について話すのを聞くのは面白いことだったし、バッタが共食いをし、見事に首だけがない写真を見せられても、それほどショッキングとは感じていなかった。
やがてうさぎやモルモット、リス、モモンガの他に、カメレオン、イグアナ、スローロリスといった写真も花原は唯に見せるようになっていったが――唯が何日たっても自分たちのほうに避難してくる気配がないのを見て、他の看護師たちはこう思うようになっていた。「あの子も実は、師長や水原さんと同じ頭おかしい系なんじゃない?」と……。
とはいえ、昼休み以外では突然人が変わったように花原は厳しい人間でもあった。彼女が最初に「同じことを二度言わせないで」と言ったとおり、花原は動物の生態のこと以外では同じ言葉を繰り返すのが嫌らしく、「わたし、前にもあなたに言ったわよね」と、他の医師や看護師たちの前で恥をかかされるのは、唯にとって日常茶飯事の出来事だったといってよい。
そして、手術室に出入りする医師たちの間では、ある奇妙な噂が広がっていた。花原師長は新しく異動してきた看護師のひとりが、結城先生のお手つきだから集中的にいじめ抜いているのではないかと、オペ室の控え室ではそんな言葉が冗談として囁かれていたのである。
>>続く。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます