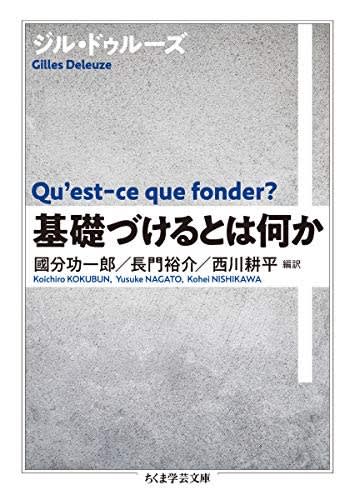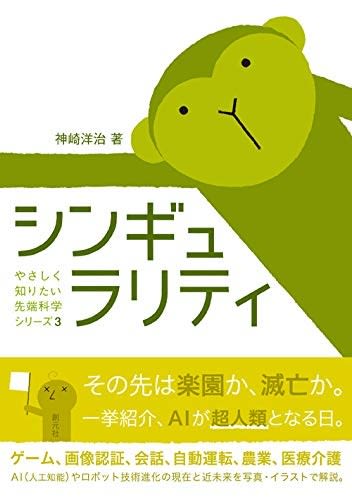経済学史への招待
柳沢 哲哉【著】

経済学史の本は多いのですが、
今回は時代背景を詳しく紹介したところと
原典からの引用を増やしたところに特徴があるようです。
内容はごくクラシックなものですので
経済学の歴史を学びなおすには最適かも。
価格 ¥2,484(本体¥2,300)
社会評論社(2017/04発売)
サイズ A5判/ページ数 224p/高さ 21cm
商品コード 9784784518432
NDC分類 331.2
Cコード C0030
内容紹介
学説とその時代背景を学び、古典への関心を喚起する。
《経済学はそれぞれの時代の経済や社会の問題に答えることで発展してきた。経済学史を学ぶ場合には、時代背景とその時代の学説との関係を理解することが不可欠である。高校で学ぶ世界史の知識を前提とすることなく、時代背景を理解できるように心がけた。これが本書の特徴の一つである。もう一つの特徴は、原典からの引用を数多く入れたことである。必ずしも分かりやすくない引用もあえて掲載した。それは経済学者の声に触れることで、少しでも古典への関心を喚起したいと考えたからである。 (「プロローグ」より)》
目次
経済学誕生以前
前期重商主義の経済思想
後期重商主義の経済思想
重農主義の経済思想
市場社会論の系譜
古典派経済学の成立
古典派経済学の展開
歴史学派の経済学
マルクスの経済思想
限界革命
ワルラスの経済学
ケンブリッジ学派の経済学
1930年代の経済学
ケインズの経済学
著者等紹介
柳沢哲哉[ヤナギサワテツヤ]
1962年群馬県生まれ。東北大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。埼玉大学人文社会科学研究科(経済系)教授
柳沢 哲哉【著】

経済学史の本は多いのですが、
今回は時代背景を詳しく紹介したところと
原典からの引用を増やしたところに特徴があるようです。
内容はごくクラシックなものですので
経済学の歴史を学びなおすには最適かも。
価格 ¥2,484(本体¥2,300)
社会評論社(2017/04発売)
サイズ A5判/ページ数 224p/高さ 21cm
商品コード 9784784518432
NDC分類 331.2
Cコード C0030
内容紹介
学説とその時代背景を学び、古典への関心を喚起する。
《経済学はそれぞれの時代の経済や社会の問題に答えることで発展してきた。経済学史を学ぶ場合には、時代背景とその時代の学説との関係を理解することが不可欠である。高校で学ぶ世界史の知識を前提とすることなく、時代背景を理解できるように心がけた。これが本書の特徴の一つである。もう一つの特徴は、原典からの引用を数多く入れたことである。必ずしも分かりやすくない引用もあえて掲載した。それは経済学者の声に触れることで、少しでも古典への関心を喚起したいと考えたからである。 (「プロローグ」より)》
目次
経済学誕生以前
前期重商主義の経済思想
後期重商主義の経済思想
重農主義の経済思想
市場社会論の系譜
古典派経済学の成立
古典派経済学の展開
歴史学派の経済学
マルクスの経済思想
限界革命
ワルラスの経済学
ケンブリッジ学派の経済学
1930年代の経済学
ケインズの経済学
著者等紹介
柳沢哲哉[ヤナギサワテツヤ]
1962年群馬県生まれ。東北大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。埼玉大学人文社会科学研究科(経済系)教授