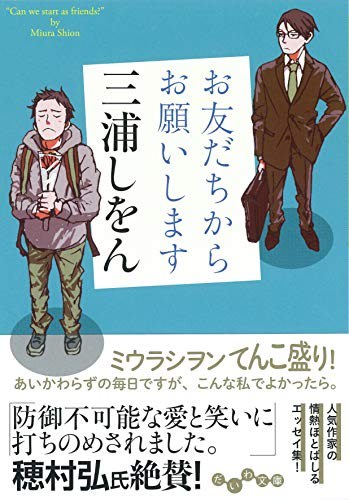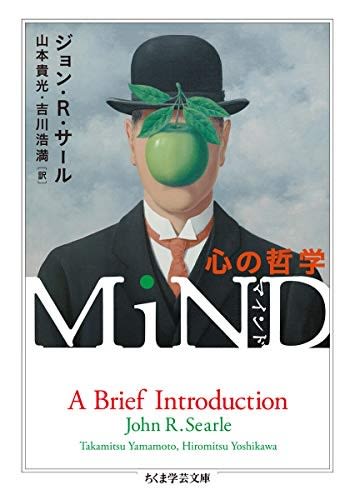ギリシア哲学30講 人類の原初の思索から〈上〉「存在の故郷」を求めて
日下部 吉信【著】
価格 ¥2,916(本体¥2,700)
明石書店(2018/11発売)
サイズ B6判/ページ数 418p/高さ 19cm
商品コード 9784750347424
NDC分類 131
Cコード C0010

哲学史の専門家である日下部氏のギリシア哲学史講義の記録。
現代の哲学史の研究姿勢にも異を唱える書物らしい。
面白そう。
内容説明
ギリシア哲学の権威にしてハイデガー研究の第一人者でもある著者が、存在の故郷を求むべく古代ギリシアの文献を読み解き、その自然哲学を「みずみずしい姿」で蘇らせると同時に、そこで繰り広げられた哲学者たちの抗争の帰結としての現代人の歪んだ思考に高らかに異を唱える。過激にして痛快な現代文明批判の書(上下巻)。
目次
ギリシア哲学俯瞰
ミレトスの哲学者(1)タレス
ミレトスの哲学者(2)アナクシマンドロス
ミレトスの哲学者(3)アナクシメネス
ピュタゴラス
アルキュタス
ヘラクレイトス
エレア派 故郷喪失の哲学者クセノパネス
エレア派 パルメニデス
エレア派 ゼノンとメリッソス
エンペドクレス
アナクサゴラス
デモクリトス
ハイデガーと原初の哲学者たち―アナクシマンドロス、ヘラクレイトス、パルメニデス
著者等紹介
日下部吉信[クサカベヨシノブ]
1946年京都府生まれ。立命館大学名誉教授。1969年立命館大学文学部哲学科卒。75年同大学院文学研究科博士課程満期退学。87‐88年、96‐97年ケルン大学トマス研究所客員研究員。2006‐07年オックスフォード大学オリエル・カレッジ客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
出版社内容情報
人類にとって原初の思索・哲学を「みずみずしい姿」で復活させ、従来のギリシア哲学観に変更を求めるとともに、そこから西洋哲学一般、近代科学、人間の思考のあり方そのものに疑問を呈する、過激にして痛烈な現代文明批判の書(上下巻)。
まえがき
本書(上巻)に登場する主な哲学者 生没年早見表
紀元前5世紀ごろのギリシアと周辺諸国地図
第1講 ギリシア哲学俯瞰
言語について
本講義の記述方針
第2講 ミレトスの哲学者(?) タレス
哲学者、タレス。
タレスの哲学
コラム:逸話
第3講 ミレトスの哲学者(?) アナクシマンドロス
アナクシマンドロス哲学の原理
ヒューマニズムを徹底的に超える哲学
アナクシマンドロス、自然の境内に住まう。
第4講 ミレトスの哲学者(?) アナクシメネス
哲学者、アナクシメネス。
アナクシメネスの自然哲学
コラム:太古的概念「ピュシス」
第5講 ピュタゴラス
哲学者、ピュタゴラス。
ピュタゴラスとテラトポイイア
第6講 アルキュタス
ギリシア世界に確信を持つ哲学者、アルキュタス。
アルキュタスの哲学
コラム一:ピュタゴラス教団
コラム二:ピュタゴラス派の数形而上学
第7講 ヘラクレイトス
ロゴスvs主観性
ヘラクレイトスの自然哲学
コラム一:世界大火
コラム二:ヘラクレイトスの出自と著作
第8講 エレア派(?) 故郷喪失の哲学者クセノパネス
クセノパネスの神観
クセノパネスの哲学
コラム:漂白の哲学者クセノパネス
第9講 エレア派(?) パルメニデス(其の一)
天才も存在の構造を脱しえず、パルメニデス。
古代のパルメニデス評価
第10講 エレア派(?) パルメニデス(其の二)
近代のパルメニデス解釈史、ないしは誤解史
再び歴史的存在としてのパルメニデスに
コラム:哲学者パルメニデス
第11講 エレア派(?) ゼノンとメリッソス
(1)ゼノン
哲学者、ゼノン。
ゼノンの哲学
(2)メリッソス
第12講 エンペドクレス
哲学者エンペドクレス
エンペドクレスの自然哲学
コラム:アクラガスの哲学者エンペドクレス
第13講 アナクサゴラス
伝統の哲学者、アナクサゴラス。
アナクサゴラスの自然哲学
コラム:クラゾメナイの哲学者アナクサゴラス
第14講 デモクリトス
哲学者、デモクリトス。
原子論哲学概観
第15講 ハイデガーと原初の哲学者たち――アナクシマンドロス、ヘラクレイトス、パルメニデス――
初期ギリシアに対するハイデガーの基本スタンス
アナクシマンドロス
ヘラクレイトス
パルメニデス
回顧と展望
著者の日下部吉信氏には以下のような著書と訳書がある。
1.
ハイデガーと西洋形而上学 : 講演集 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2015.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 別冊)
2.
アリストテレス講義・6講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2012.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 3)
3.
プラトニズム講義・4講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2012.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 2)
4.
ヘレニズム哲学講義・3講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2013.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 4)
5.
初期ギリシア哲学講義・8講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2012.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 1)
6.
ギリシア哲学と主観性 : 初期ギリシア哲学研究 / 日下部吉信著.-- 法政大学出版局; 2005
7.
西洋古代哲学史 / 日下部吉信著.-- 昭和堂; 1981.-- (昭和堂入門選書 ; 7)
8.
パルメニデス : 断片の研究 / カール・ボルマン著 ; 日下部吉信訳.-- 法政大学出版局; 1992
9.
プレソクラティクス : 初期ギリシア哲学研究 / エドワード・ハッセイ [著] ; 日下部吉信訳.-- 法政大学出版局; 2010.-- (叢書・ウニベルシタス ; 934)
10.
カテゴリー論史 / A.トレンデレンブルク著 ;
日下部 吉信【著】
価格 ¥2,916(本体¥2,700)
明石書店(2018/11発売)
サイズ B6判/ページ数 418p/高さ 19cm
商品コード 9784750347424
NDC分類 131
Cコード C0010

哲学史の専門家である日下部氏のギリシア哲学史講義の記録。
現代の哲学史の研究姿勢にも異を唱える書物らしい。
面白そう。
内容説明
ギリシア哲学の権威にしてハイデガー研究の第一人者でもある著者が、存在の故郷を求むべく古代ギリシアの文献を読み解き、その自然哲学を「みずみずしい姿」で蘇らせると同時に、そこで繰り広げられた哲学者たちの抗争の帰結としての現代人の歪んだ思考に高らかに異を唱える。過激にして痛快な現代文明批判の書(上下巻)。
目次
ギリシア哲学俯瞰
ミレトスの哲学者(1)タレス
ミレトスの哲学者(2)アナクシマンドロス
ミレトスの哲学者(3)アナクシメネス
ピュタゴラス
アルキュタス
ヘラクレイトス
エレア派 故郷喪失の哲学者クセノパネス
エレア派 パルメニデス
エレア派 ゼノンとメリッソス
エンペドクレス
アナクサゴラス
デモクリトス
ハイデガーと原初の哲学者たち―アナクシマンドロス、ヘラクレイトス、パルメニデス
著者等紹介
日下部吉信[クサカベヨシノブ]
1946年京都府生まれ。立命館大学名誉教授。1969年立命館大学文学部哲学科卒。75年同大学院文学研究科博士課程満期退学。87‐88年、96‐97年ケルン大学トマス研究所客員研究員。2006‐07年オックスフォード大学オリエル・カレッジ客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
出版社内容情報
人類にとって原初の思索・哲学を「みずみずしい姿」で復活させ、従来のギリシア哲学観に変更を求めるとともに、そこから西洋哲学一般、近代科学、人間の思考のあり方そのものに疑問を呈する、過激にして痛烈な現代文明批判の書(上下巻)。
まえがき
本書(上巻)に登場する主な哲学者 生没年早見表
紀元前5世紀ごろのギリシアと周辺諸国地図
第1講 ギリシア哲学俯瞰
言語について
本講義の記述方針
第2講 ミレトスの哲学者(?) タレス
哲学者、タレス。
タレスの哲学
コラム:逸話
第3講 ミレトスの哲学者(?) アナクシマンドロス
アナクシマンドロス哲学の原理
ヒューマニズムを徹底的に超える哲学
アナクシマンドロス、自然の境内に住まう。
第4講 ミレトスの哲学者(?) アナクシメネス
哲学者、アナクシメネス。
アナクシメネスの自然哲学
コラム:太古的概念「ピュシス」
第5講 ピュタゴラス
哲学者、ピュタゴラス。
ピュタゴラスとテラトポイイア
第6講 アルキュタス
ギリシア世界に確信を持つ哲学者、アルキュタス。
アルキュタスの哲学
コラム一:ピュタゴラス教団
コラム二:ピュタゴラス派の数形而上学
第7講 ヘラクレイトス
ロゴスvs主観性
ヘラクレイトスの自然哲学
コラム一:世界大火
コラム二:ヘラクレイトスの出自と著作
第8講 エレア派(?) 故郷喪失の哲学者クセノパネス
クセノパネスの神観
クセノパネスの哲学
コラム:漂白の哲学者クセノパネス
第9講 エレア派(?) パルメニデス(其の一)
天才も存在の構造を脱しえず、パルメニデス。
古代のパルメニデス評価
第10講 エレア派(?) パルメニデス(其の二)
近代のパルメニデス解釈史、ないしは誤解史
再び歴史的存在としてのパルメニデスに
コラム:哲学者パルメニデス
第11講 エレア派(?) ゼノンとメリッソス
(1)ゼノン
哲学者、ゼノン。
ゼノンの哲学
(2)メリッソス
第12講 エンペドクレス
哲学者エンペドクレス
エンペドクレスの自然哲学
コラム:アクラガスの哲学者エンペドクレス
第13講 アナクサゴラス
伝統の哲学者、アナクサゴラス。
アナクサゴラスの自然哲学
コラム:クラゾメナイの哲学者アナクサゴラス
第14講 デモクリトス
哲学者、デモクリトス。
原子論哲学概観
第15講 ハイデガーと原初の哲学者たち――アナクシマンドロス、ヘラクレイトス、パルメニデス――
初期ギリシアに対するハイデガーの基本スタンス
アナクシマンドロス
ヘラクレイトス
パルメニデス
回顧と展望
著者の日下部吉信氏には以下のような著書と訳書がある。
1.
ハイデガーと西洋形而上学 : 講演集 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2015.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 別冊)
2.
アリストテレス講義・6講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2012.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 3)
3.
プラトニズム講義・4講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2012.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 2)
4.
ヘレニズム哲学講義・3講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2013.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 4)
5.
初期ギリシア哲学講義・8講 / 日下部吉信著.-- 晃洋書房; 2012.-- (シリーズ・ギリシア哲学講義 ; 1)
6.
ギリシア哲学と主観性 : 初期ギリシア哲学研究 / 日下部吉信著.-- 法政大学出版局; 2005
7.
西洋古代哲学史 / 日下部吉信著.-- 昭和堂; 1981.-- (昭和堂入門選書 ; 7)
8.
パルメニデス : 断片の研究 / カール・ボルマン著 ; 日下部吉信訳.-- 法政大学出版局; 1992
9.
プレソクラティクス : 初期ギリシア哲学研究 / エドワード・ハッセイ [著] ; 日下部吉信訳.-- 法政大学出版局; 2010.-- (叢書・ウニベルシタス ; 934)
10.
カテゴリー論史 / A.トレンデレンブルク著 ;