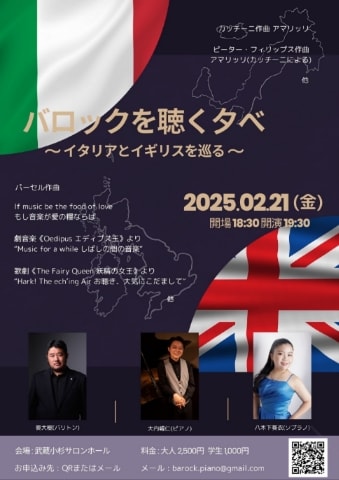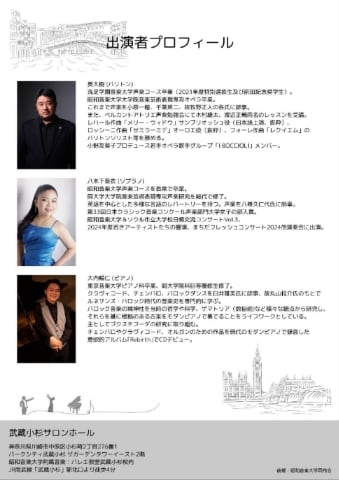大変にお恥ずかしいのですが、自分は本当に嫉妬深いタイプです。いや、でした?笑
大学生あたりから嫉妬というものをするようになった気がします。それまでは素直に拍手をし、褒めていたように思います。
しかしながらここ数年、嫉妬という気持ちがほとんど湧いていないように思います。自分がやるべきことを見つけた頃と重なるでしょうか。
物語やオペラなんかを観ても、嫉妬という感情が引き起こす事象は良いことがありませんよね(笑)「嫉妬に狂う」なんて言ったりしますが、やはり嫉妬という感情はとても醜いものに思います。
自分は心理学者でもカウンセラーでもないので詳しいことは分かりませんが、自己の確立が手っ取り早いのかもしれませんね。
大学院を出た後、自分はこれからどうしたらいいんだろう…という漠然とした不安の中にいました。そうすると、少しでも活躍してる人達がとても羨ましく嫉妬の対象になっていました。そしてその対象を認めたくないんですよね。このドロドロとした感情分かりますかね?笑
嫉妬は動物なら少なからず持っているものだと思うんです。人間に近いのならサルだって持っているはずですし、身近なところで考えれば、ペットなんかがそうですよね。目の前で他の子を可愛がれば嫉妬します。
つい先日、非常に可愛らしい花を見かけました。それはそれはひっそりとした場所にこっそりと咲いているんです。花は移動出来ません。与えられた場でのみ咲くことが許されているんですよね。もし自分なら「うわーあいつの場所日当たり良くて皆に見られる場所だなーいいなぁー」って思っちゃう(笑)でも、その花は人通りの少ないところでとても綺麗に咲いていました。
世界に一つだけの花って曲がありますが、歌詞の意味が分かったような気がしましたね(笑)
嫉妬の中で生まれるものはやはり良くないものが多いのではないでしょうか?昔はそんなこと考えていませんでした。ただ自分がやりたいことをひたすら追求していたらいつの間にか嫉妬という感情がなくなっていったように思います。人を羨ましがって嫉妬しても自分が良くなるわけではないですし、結局自分を磨いていくことでしか自分のやりたいことを達成する方法はありませんものね。
だからといって独りで突っ走ってしまっては良くないわけで(笑)常にアンテナを張りつつ、周りの声はしっかり聞いていないといきなり目の前に崖が現れたりします。自分が輝くべきフィールドを見つけ、自分を大事にコツコツ磨いていくことが大事なことなのかもしれませんね。
しかしながらここ数年、
物語やオペラなんかを観ても、
自分は心理学者でもカウンセラーでもないので詳しいことは分かり
大学院を出た後、自分はこれからどうしたらいいんだろう…
嫉妬は動物なら少なからず持っているものだと思うんです。
つい先日、非常に可愛らしい花を見かけました。
世界に一つだけの花って曲がありますが、
嫉妬の中で生まれるものはやはり良くないものが多いのではないで
だからといって独りで突っ走ってしまっては良くないわけで(笑)