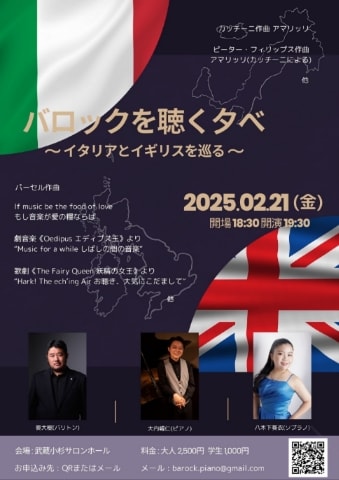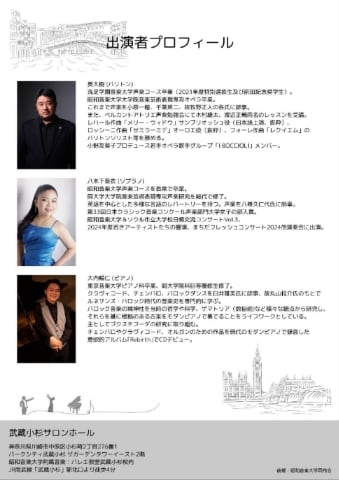しかしながら美しい旋律に惑わされがちでありますこのショパン…やはりただものじゃないですね。彼のレッスンの記録や言葉は重要な手がかりになりますね。ショパンの録音が残っていたらどれほど幸せだったか!ノクターンの自作自演が聴けたら最高でしょうね…まぁ無理なことを嘆いても仕方ないので我々は残された資料や音楽、ショパンに近かった人達の録音からショパンを探る他ないわけです。パハマンやコチャルスキなんかがそんなところに引っかかってくるでしょうか?彼らの演奏するショパンには好みどうこうよりもやはり何か惹かれるものがあるように思います。
さて、ショパンコンクールが今年開催されるそうです←SNS見るまで知らなかった笑
ショパン国際ピアノコンクールの理念として「ショパンの解釈者を発掘すること」を掲げているようです。この翻訳は難しいですね。ここでの「解釈者」とは伝統的な解釈者なのか、革新的な解釈者なのか。恐らく前者ではないかと思います。
ここからはただの音楽好きの感想として流してもらいたいのですが、前者で考えるならばそういった演奏は1990年代からほぼ絶たれたと言っても過言では無いと思います。もちろん「あぁやっぱりショパンってそうだよな!」って演奏もごく稀に耳にしますが、そのような演奏が本選まで残ることも稀なもんで。
現在予備予選が行われています。同じような曲を何人も続けて聴くのはとても面白いですね。同時に、「薬にも毒にもならない演奏」というのがとてもしっくりきます。ここでいう「毒」というのは1980年のポゴレリチのような演奏のことです。
ピアノをやっと弾いてる私なんかからすれば、予備予選に出るだけでみんな凄いし天と地がひっくり返ったってあんな演奏私には出来ませんが、好き勝手言わせてもらえるのならばそんな感想でしょうか。
それと予備予選を「見て」とても気になったのが奏者の顔です。いや、美男美女って意味じゃなくね。もはやみんな名前の情報だけで審査したほうがいいんじゃないでしょうか?弾きながら「あれ〜どっか行っちゃうの?」、「お腹痛いの?」と心配しちゃうくらいの表情。「分かった、分かったからその表情を音にしてくれよ」というのが聴く側の気持ちでしょう。ホロヴィッツもそんなことを言ってますよね(すまんホロ爺、盾になってくれ😂)。この表情コンクールも1990年以降どんどん増えたように思います。それは映像技術の発展もあるのでしょう。このように生配信なんてもの考えられませんでしたものね。
それこそユンディ・リが優勝した時だったでしょうか、当時審査員をしていた中村紘子さんが「新しいスターを探している」というようなことを話してました。今思えばそれは理念に反しているんではなかろうか?そうではなく、ショパンの思い描いたショパンの音楽観を継承していく人材を発掘するためのコンクールなのでしょう?まぁ中村さんの言葉はその前後があるでしょうから本意は分かりませんが。革新的な解釈は他のコンクールに任せて、ショパンの名を冠しショパンしか演奏しないコンクールなのだから、そこは厳しくすべき部分ではなかろうかと思うのが正直なところですね。
もはやピアノメーカーとその技術者のためのコンクール、ポーランドの観光資源になりつつあるような印象を受けますね。あくまでも演奏の好みではなく、バロック音楽を追究するなかで私に見えているショパンの話なのでズレがあることは認めますので怒らないでほしいんですが笑
もう演奏中は手元だけの映像でいいよって感想が最初に来るのもどうかと思いますけれどもね笑
「良い演奏」よりも「達者な演奏」が選ばれやすい感がありますね。
帰省中、テレビでどうやってYouTubeを見るのかを父に教え込むのが大変でした😂毎晩楽しそうに見る父とあーだこーだ言いながら見る予備予選は楽しいものでした。さてさて、親父が言った人と俺が言った人、一次予選で聴けるかな〜💡