
「箸の上げ下げでお里が知れる」この言葉を聞いて「ぎくり」とします。
もうすぐお正月。御呼ばれしたり、孫たちも揃って一家の帰省とか食事を楽しむ機会が増えることでしょう。
旧皇族の竹田恒泰氏のご指南を読んでいましたら、小生、結構マナー違反を致して居ることを恥じ入りました。
食事どきのマナーです。
同氏によれば日本では古くから箸を神事に用いてきた、とされています。
元々、箸は神霊の宿るもの。宮中で行われる新嘗祭では箸は神人共食の祭器とされています。
例えば伊勢神宮では毎日神前にお食事と一緒に箸が供されています。
古来、唾液が付く箸には使った者の魂が宿るとされ、箸と茶碗と味噌汁茶碗などはそれを使う者の分身として
大切に扱われています。
食事中のマナー。第一に箸は丁寧に扱わねばならない。箸に対して常に意識を向けねばならない。
第二に、箸は綺麗に使わなくてはいけない。昔から箸先の汚れは1寸(約3センチ)以内といわれる。
箸先だけで食事するのは、小分けして口に運ぶことで、ゆっくり食事するようになる。
唾液も出やすくなり、健康的な食べ方でもある。
この2つが箸の作法で大切だそうです。
さて、小生の違反は
「渡し箸」箸休めの時に、箸を横にして器の上に乗せること。ただし、箸置き・御膳などない場合は作法の外であり、
許されるそうです。
「涙箸」汁が垂れやすい料理など「手皿」といって左手を受皿にするような所作。
これは汁気をしっかり切ってから運ぶべき、とあります。最も優雅なのは懐紙を使用すること。
「ちぎり箸」箸を左右に1本づつ持って、ナイフとフォークを使うように食べ物をちぎる行為は禁忌とされるそうです。
今までいくどか経験があります。
長年、上記のようなマナー違反をしておりました。
上記の3つのタブーの他、箸には多くの禁忌があり、それらは「忌み箸」とか「嫌い箸」と呼ばれています。
握り箸・寄せ箸・刺し箸(食べ物に箸を刺す)・探り箸・迷い箸・空箸・移り箸・もぎ箸・横箸・噛み箸・移し箸・
ねぶり箸・持ち箸・押し込み箸・指し箸・立て箸(亡くなった方に使います)などなど。
この年齢になって日本の礼儀作法の一端を知りました。
お正月には孫たちにも箸の使い方を優しく教えなくては、と思っている次第です。











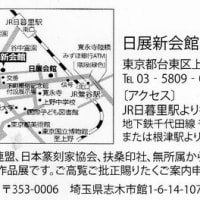
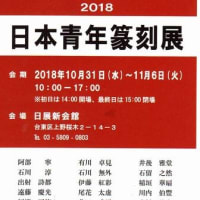
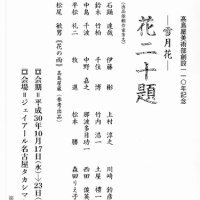



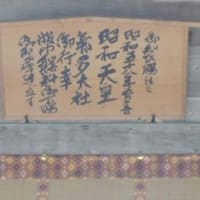


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます