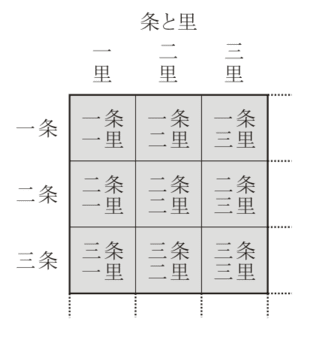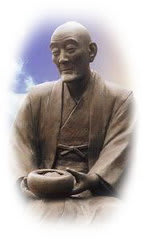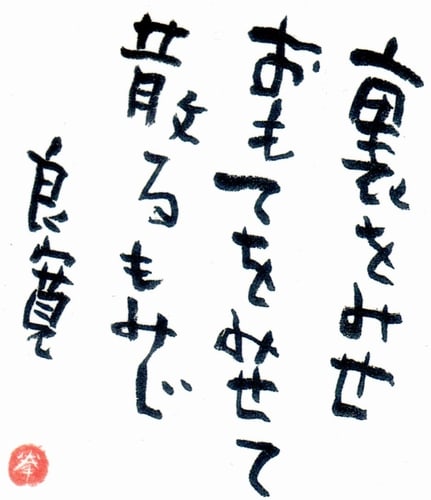「ところてん」(心太)は夏の風物詩です。
先般、菩提寺で永代経の行事があり、お参りに行ってまいりました。
お経やお説教の行事が終わり、最後に「ところてん」のお接待がありました。
最近は「ところてん」を味わう機会もすっかり減りましたが、喉をツルツルと冷たく、すべり良く通る
瞬間がとても気分のよいものです。
つい昔を思い出しましたが現在のスーパーでの売り物と異なり、羊羹のような長い「ところてん」を
器具を使って細く押し出し、それを口に運ぶ一連の流れが子供にとって楽しいものでした。
ところで、この地方だけかも知れませんが、食べるときは箸1本だけです。
別に不自由はありませんが少し不思議な感じもいたします。
理由は後からのこじつけかも知れませんが
*昔は箸が高価だったため1本の箸だけで食べた
*「ところてん」は「食事」か「おやつ」かを区別するために箸1本にした
その他、色々説があるようです。
でも1本で味わうのはちょっと粋な感じではあります。
今朝、TVで「ところてん」を箸2本で食べるシーンがありましたが、長年1本の箸で味わう習慣のせいかも
知れませんが確かに食事のようで、ちょっと違和感がありました。
所が違えば習慣も違うということでしょうか。
「ところてん」は自然食品、カロリーも少なく、食感もよく、日本っていいなあ・・・