甲府城は、浅野長政・幸長親子が完成させました。
加藤光泰病死後、豊臣五奉行の筆頭浅野長政が甲斐国の支配を任されていましたが主に大阪にいたため幸長が甲斐の支配を行っていました。関が原の合戦に、東軍について出陣、勝利し紀州和歌山に移封しました。甲斐の国は、徳川の支配に入ります。
長政の三男、長重が赤穂浪士で有名な赤穂浅野家の初代です。
その浅野家が家紋としていたのがこれ

「丸に違い鷹の羽紋」です。
鷹の羽のことで、日本の和弓に用いられる矢の矢羽根の材料です。
鷹は武人を表すとされ、武家に人気がありました。
鷹の羽紋だけで60種以上あるそうです。江戸時代には、120余の大名・旗本が使用していました。
阿蘇神社が「違い鷹の羽」を神紋として起用している影響で、南九州に多く分布しています。
武士が多く用いた紋であることから、武家政権があった土地に多いのも特徴だそうです。 (さ)
加藤光泰病死後、豊臣五奉行の筆頭浅野長政が甲斐国の支配を任されていましたが主に大阪にいたため幸長が甲斐の支配を行っていました。関が原の合戦に、東軍について出陣、勝利し紀州和歌山に移封しました。甲斐の国は、徳川の支配に入ります。
長政の三男、長重が赤穂浪士で有名な赤穂浅野家の初代です。
その浅野家が家紋としていたのがこれ


「丸に違い鷹の羽紋」です。
鷹の羽のことで、日本の和弓に用いられる矢の矢羽根の材料です。
鷹は武人を表すとされ、武家に人気がありました。
鷹の羽紋だけで60種以上あるそうです。江戸時代には、120余の大名・旗本が使用していました。
阿蘇神社が「違い鷹の羽」を神紋として起用している影響で、南九州に多く分布しています。
武士が多く用いた紋であることから、武家政権があった土地に多いのも特徴だそうです。 (さ)










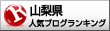
















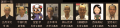

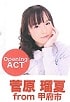

 甲斐国分寺跡に行ってみよう!!
甲斐国分寺跡に行ってみよう!!


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます