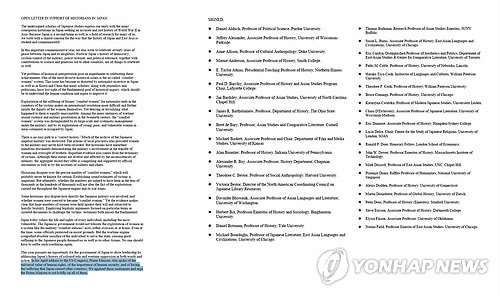※木下裕也先生の「教会・国家・平和・人権―とくに若い人々のために」記事を連載しています。
 木下裕也(プロテスタント 日本キリスト改革派教会牧師、神戸改革派神学校教師)
木下裕也(プロテスタント 日本キリスト改革派教会牧師、神戸改革派神学校教師)
大正デモクラシー
明治の時代には、何はともあれ第一の関心事は国家でした。明治維新という大きな転換点を経験した人々にとっては、新しい国家をどのように築いていくのかということこそが共通の課題であったのです。
しかし大正の時代になると、あきらかな変化が生じます。アジアにあって西欧の国々にもわたりあっていける強い国をつくるという目的は、ある程度果たされました。日清戦争、日露戦争に勝利し、朝鮮を植民地とし、大正期の日本は一方では帝国主義国家への道をさらに先へと進んでいくことになります。
...他方、明治国家のさまざまなほころびがあらわれてくるということもあり、人々はようやく個人の意識に目覚め、個人の権利や個人的な幸せをもとめるようになります。そして大正デモクラシーと呼ばれる民主主義運動が起こり、国民ひとりひとりが政治に参加していこうとする機運がたかまっていきます。
国民のひとりひとりが自分の権利を守り、生活を安定したものとし、幸福を得るためには、自分も政治に参加し、政治をよくしなければなりません。そのために大切なのは選挙権です。けれども大日本帝国憲法のもとでは基本的人権は保障されておらず、国民の自由や権利もおおはばに制限され、選挙権も限られた人々にしか与えられていませんでした。それゆえ、大正デモクラシー運動はまず普通選挙【注1】権を獲得する運動として始まりました。だれもが政治に参加できる権利を得ることにより、明治の専制政治【注2】に抵抗し、政党が政治を運営していく仕組みを確立することを目標としたのです。
当時デモクラシーは世界的な風潮でした。そのことも追い風となって、大正デモクラシーはさまざまな民衆運動もまきこんだ大運動となり、1918年には日本最初の政党内閣【注3】を誕生させ、1925年には日本最初の男子普通選挙法【注4】を成立させる等の成果をもたらします。
大正デモクラシーの立役者となったのは、当時東京帝国大学法科大学教授であった吉野作造【注5】です。吉野がとなえた民本主義という学説が、この運動を支えました。大日本帝国憲法の枠の中で、できるかぎり民主主義的な政治のありかたをもとめようとしたもの【注6】で、注目すべき学説です。ただ、この時期にはすでに天皇主権の国家のかたちが固まってしまっていましたから、そのありかた自体をくつがえすものとはならなかったのです。
【注1】身分や性別、教育や財産のちがいによって制限されない選挙。
【注2】君主や身分の高い支配者が思うままに民を統治する政治のありかた。大日本帝国憲法では、国会は貴族院(皇族、華族、税金を多く納めている者や学者たちから天皇によって任命された議員からなる)と衆議院により構成されており、衆議院に持ち込まれた国民の思いや願いが貴族院によってしりぞけられてしまうことがしばしばでした。貴族院は普通選挙にも反対していました。
【注3】首相は原敬(はら・たかし)(1856~1921)。
【注4】それまで選挙権は一定額以上の税金を納めている満25歳以上の男子にかぎられていましたが、ここで満25歳以上の男子すべてに選挙権が与えられました。しかしこのときにも女性の選挙権は認められませんでした。
【注5】1878~1933。東京帝国大学法科大学教授。
【注6】同じような学説に美濃部達吉(1873~1948、東京帝国大学法科大学教授)の天皇機関説があります。